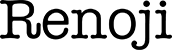Life
FOOD Life
Topics
「料理」の「盛り付け」を「魅力的」にする方法「レトルトパックフード」の美味しい「食べ方」「化膿・炎症」を抑える「坑炎症作用」のある「食べ物」注意が必要な「食べ合わせ」の悪い「食べ物」健康への悪影響が心配される食べ物知っていると役立つ「食べ物の知識」Recipe(レシピ)
美味しい「味付け」をする「方法」美味しい「カレー」の「作り方」美味しい「ジェノベーゼソースパスタ」の作り方美味しい「ピクルス(酢漬け)」の作り方美味しい「ハム」の作り方美味しい「ベーコン」の作り方美味しい「チーズ」の作り方美味しい「バター」の作り方美味しい「ホイップクリーム」の作り方調味料
美味しい「柚子胡椒」の作り方美味しい「かぼす胡椒」の作り方食材
炭水化物
「パン」の美味しい「食べ方」「お米」の美味しい「食べ方」肉類
「牛肉」の美味しい「食べ方」「豚肉」の美味しい「食べ方」「鶏肉」の美味しい「食べ方」「牛ホルモン」の美味しい「食べ方」「ハム」の美味しい「食べ方」「ベーコン」の美味しい「食べ方」魚類
「魚」の美味しい「食べ方」「アサリ」の美味しい「食べ方」「雲丹(ウニ)」の美味しい「食べ方」卵類
「卵」の美味しい「食べ方」野菜
「タマネギ」の美味しい「食べ方」「大根」の美味しい「食べ方」「ジャガイモ」の美味しい「食べ方」「ホウレンソウ」の美味しい「食べ方」「トマト」の美味しい「食べ方」フルーツ
「レモン」の美味しい「食べ方」「みかん」の美味しい「食べ方」「いちご」の美味しい「食べ方」「梅」の美味しい「食べ方」乳製品
「チーズ」の美味しい「食べ方」「バター」の美味しい「食べ方」甘味料
「はちみつ」の美味しい「食べ方」スパイス
「スパイス」の美味しい「食べ方」「マスタード」の美味しい「食べ方」「からし」「和からし」の美味しい「食べ方」「唐辛子」の美味しい「食べ方」調味料
「お酢」の美味しい「使い方」「みりん」の美味しい「使い方」飲み物 & アルコール
「ビール」の美味しい「食べ方」調理器具
「フライパン」を「綺麗」に維持する方法新しい「アルミ製調理器具」を使うための「下準備」をする方法
【食材】「梅・梅干し」の美味しい「食べ方」
【食材】
「梅・梅干し」の美味しい「食べ方」
「梅・梅干し」の美味しい「食べ方」
INDEX
■ はじめに
■ 「梅」とは
■ 「梅干し」とは
■ 「梅干し」の悪い効果(デメリット)
■ 「梅」の効能
■ 「梅」は、「アルカリ性食品」
■ 「梅」に含まれる「クエン酸」には「疲労回復効果」がある
■ Gallery
はじめに
「梅」と言えば、
「日本」では「梅干し」が知られている。
料理に少し使用すると、
とても美味しい「薬味」だったりする。
「酸性」の「食べ物」のようで、
食べると「体内」を「アルカリ性」にしてくれる修正もある。
Back
「梅」とは
「梅」は、
バラ科サクラ属の木で、
木自体を「梅」という名称ですが、
その果実のことも「梅」という。
その中でも、
果実を利用する品種は、
「実梅」という扱いになるらしいです。
知らなかったのですが、
「梅」の果実で、
未熟なものには、「有毒」なものもあるとのこと。
ご注意下さい。
「梅」の木の「枝」「樹皮」は、
「染色」に使用することもできるそうです。
Back
「梅干し」とは
「梅干し(うめぼし)」は、
「梅の果実」を塩漬けし、
天日干しして作られる日本の伝統的な保存食。
「強い酸味」と「塩味」が特徴。
古くからおにぎりや弁当の具材、薬膳としても親しまれてきた。
梅干しの定義と製法
・梅漬け(梅の果実を塩漬けしたもの)・梅干し(梅漬けを天日干ししたも)
・調味梅干し(梅干しを蜂蜜・鰹節・昆布などで味付けしたもの)
伝統的な梅干しは、塩分25〜30%と高め。
最近は、塩分10〜20%の減塩タイプも多く流通している。
歴史と文化的背景
「梅干し」は、平安時代には薬として用いられ、
「三毒を断つ(血毒・水毒・食毒)」と記された医学書も存在するらしい。
戦国時代には、
戦場での食中毒予防や傷の消毒に使われ、
戦略物資として梅の植林が奨励されていたとのこと。
江戸時代以降になると、
庶民にも広まり、
赤紫蘇漬けや甘露梅など
多様な製法で作られるようになった。
Back
「梅干し」の悪い効果(デメリット)
「梅干し」の悪い効果(デメリット)は、
個人差によるので、1日2~3粒ぐらいから注意が必要になる。
「梅干し」を食べ過ぎると、
一番気を付けたいのが、「塩分過多」。
内臓だけでなく、
体のむくみも引き起こします。
地味ですが、
ボディブローのように、身体にダメージを与えてしまう。
「梅干し」の「悪い効果(デメリット)」一覧
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| 塩分過多 | 高血圧・腎臓への負担・むくみの原因になる |
| 胃への刺激 | 空腹時に食べると胃痛や胸焼けを引き起こす可能性 |
| 歯へのダメージ | 酸がエナメル質を溶かし、虫歯や知覚過敏の原因に |
Back
「梅」の効能
「梅」の効能には、
・疲労回復
・高血圧改善
・動脈硬化予防
・便秘解消
・肌トラブルの解消
・血液サラサラ硬化
・腎臓病予防
・ダイエット効果
などがあると言われています。
「疲労回復」に「クエン酸」
「梅」には、「クエン酸」が豊富に含まれています。
「梅干し」にすることで、
「クエン酸」の量がアップする不思議な「梅干し」。
「クエン酸」は、
疲労物質「乳酸」を分解してくれるので、
「疲労回復」に効果があります。
| 効果 | 説明 |
|---|---|
| 疲労回復 | クエン酸が疲労物質の乳酸を分解し、疲労を回復。 エネルギー代謝を高め、疲れにくい体に。 |
| 整腸作用 | 有機酸が腸内の悪玉菌の繁殖を抑制し、善玉菌を増やす働きをする。 |
| 抗菌・抗ウイルス作用 | 免疫力が向上するので、風邪予防に効果的 |
| 血流改善・血液サラサラ効果 |
血液をサラサラにし、冷え性や生活習慣病の予防に役立つ。 「梅肉エキス」に「熱」を加えると、 「ムメフラール」という成分が作られ、 血液中の「血小板」の「凝集」を防ぐ働きがあるとのこと。 1日に「耳かき1杯分」を摂取するだけで、 血液がサラサラになるとのこと。 |
| 美肌効果・老化防止 |
クエン酸の抗酸化作用で、シミ・シワの予防や老化防止に。 |
| 肝臓ケア | 有機酸が肝機能を活性化し、二日酔いの軽減にも |
| 自律神経の調整 | クエン酸と塩分が交感・副交感神経のバランスを整える |
| 高血圧改善 |
「高血圧改善」の効果もある「梅」。 「クエン酸」が分解してくれる疲労物質「乳酸」は、 「動脈硬化」の原因にもなっており、 「乳酸」を分解することで、 「血圧」を下げる働きもあることが明らかになったそうです。 「梅」のエキスを濃縮した「梅肉エキス」は、 「塩分」を含まないので、 「梅」の良い所だけ摂取できる優れモノ。 |
| 便秘解消 |
「梅」には、 「腸壁」を刺激し、「煽動運動」を即す効果があるとのこと。 毎日、「梅干し1個」を食べると、 便秘が自然に解消される効果があるそうです。 自然と、腸内が綺麗になり、「肌」が綺麗になり、 「肌トラブル解消」にも繋がるそうです。 |
| 解毒作用 |
「梅」には、 強い「解毒作用」があり、 「腎臓」の働きをサポートしてくれる効果があります。 「腎臓」は、身体の「新陳代謝」を担っているので、 自然と「新陳代謝」が活発になります。 「梅肉エキス」で摂取をすると、 「腎臓」の大敵となる「塩分」が少ないので、 更に良い効果が期待できます。 |
| 抗炎症作用 |
「梅」の「クエン酸」は、 「体内」で代謝されると「アルカリ性」になるので、 「体内の酸性度」を「中和」する働きもある。 「酸性」のカラダになると、炎症が起きやすいので、 「アルカリ性」の身体になる事は、「抗炎症作用」が働く事になる。 |
| 脂肪燃焼効果 | |
| 便秘予防や肥満の抑制 | |
| 抗アレルギー効果 | |
| 抗腫瘍作用のがん予防 | |
| 動脈硬化の予防効果 |
Back
「梅」は、「アルカリ性食品」
「梅」は、
その酸味から「酸性」の食べ物と思われがちだが、
実は「アルカリ性食品」に分類される。
「梅」は、
「クエン酸」を多く含み、
「クエン酸」自体は、「酸性」。
しかし、
「体内」で代謝されると「アルカリ性」になるので、
「アルカリ性食品」とされる。
加えて、
「梅」に含まれる、アルカリ性のミネラル「カリウム」などが、
「体内の酸性度」を「中和」する働きもある。
「体内」で「アルカリ性」になり、
「アルカリ性食品」に分類される「梅」は、
摂取することで、
「酸性食品」を摂取しがちの現代人の
「身体の酸性化」を防ぐことができる。
Back
「梅」に含まれる「クエン酸」には「疲労回復効果」がある
「クエン酸」には、「疲労回復効果」があり、
運動後や体調が優れない時に「梅干し」を食べると、
「エネルギー代謝」を活発にし、「疲労回復」を促す。
さらに、
「クエン酸」には、「血液」を「サラサラ」にする効果も期待できる。
Back