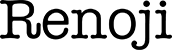旅メモ
旅メモ【日本編】
旅Memo【関西地方編】
旅Memo【京都府編】
Topics
「京都府」の「基本情報」「京都市」を構成している「11区」の「区割り位置」「京都府」の「アウトドア」「旅」に役立つ「旅情報」
「京都府」の「定番スポット」「京都府」にある「愛犬同伴OK」の「旅スポット」「京都府」にある「各宗派の大本山」Area
古都「京都(京都市)」【京都市東山区】清水寺【京都市東山区】高台寺【京都市東山区】八坂神社【京都市左京区】下鴨神社【京都市左京区】銀閣寺【京都市左京区】平安神宮【京都市左京区】南禅寺【京都市上京区】京都御所【京都市上京区】晴明神社【京都市中京区】元離宮二条城【京都市中京区】御金神社【京都市下京区】京都駅【京都市北区】金閣寺【京都市北区】上賀茂神社【京都市伏見区】伏見稲荷大社【京都市右京区】嵐山【京都市右京区】天龍寺【京都市右京区】竜安寺【京都市伏見区】醍醐寺【宇治市】平等院【宇治市】宇治上神社【宮津市】天橋立【与謝郡】舟屋の里「伊根」旅グルメ
「京都府」を訪れたら食べたい美味しそうな「御当地グルメ」「京都府」にある美味しそうな「回転寿司店」「京都府」にある美味しそうな「焼肉店」旅の宿
「京都府」にある魅力的な「旅の宿」「京都府」の「日帰り入浴施設」「京都府」にある「愛犬」と一緒に宿泊できる「旅の宿」「京都府」にある「仮眠」「車中泊」ができる「スポット」
【京都市 東山区】「豊臣秀吉」公の「菩提寺」として創建された「高台寺」
【京都市 東山区】
「豊臣秀吉」公の「菩提寺」として創建された「高台寺」
INDEX
はじめに
 *Image is 高台寺
*Image is 高台寺「清水寺」と同じ東山区にある「高台寺」。
「三寧坂」「二寧坂」を歩いて、「清水寺」から歩いてくると、
「高台寺」にたどり着きます。
さらに進むと「八坂神社」「円山公園」「知恩院」「祇園」などに歩いて行ける。
「高台寺」は、「豊臣秀吉」公を弔うため、 正室「ねね」様が、「菩提寺」として建立されたお寺。
落ち着いた綺麗な庭園などが広がっています。
すぐ近くに、
「豊臣秀吉」公の妻「ねね」様の最後の居所だった住居が
「お寺」になった「圓徳院」もあります。
とても綺麗な庭園や、
住居だった建物を見学できるので、
「高台寺」と一緒に参拝するのがおすすめ。
 「豊臣秀吉」公と「ねね」様の「霊廟」もあり、
「豊臣秀吉」公と「ねね」様の「霊廟」もあり、「豊臣家」にゆかりの深い場所となっています。
 「高台寺 利生堂」には、
「高台寺 利生堂」には、お釈迦様が亡くなった時の様子を描いた「涅槃図」が、
天井に描かれています。
天井の「涅槃図」は、
650年前の南北朝時代に描かれた「八相涅槃図」。
「高台寺」に所蔵されているものを、
最新技術によって、天井に再現したとのことです。
貴重な空間にも関わらず、
「写真撮影OK」となっていました。
綺麗な「涅槃図」なので、一見の価値があると思います。
Back
「高台寺」は「愛犬同伴NG」
「高台寺」は「豊臣秀吉」公と「ねね」様のゆかりの「旅スポット」
 *Image is 高台寺 霊屋
*Image is 高台寺 霊屋
Address : 〒601-1325 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22
「三宝院 庭園」は、「豊臣秀吉」公が自ら作庭した「庭園」。
「京都」には、
「豊臣秀吉」公にゆかりのある場所が多くあります。
代表的な「豊臣秀吉」公にゆかりのある場所は、
「豊臣秀吉」公が祀られている「豊国神社」。
「豊臣秀吉」公のお墓「豊国廟(とよくにびょう)」も、「京都市内」にある。
明治時代に、お墓の修繕をするときには、
「豊臣秀吉」公のミイラ化したご遺体が確認されていたそう。
形見として分けられた「豊臣秀吉」公の歯も、
「豊国神社」で見ることができるそう。
「豊国神社」の「宝物館」には、
「豊臣家」や「秀吉」公に関する「名品・珍宝」がたくさん収められ、展示されているそうです。
「豊臣秀吉」公を祀る神社
「豊臣秀吉」公のお墓
「ねね」様が「豊臣秀吉」公の菩提を弔うために建てた「菩提寺(お寺)」
「豊臣秀吉」公の正室「ねね」様が住まわれた最後のお住まい
「豊臣秀吉」公が自ら作庭した「醍醐三宝院の庭園」
Address : 〒601-1325 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22
「三宝院 庭園」は、「豊臣秀吉」公が自ら作庭した「庭園」。
初代「伏見城(指月伏見城)」は「豊臣秀吉」公が築城した「お城」
Address : 〒612-8034 京都府京都市伏見区桃山町泰長老126−27
「豊臣秀吉」が最初に作った「伏見城」の跡。現在は遺跡のみ。「伏見桃山城」は、テーマパークの一部として建設された「模擬天守」。
Back
初代「伏見城」は「豊臣秀吉」が築城したお城
 *Image is 城のイメージイラスト
*Image is 城のイメージイラスト
Address : 〒612-0831 京都府京都市伏見区桃山町古城山
3代目 伏見城「木幡伏見城」の跡地。
初代「伏見城」は、
「豊臣秀吉」が築城したお城で、
「豊臣秀吉」のゆかりが深いお城。
ですが、
歴史上に出てくる「伏見城」は、
現在、現存しているお城は廃城され、
遺跡が一部だけ街中に残っているだけ。
現在「伏見桃山城」として、
「伏見城天守跡」にあるのは、
「1964年(昭和34年)」に、
「テーマパーク」の一部として造られた「模擬天守」。
現在の「伏見桃山城」は、
「1964年(昭和34年)」に、
「伏見城」を模して鉄筋コンクリート製の「模擬天守」として建設され、
周囲には、
「伏見桃山キャッスルランド」というテーマパークが作られ、
人気となったそう。
「伏見桃山キャッスルランド」は、
2003年に閉鎖し、現在は、京都市が運営する「運動公園」として利用されている。
「模擬天守」は、
地元の人たちの要望で、現在も残っている。
現在の「伏見桃山城」は、歴史上の初代「伏見城」は「豊臣秀吉」が築城したお城、
まったく関連性がない「模擬天守」。
歴史上の「伏見城」は、
歴史上では、3度建設されているそう。
・1代目 伏見城「指月伏見城」 = 1596年(文禄5年)に完成して年に「慶長伏見地震」で倒壊
・2代目 伏見城「木幡伏見城」 = 1600年に戦により炎上・消失
・3代目 伏見城「木幡伏見城」 = 1619年(元和5年)「一国一城」の制により「廃城」が決定
という歴史的経緯がある。
最終的には、「廃城」されたことで、
他の場所に、移築されて残っている一部を見ることができる。
現存していれば、立派な城だったことが伺える。
1代目 伏見城「指月伏見城」
「初代伏見城(1代目)」の「 伏見城(指月伏見城)」は、「豊臣秀吉」が最初に作った「伏見城」で、 「京都市伏見区桃山町泰長老」あたりに築城された。
1596年(文禄5年)に完成したが、
その年の「慶長伏見地震」で倒壊。
跡地は、不明だったが、
建設工事により、「遺構」が発見され、
現在でも、「石垣」の一部が、マンション横に展示されている。
2代目 伏見城「木幡伏見城」
2代目 伏見城「木幡伏見城」は、慶長伏見地震で「指月山伏見城」が倒壊した後、
翌年(1597年)から、 「指月伏見城」の「約500m北東」の「木幡山」に、
更に大規模な城として建設が開始された。
現在「木幡伏見城の本丸跡」は、「明治天皇の伏見桃山陵」がある。
Address : 〒612-0831 京都府京都市伏見区桃山町古城山
3代目 伏見城「木幡伏見城」の跡地。
1598年に「豊臣秀吉」が亡くなった後、
「徳川家康」が城主となった。
1600年(慶長5年)「関ケ原の戦い」の前哨戦で、
「木幡伏見城」は、「徳川家康」と「西軍」の「戦場」となり、
「落城」してしまった結果、炎上・消失してしまった。
この際に、残った城の一部を
他のお寺などに寄贈・移築をした歴史があり、
「豊臣秀吉」公の正室「ねね」様の居宅となった「圓徳院」へも一部移築された経緯がここにあります。
3代目 伏見城「木幡伏見城」
3代目 伏見城「木幡伏見城」は、1602年(慶長7年)に、「徳川家康」によって、同じ場所に再建された。
「徳川家康」は、朝廷からの「将軍宣下」を、「木幡伏見城」で受けたが、
1619年(元和5年)に、「一国一城」の制が下り、
3代目 伏見城「木幡伏見城」は、「廃城」が決定した。
3代目 伏見城「木幡伏見城」の建築物や石垣は、
色々な場所で転用され、
京都では、「御香宮神社」「豊国神社」「西本願寺の唐門」などに使用されたとのこと。
そして、「明治天皇」の「崩御」に伴い、「明治天皇 伏見桃山陵」となった。
現在の「伏見桃山城」
現在の「伏見桃山城」は、かつての「木幡山伏見城」の「花畑曲輪」跡付近に建てられた
遊園地(テーマパーク)「伏見桃山城キャッスルランド」に建設された一部で、
「鉄筋コンクリート製の模擬天守」。
「伏見桃山キャッスルランド」は、「2003年」に閉鎖。
現在は、「京都市」が運営する「運動公園」として利用されている。
模擬天守の「伏見桃山城」は、現在も保存されている。
なので、
「城郭」「天守」としての再現性は低いと言われている。
「伏見城」に関連する「旅スポット」
Address : 〒612-0831 京都府京都市伏見区桃山町古城山
3代目 伏見城「木幡伏見城」の跡地。
Back
「高台寺」とは

「高台寺(こうだいじ)」は、
京都府京都市東山区にある「臨済宗建仁寺派」の寺院。
「山号」は、「鷲峰山(じゅぶさん)」。
「寺号」は、「高台寿聖禅寺」。
1598年(慶長3年)に。「豊臣秀吉」公が病死し、
「豊臣秀吉」公の正室「ねね」様こと「北政所」が、「豊臣秀吉」公を弔う「菩提寺」として建立したお寺。
お寺の名前の「高台寺」は、「ねね」様が仏門に入る時の院号「高台院」からきている。
「釈迦如来」を本尊としている「禅宗寺院」ですが、
「秀吉」公と「北政所(ねね)」を祀る「霊廟」として寺院でもある。
「ねね(北政所)」様は、1624年(寛永元年)9月に亡くなるまで、
現在の「圓徳院」の場所に、居を構えていた。
その後、「ねね(高台院)」の甥である「木下勝俊」によって、寺院「圓徳院」に居宅を変更した。
「木下勝俊」の「墓塔」も存在する。
「高台寺」の建物・庭園などは、移築・改築したものが多く、
「方丈」「茶室」などは、戦の落城により焼け残った「伏見城」の一部を移築したもの。
江戸時代末期(幕末)には、「高台寺」は、
一時期に、「新選組」から離脱した「御陵衛士(高台寺党)」の拠点となったこともある。
その後、数度の火災により、「仏殿」「方丈」などが焼失してしまい。
創建当時の建造物が現存しているのは、
「三江紹益」を祀る「開山堂」
「秀吉」と「ねね(北政所)」を祀る「霊屋(おたまや)」
茶室の「傘亭」と
「時雨亭」
など。
Back
綺麗な白砂と舞台のようにも見える廊下の「方丈前庭」

創建当時に建設された「仏殿」は、
焼失後に再建されていないので、
「方丈」が中心的な「仏殿」となっていた「高山寺」。
「方丈」は、1912年(大正元年)に再建されたもので、
創建当時には、「伏見城」の建物を移築したものだったそうです。
「方丈」の庭園「方丈前庭」は、
白い砂が敷き詰められていて、とても綺麗に整備されています。
季節にもよりますが、
「廊下」と「庭」の「白砂」「緑」「門」のバランスが良い気がします。
「庭」に向かって右側には、大きな「しだれ桜」がありました。
「春」の「桜」の季節には、
綺麗な「桜色」が「白砂」に映えそうです。
Back
「開山堂」と「ねね」様が「秀吉」公を偲んだ「庭園」

「開山堂」の境内には、
向かって左側に、「偃月池」、
向かって右側に、「臥龍池」
という2つの池をもつ庭園が広がっています。
向かって右側にある「臥龍廊(がりょうろう)」で、
「秀吉」公と「ねね」様をともらう「霊屋」と繋がっています。
「開山堂」は、
「重要文化財」にも指定されていて、
1605年(慶長10年)に、
「入母屋造本瓦葺き」の「禅宗様式」で建設された「仏堂」。
元来、北政所の持仏堂だったもので、 その後、中興開山の三江紹益の木像を祀る堂となっている。 堂内は中央奥に三江紹益像、 向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、 左に高台寺の普請に尽力した堀直政の木像を安置している。
「仏堂」の天井は、
「秀吉」公の「御座舟」の天井と、
「北政所(ねね)」様の「御所車」の天井を
移築した建物。
「開山堂」前に広がる「庭園」は、
「史跡・名勝」にも指定されていて、
「小堀遠州」作の「桃山時代」を代表する「庭園」。
「しだれ桜」と「石組み」の見事さが見どころ。
 「偃月池」に浮かぶ「観月台(かんげつだい)」は、
「偃月池」に浮かぶ「観月台(かんげつだい)」は、「書院」と「開山堂」を結ぶ屋根つき「廊」の途中にある少し広くなっている場所。
「観月台(かんげつだい)」から、「北政所(ねね)」様が、
亡き「秀吉」公を偲びながら月を眺めていた場所とのことです。
Back
「秀吉」公と「ねね」様を弔う「霊廟」

「霊屋(おたまや)」は、
「重要文化財」にも指定されていて、
「ねね」様こと「北政所」は、
自身の像の約2メートル下に葬られています。
「豊臣秀吉」公は、
京都市東山区今熊野阿弥陀ケ峯町にある「豊国廟」に葬られています。
「霊屋(おたまや)」は、
「開山堂」の一段高くなった東方の敷地にあり、
「霊屋」と「開山堂」は、
回廊の「臥龍廊(がりょうろう)」で繋がっている。
「宝形造檜皮葺き」で作られた「お堂」は、
1605年(慶長10年)に建設されたもの。
「霊屋(おたまや)」の内部は、
中央に、「大随求菩薩(だいずいぐぼさつ)」の像、
向かって右に、「豊臣秀吉」公の坐像、
向かって左に。正室「北政所(ねね)」の片膝立の木像、
 がそれぞれ安置されていて、
がそれぞれ安置されていて、「霊屋(おたまや)」の外装は、とても綺麗な装飾がされています。
「秋草」「松竹」「楽器」などの「蒔絵」が施され、
「ねね」様専用の蒔絵「高台寺蒔絵」も施されていて、 華やかな「霊廟」となっていました。
「秀吉」公と「ねね」様のお人柄なのかもしれませんが、
雰囲気の良い、穏やかで、心地の良い「霊廟」な気がしました。
Back
650年前に描かれた「八相涅槃図」が描かれた貴重な空間「利生堂」

 「高台寺」の「利生堂」には、
「高台寺」の「利生堂」には、650年前の南北朝時代に描かれた
「お釈迦様」が亡くなった時の様子を描いた涅槃図「八相涅槃図」が、
天井に描かれています。
「八相涅槃図」は、
「高台寺」に所蔵されていて、
最新技術によって、天井に再現したとのことです。
ありがたいことに、
貴重な空間にも関わらず、
「写真撮影OK」となっていました。
 真下から上を眺めた絵が綺麗で、
真下から上を眺めた絵が綺麗で、とてもよかったです。
壁には、
「お釈迦様」が亡くなられて、
悲しむ人々が描かれていました。
他では見れないものなので、
「高台寺」を訪れたら、
「利生堂」もおすすめです。
Back
「高台寺」の駐車場は広め

「高台寺」の駐車場は、
50台ぐらいが駐車できる広さでしたが、
調べたら、正確には「100台」の駐車スペースとのこと。
屋根付きではなく、平置きの砂利敷きで、日影は全くありません。
愛犬を車にお留守番させる人は、季節と天気、気温にご注意ください。
駐車場の正確な料金などの情報は、
「高台寺」オフィシャルWebからアクセスできました。
「倒変木 駐車場」のページで確認しました。
駐車料金は、
最初の1時間=600円
以後30分ごと=300円
23:00〜翌7:00の1時間ごと=100円
正月期間中は特別料金とのことでした。
「高台寺」「圓徳院」を拝観すると、
駐車場の1時間無料サービス券がもらえる特典もありました。
「売店」で、3000円以上買い物をしても、
1時間無料サービス券がもらえるとのことです。
変更になる可能性もあるので、
駐車場のサービスは、
「高台寺」の「倒変木 駐車場」公式ページをご確認ください。
「高台寺」敷地内の有料駐車場「倒変木 駐車場」の情報
| 項目 | 情報内容 |
|---|---|
| 駐車台数 |
100台 |
| 営業時間 |
24時間対応 |
| 駐車料金 |
最初の1時間・600円。 以後30分毎・300円。 23:00~翌7:00迄、1時間・100円。 *正月期間中は除く |
| 駐車サービス |
高台寺 駐車場 3大特典サービス
1、高台寺 拝観 ⇒ 1時間無料サービス券発行 2、圓徳院 拝観 ⇒ 1時間無料サービス券発行 3、賑店(土産) ⇒ 3000円以上お買い上げ時、1時間無料サービス券発行 |
Back
「高台寺」の後は「圓徳院」へもご参拝

「高台寺」から
紅葉の綺麗な長い階段を下って、
「ねねの道」を渡ると、
「豊臣秀吉」公の正室「ねね」様が、
最後に住まわれたお住まい「圓徳院」がある。
「圓徳院」は、
「豊臣秀吉」公の死後、正室「ねね」様が住まわれた邸宅が、
お寺になった寺院。
建物と庭は、
「豊臣秀吉」公と「ねね」様が親しんだ、
「木幡伏見城(2代目)」の「化粧御殿」と「庭」を移築したもの。
「木幡伏見城(2代目)」は、
「1600年(慶長5年)」の「関ケ原の戦い」における前哨戦で、
「木幡伏見城」は、「徳川家康」と「西軍」の「戦場」となり、
「落城」してしまった結果、炎上・消失してしまった。
この際に、残った城の一部を
他のお寺などに寄贈・移築をした歴史があり、
「豊臣秀吉」公の正室「ねね」様の居宅となった
「圓徳院」へも一部移築された経緯がここにある。
現在も、「ねね」様が親しんだ庭が綺麗に維持され、
眺めることができるようになっています。
Back
「圓徳院」は「愛犬同伴NG」
「圓徳院」とは

「圓徳院(えんとくいん)」は、
「京都市東山区」にある臨済宗建仁寺派「高台寺」の「塔頭(たっちゅう)」のひとつ。
「塔頭(たっちゅう)」というのは、
大きなお寺で修行した弟子たちが、協力していくために、
その近くに作ったお寺のことをいう。
戦国武将の1人「豊臣秀吉」の正室「ねね」様が、
77歳で没するまでの、晩年の19年間を過ごしたことで知られる「圓徳院(えんとくいん)」。
「ねね」様の正式名は、「高台院(こうだいいん)」で、
一般的な通称は、「北政所(きたのまんどころ)」。
「ねね」様は、「豊臣秀吉」公との間での呼び名で、手紙でも確認されているそう。
「おね」「ねい」という記述もある。
「ねね」様がお住まいの時には、
多くの「大名」「禅僧」「文化人」が、「ねね」様を慕い、訪れ、交流の場としての一面も持っていたそう。
 「圓徳院」の建物は、
「圓徳院」の建物は、「豊臣秀吉」と「ねね」の思い出が多い、「伏見城」の「化粧御殿」と「庭」を移築し、
邸宅として利用されていたそう。
 「ねね」様が、「圓徳院」にお住まいになったのは、
「ねね」様が、「圓徳院」にお住まいになったのは、「豊臣秀吉」公のの「菩提寺(お墓のあるお寺)」として建立した「高台寺」に通うため。
「圓徳院」として、お寺になったのは、
「ねね」様が亡くなった後に、
「ねね」様の甥にあたる備中国足守藩主「木下利房」が、
邸宅をお寺へと改めて創建されたことによる。
「圓徳院」の名前は、利房の院号「圓德院」をそのまま寺号としたもの。
高台寺の塔頭寺院「圓徳院」には、
現在も、「ねね」様が眺めた美しい庭園を眺めることができる貴重な歴史資産。
安置されている「三面大黒天」は、
「豊臣秀吉」公の「念持仏」として伝わるもの。
 「小堀遠州」が整えた「北庭」は、
「小堀遠州」が整えた「北庭」は、「旧円徳院庭園(きゅう えんとくいん ていえん)」として、
国の「名勝」に指定されている。
他にも、
「長谷川等伯」の筆による「襖32面」の「墨画」も、国の「重要文化財」に指定されている。

Back
「圓徳院」近くのお蕎麦屋さん「波ぎ茶寮」

 店内は、風情のある日本的なインテリア。
店内は、風情のある日本的なインテリア。庭を眺めながら、食事ができるお蕎麦屋さん「波ぎ茶寮」。
京都らしい雰囲気で、
お蕎麦を楽しめるので、
居心地が良いお店でした。
 「お蕎麦」「天ぷら」の盛り付けも綺麗。
「お蕎麦」「天ぷら」の盛り付けも綺麗。空いている夕方ぐらいの時間帯がおすすめ。
賑やかな「ねねの道」沿いにあるお店ですが、
観光客で賑わっている雰囲気は、
全く感じない店内。
観光で疲れた後に、一休みするのにちょうど良いお店かもしれません。
Back