【PetLife】「愛犬」が「高齢」になったらしておくべきこと
【PetLife】
「愛犬」が「高齢」になったらしておくべきこと
INDEX
■ はじめに
■ 「酸素ルーム」の設置
■ 最後の亡くなるときの希望の場所を決めておく
■ お世話になる動物病院を決めておく
■ 動物病院の定休日の対応を決めておく
■ 動物病院での入院中ケアは、一般的なケアだと知っておく
■ 動物病院は、愛犬にとって完璧なケアはしてくれないことを知っておく
■ 自宅でのケア内容によっては、入院も危険になることを知っておく
■ 初めての動物病院での入院は、隠れた危険性があることを知っておく
■ 獣医師の治療計画と終活計画をすり合わせて、自身で方針を決めるようにする
■ 歩けなくなってからの入院は注意
■ 流動食を準備しておく
■ 食事サポートツールを用意しておく
■ リカバリーウェア(回復ウェア)を利用する
■ 抱っこツールを準備しておく
■ 歩行サポートツールを準備しておく
■ 体力がなくなったら「ドッグカード」で移動する
■ Gallery
はじめに

「愛犬」が歳を重ね、老犬になってくると、
身体に合わせて、色々なケアが必要になる。
体力がなくなり、病気になりやすくなる。
食事量も減り、体重が減ってくる。
それらに合わせて、
必要なツールが色々と出てきたり、
動物病院での注意点なども出てくる。
愛犬の急病などに直面すると、
その時にベストな判断が出来ないこともある。
事前に、できるだけ準備と決定をしておくのがおすすめ。
Back
「酸素ルーム」の設置
愛犬が老犬になって、
急病になった時に、一番後悔したのが、
「酸素ルーム」を自宅に用意しておかなかったこと。
呼吸が苦しそうになった時に、
救急外来を訪れ、
苦しいときに、知らない場所に愛犬を1人残さないといけなかった。
自宅に「酸素ルーム」があれば、
自分で万全のケアをしながら、お世話が出来たので、
「酸素ルーム」を自宅に用意していなかったのは、
かなりの後悔になった。
レンタルの「酸素ルーム」もあるが、
早くても、翌日の昼過ぎになる。
レンタル商品の在庫がなければ、借りることも出来ない。
愛犬が老犬になったら、
「酸素ルーム」だけは、いつでも接地できるようにしておきたい。
「高濃度酸素」は、
健康や回復にも効果があるので、
人にも良い効果があるらしい。
愛犬と人の両方で利用できるので、日常から利用することもできる。
「酸素ルーム」に必要なアイテム
・酸素濃縮器・酸素濃度測定器
・酸素ルームゲージ
「酸素ルーム」を自宅に設置する場合は、
「酸素濃縮器」「酸素濃度測定器」「酸素ルームゲージ」が必要になる。
一番のポイントは、「酸素濃縮器」で、
医療用の高価なものから、家庭での健康用のものまである。
医療用と健康用の違いは、
医療機器としての認証の有無と、
それに伴う安全性や信憑性、基準などが異なる。
酸素濃度の流量や安定性が、異なってくるそうです。
「酸素濃縮器」は、
元気なうちから用意をして、活用しておくと良い。
具合が悪くなってから準備をすると、
早くても数日は必要になる。
動物病院では、
「酸素ルーム」をレンタルしている業者を紹介してくれる。
レンタル業者を利用すると、
早くて翌日の夕方ぐらいから、自宅に酸素ルームを設置できることがあるらしい。
利用している動物病院で、確認すると良い。
Back
最後の亡くなるときの希望の場所を決めておく

愛犬が亡くなるとき、
どこで、息を引き取るかを決めておいてあげた方がよい。
寂しがり屋の愛犬なら、
最後は、家族と一緒にいたいと思う。
入院をするときも、
このまま入院させるか、
一緒に連れて帰るか、
のどちらを選択するかを決める判断材料にもなる。
そして、
自宅で、最後を過ごすことを決めたのなら、
苦しまないように、最善の準備をする必要もある。
呼吸器系で苦しむ愛犬の場合は、
「酸素ルーム(高濃度酸素製造機)」は必須となる。
食事が取れない愛犬なら、
流動食や食事ツールも新たに用意しておく必要がある。
まだ元気だからではなく、
必要になるものを元気なうちから用意して、
実際に慣れさせておく事も必要となる。
動物の習性として、はじめてのものは、
驚いて拒絶することが多いのを覚えておく。
Back
お世話になる動物病院を決めておく

動物病院は、
いきなり訪れても、完璧な対応をするのが難しいことを知っておこう。
犬は喋ることが出来ず、 痛い場所や、不調の場所、現在の病状などを伝えることが出来ない。
そのため、
緊急で、初めての動物病院を訪れると、
薬を投与して、
様子を経過観察することが多いそう。
通う動物病院を決めて、
普段からお世話になっている場合は、
できるだけ同じ動物病院を訪れる方が良い。
夜間や休診日ということもあるだろう。
緊急診療を訪れたら、
翌日には、いつもの動物病院を受診する方が良いと思う。
お世話になる動物病院は、
愛犬が元気なうちに、ケガや、予防注射、定期健診などで訪れて、
病院や獣医師さんの人柄などを見て、
最後までお世話になれそうかを模索すると良い。
動物病院とは、相性もあるので、
良いと感じる人もいれば、いまいちと感じる人もいると思う。
自分にあった動物病院を探すと良い。
Back
動物病院の定休日の対応を決めておく

いつも訪れている動物病院には、「休診日」が必ずある。
その休診日に、
愛犬の具合が悪くなることがある。
その時に、
他の動物病院を受診するか、
翌日まで待って、いつもの動物病院を訪れるか、
の選択をする事になる。
救急外来を行っている24時間対応の病院を
もう一つの動物病院として、
利用することを想定しておくと、
緊急時の受診もできるので、良いと思う。
グーグルマップなどの「評価」「コメント欄」を見ると、
その動物病院の評判が把握できる。
あまりにも評判が悪い動物病院は、避けた方が無難。
コメント欄の内容によって、
その動物病院に置いて、注意するポイントや、
自身がどう行動すればよいかもわかるので、
必ず調べておいた方が良い。
Back
動物病院での入院中ケアは、一般的なケアだと知っておく

緊急で、
動物病院に入院することがあるが、
手のかかる愛犬の場合は、注意が必要。
動物病院だからと言って、
自身が行っている愛犬へのケアと、
同等のケアが行われることは難しいと思っていた方が良い。
人見知りだったり、
ご飯を食べられなくなっていたり、
起き上がれなかったりする場合は、
受診した際に、必ず伝え、入院させても大丈夫か、
入院状態によっては、ご飯を食べさせに訪れるべきかなど、
色々なことを相談して決める必要がある。
何も伝えないと、
点滴で栄養補給はするが、
栄養状態が悪くなったりして、状態が悪化する可能性もある。
Back
動物病院は、愛犬にとって完璧なケアはしてくれないことを知っておく

動物病院といっても、
愛犬にとって完璧なケアをすることができないことを知っておく。
これは、動物病院や看護師さんが悪いのではなく、
毎日一緒にいる飼い主以上のケアを、
動物病院や獣医師さん、看護師さんがするのが難しいというだけ。
忙しい、獣医師さんや看護師さんが、
飼い主と同じようなケアをすることができるかを考えれば、
誰も悪くないことがわかるだろう。
愛犬が安心して、
ケアを受け入れられるのは、飼い主だけだから。
もし、
動物病院では、十分なケアが難しい場合は、
自身で、訪れてケアをしてあげる事も考えた方が良い。
Back
自宅でのケア内容によっては、入院も危険になることを知っておく

動物病院に入院したとしても、
あまり安心できないこともある。
愛犬の症状が重篤な状態の時や、
自身で食べ物を食べれなかったりする時などは、
獣医師さん、看護師さんへ伝えて、
対策をしてもらうか、自身で訪れてケアをする必要がある。
それらのケアを怠ると、
症状が悪化する可能性がある場合は、
事前に、
獣医師さん、看護師さんと相談をして、
万全の体制を整えた方が良い。
Back
初めての動物病院での入院は、隠れた危険性があることを知っておく

初めて訪れた「動物病院」での入院では、
愛犬の「性格」「病状」「特性」「習慣」「好み」「体力」「過程」が、
まったくと言ってわからない状態からスタートなので、
多くのケアが必要な愛犬の場合は、
かなり慎重に対策をしないと、
気付いたら、病室で亡くなってしまう可能性すらある。
できる限り、
いつも訪れている動物病院で受診することが良いのだが、
初めての動物病院での入院が必要になった場合は、
とても慎重に判断した方が良い。
Back
歩けなくなってからの入院は注意

歩けなくなってから、動物病院へ入院するときは、
かなり注意が必要。
自宅で、最後を看取りたいと考えているのなら、
かなり慎重に判断したい状況。
犬が歩けなくなるのは、
かなり病状が悪く、最後が近い合図。
調子が悪いなぁと感じたら、
無理をさせず、動物病院と相談。
治療をする手段があるのなら、入院を検討しても良いが、
治療することがなく、酸素ルームに入れて、
様子を見るしかないのなら、
自宅でゆっくりとさせてあげた方が良い。
Back
流動食を準備しておく

愛犬が、
年老いてきたら、
いつケガや病気をするのかわからないので、
元気でも「流動食」を用意した方が良い。
流動食は、
元気な時に、選んでおいた方が良い。
好き嫌いのある愛犬なら、特に食べるものを用意する必要がある。
できるだけ、
元気なうちに、好きな流動食を見つけてあげて置いて欲しい。
普段から食べている流動食を食べなくなっていたら、
かなり病状が悪化している事も推測できる。
Back
食事サポートツールを用意しておく

愛犬が年老いてくると、「薬」が、必然的に増える。
そして、犬は薬が苦手。。。。
ご飯も、年々食べなくなってくる。
自分だけで食べることもできなくなる。
薬を口入れたら、素直に薬を飲み込んでくれることは、あまりない。
素直な子なら、当たりくじみたいなもの。
口の奥まで、食べ物や薬を入れることができるツールや、
薬を包むコーティングツールなど、
愛犬にあった食事サポートツールを用意しておくと良い。
薬を包むコーティング剤には、
「サツマイモ」「チーズ」「ハチミツ」などが使える。
愛犬に使える食事サポートツールには、
・スポイトツール
・シリコン制ピンセット
・プラスチック製ピンセット
・ストロー
・針なしの注射器
・ペット用哺乳瓶
などが使える。
Back
リカバリーウェア(回復ウェア)を利用する
*Image is ALPHAICON公式WEB「リカバリーウェア」ページ
犬の回復ウェアも販売されているので、
病気の愛犬には、とても良いアイテムの1つ。
寝る時に、パジャマがわりに回復ウェアを着せると、
なんだか調子が良さそう。
元気な時も、
回復ウェアを着せると良い感じ。
健康で長生きになるのかも。
我が家では、
ペットグッズブランド「ALPHAICON」が販売している
「リカバリーウェア」を利用しています。
夜の睡眠時に着せているのですが、
なんとなく調子が良い感じがします。
なので、毎晩、パジャマのように着用しています。
*Image is ALPHAICON公式WEB「リカバリーウェア」ページ
ペットグッズブランド「ALPHAICON」が販売する「リカバリーウェア」
公式WEB「リカバリーウェア」URLリンクはこちら ↓
■ https://alphaicon.com/products/recovery-dogwear
Back
抱っこツールを準備しておく
愛犬が年老いていくと、
なにかと「抱っこ」をすることが多くなる。
愛犬の特徴によって、
愛犬を運ぶツールを使い分ける方が良い。
抱っこをして欲しそうな、
ぬくもりを感じていたそうなときは「スリング」がおすすめ。
家での抱っこにも大活躍。
寒い冬には、体温で温めることができるので、
ブランケットや、ダウンを使うと、
かなりぬくぬくで移動ができる。
スッポリと入って、
伏せの状態で移動できる「トートバッグ型キャリーバッグ」は、
外への散歩や、長い移動や、温かい季節にオススメ。
寒い冬には、寒さ対策が必要。
動かないので、体温が下がりやすい。
Back
歩行サポートツールを準備しておく
歩けなくなった愛犬の場合、
車いすのような歩行サポートツールを使用する方が良い。
自分の体重を軽くなるような車輪付きの補助ツールなどがあるので、
軽い体重なら動ける愛犬なら、かなり喜んでくれる。
Back
体力がなくなったら「ドッグカード」で移動する
体力がなくなったら「ドッグカード」で移動するのをメインにする。
無理に歩かせると、
身体が疲れてしまい、体力が減り、
病状が悪化することもある。
愛犬が年老いたり、病気になったら、
できるだけドッグカートを利用して、
遊びたい心を満足させて、体力を温存させた方が良い。
Back
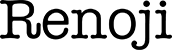
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/473a6fad.d685b00a.473a6faf.2cdb71a9/?me_id=1295999&item_id=10000824&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbijyutuhinn%2Fcabinet%2F11019377%2F20240729-02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/189ab8fb.3d911eb7.189ab8fc.aa443a94/?me_id=1313483&item_id=10003528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falice-zk%2Fcabinet%2Fmk%2Fny438s.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/473a6fad.d685b00a.473a6faf.2cdb71a9/?me_id=1295999&item_id=10000822&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbijyutuhinn%2Fcabinet%2F11019176%2F2024062802.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)









