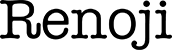Life
掃除 & 洗濯
掃除
洗剤
「汚れ」に適した「洗剤」を選ぶ方法汚れ
「油汚れ」を落とす方法「水あか」を落とす方法場所
「キッチン」を「綺麗」に維持する方法「部屋」を「綺麗」に維持する方法「浴室」を「綺麗」に維持する方法Goods
「食器」を「綺麗」に維持する方法「冷蔵庫」を「綺麗」に維持する方法「ドラム型洗濯機」を「綺麗」に維持する方法「窓」を「綺麗」に維持する方法「鏡」を「綺麗」に維持する方法「エアコン」を「綺麗」に維持する方法「壁」を「綺麗」に維持する方法「シール」を「綺麗」に剥がす方法洗濯
「服」を「綺麗」に維持する方法Material(素材)
「革(レザー)」素材を「綺麗」に維持する方法収納
「服」を「綺麗」に「収納」する方法
【掃除】「油汚れ」の落とし方
【掃除】
「油汚れ」の落とし方
「油汚れ」の落とし方
「油汚れ」は、
「キッチン」周辺がメインですが、 「手あか」「皮脂」も「油汚れ」と同じ「酸性」の汚れ。
意外と部屋中に「油汚れ(酸性の汚れ)」は点在しています。
「油汚れ」などの「酸性」の汚れには、 「アルカリ性」の洗剤が効果的です。
「アルカリ性」洗剤で、「酸性」の汚れを中和して、 汚れを落とします。
INDEX
油汚れの特徴
「油汚れ」は、「酸性」の性質を持った汚れで、
「油汚れ」「手あか」「皮脂」など、主に「ベトベト」しているのが特徴。
「油汚れ」のような「酸性」の性質を持った汚れは、
「アルカリ性」の性質を持つ洗剤で、「中和」させると、「油汚れ」が落ちる。
「酸性」と「アルカリ性」は、
「酸性」「アルカリ性」を計測する「pH値(ペーハー値)」だと、 「pH値」が「0」に近ければ近いほど「酸性」が強く、 「pH値」が「14」に近ければ近いほど「アルカリ性」が強い。
「pH値」が「7」に近いと「中性」と言われる。
「酸性(pH0~6)の汚れ」には、
・油汚れ
・皮脂汚れ
・手アカ
・血液
などがある。
「アルカリ性(pH8~14)の汚れ」には、
・水アカ(カルシウム)
・石鹸カス
・カルキ
・黒ずみ
・尿石
などがあります。
Back
「酸性」の「油汚れ」に効果的な洗剤
汚れを落とすときの基本は、「中和」させること。
「中和」させることで、頑固な汚れも落としやすくなる。
「油汚れ」「皮脂汚れ」「手アカ」「血液」などの汚れは、
「酸性」の汚れなので、
「アルカリ性」の洗剤で「中和」させることで、 「酸性」の汚れを効果的に落とすことができる。
強いアルカリ性の「pH値」で、
人体に影響がない「アルカリ電解水(pH 12)」が効果的。
「アルカリ電解水」が無い場合、
「重曹水」を加熱して「熱分解」すると、
「アルカリ電解水」に似た液体を作成することができる。
他にも、
「弱アルカリ性」の「重曹」「セスキ炭酸ソーダ」「石鹸」
「アルカリ性」の「オキシクリーン」「カビキラー」「キッチンハイター」
などが「酸性」の汚れに使用すると効果的な洗剤です。
Back
「pH値」リスト
「pH値」は、「7」に近いほど人体に優しく、 「7」から離れるほど、刺激が強く、危険になる。
「クエン酸(pH 2)」は、強力な「酸性」で、
「アルカリ電解水(pH 12)」は、強力な「アルカリ性」だが、 人体に大きな影響がないので、非常に便利な掃除アイテム。
| pH値 | 性質 | 商品名 |
|---|---|---|
| pH 1 | 酸性 | サンポール |
| pH 2 | 酸性 | クエン酸 |
| pH 3 | 酸性 | 酢 |
| pH 4 | 弱酸性 | 炭酸水 |
| pH 5 | 弱酸性 | アルコール(原液) |
| pH 6 | 弱酸性 | 中性洗剤(ph6~8) |
| pH 7 | 中性 | 真水(参考) |
| pH 8 | 弱アルカリ性 | 重曹 |
| pH 9 | 弱アルカリ性 | セスキ炭酸ソーダ |
| pH 10 | 弱アルカリ性 | 石鹸 |
| pH 11 | アルカリ性 | オキシクリーン |
| pH 12 | アルカリ性 | アルカリ電解水 |
| pH 13 | アルカリ性 | カビキラー・キッチンハイター |
Back
「重曹水」の「水」と「重曹」の比率は「100 : 5」ぐらい
「重曹水」を作る時に、
「水」と「重曹」の比率は、基本「100 : 5」ぐらい。
濃くしたい場合や、薄くしたい場合は、
それぞれ加減をして作成するだけ。
濃い「重曹水」を作成したい場合は、
「重曹」を多めにすれば良いのですが、
入れすぎると、「水」に溶けきらないので、
少しずつ混ぜて行きます。
1分以上混ぜても、溶けきらない場合は、
飽和量以上になっています。
水を加えて調節するなどをして、
残りの「重曹」を溶かしていきます。
Back
「重曹水」は「煮沸」すると「アルカリ度」が強くなる
「重曹溶液」は、
一度「沸騰」させると化学変化を起こし、「アルカリ度」が強くなる性質がなるそうです。
「アルカリ度」が強くなることで、
汚れを落とす能力や、消臭効果が高まることにもなります。
煮沸した「重曹水」は、
「重曹熱分解水」と呼ばれ、pH値が「10」ほどになり、
「アルカリ電解水(pH 12)」に近くなるそうです。
「重曹熱分解水」を作る手順
「アルミ鍋」を使用すると「変色」しますのでご注意ください。
・「水 1カップ」を鍋で沸かす
・沸騰後、「重曹 小さじ1」を投入する
・「弱火」で「5分」ほど煮る
・「重曹熱分解水」を冷ます
・「重曹熱分解水」の完成
・「水 1カップ」を鍋で沸かす
・沸騰後、「重曹 小さじ1」を投入する
・「弱火」で「5分」ほど煮る
・「重曹熱分解水」を冷ます
・「重曹熱分解水」の完成
Back
「アルカリ性」が「NG」の素材
「油汚れ」を綺麗にするのに便利な「アルカリ性洗剤」ですが、
適さない素材もあります。
「アルカリ性」が「NG」の素材は、
・アルミ
・大理石
・生木
・畳
・水を吸い込む素材
などがあります。
「アルミ」「大理石」は、「アルカリ性」に反応するので、
素材が傷む可能性がある。
Back
「ビール」は「油汚れ」を分解する
「ビール」の「糖分」は、
「油汚れ」を分解してくれる。
「布」などに、「ビール」を染み込ませて、
こするだけで、軽い「油汚れ」は、簡単に落とせてしまう。
「頑固な油汚れ」には、「布」「ティッシュ」に、
「ビール」を染み込ませて、しばらく付け置く。
その後、布などでこすると、「油汚れ」がほとんど取れる。
それでも落ちない場合は、
繰り返し同じ掃除方法を繰り返す。
「ビール」の「独特なにおい」は、「10分ほど」で消える。
Back
「ひどい油汚れ」には「小麦粉」をかけると吸収してくれる
「油」がこびりついているような
「ひどい油汚れ」には、「小麦粉」をかけると、
「小麦粉」が「油」を吸収してくれて、掃除がしやすくなる。
「研磨剤」的な役割をしてくれるので、
そのまま「こすり洗い」すると、
細かい汚れが綺麗になりやすい。
注意点もあり、
傷つきやすい素材で使用すると、
「小麦粉」によって、細かい傷がつく可能性がある。
使用前に、確認する必要がある。
「小麦粉」で作られた「うどん」「パスタ」の「茹で汁」を使用して、
「油汚れ」を掃除すると、綺麗にすることができる。
「小麦粉」には、
「油」を包み込む特性がある。
Back
「油汚れ」を落としやすい「生地」
「油汚れ」を落としやすい「生地」には、
・デニム
・フリース
などがある。
「油汚れ」を落としやすい「生地」一覧
| 生地 | 説明 |
|---|---|
| デニム |
「デニム」は、 程よい「固さ」「ざらつき」があるため、 「油汚れ」を巻き込み、落としやすい。 「クレンザー」をつけることで、 簡単に「レンジ周り」の「油汚れ」を落とせる。 |
| フリース |
「フリース」は、 「石油」を原料とした「合成繊維」なので、 「油汚れ」と親和性があり、乾拭きだけで、汚れを落としやすい。 |
Back