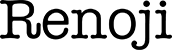Life
Plant & Farming
基礎知識
「植木鉢」での「育て方」【植物】「若返り効果」のある「植物」ハーブ栽培
【Herbs】「バジル」を栽培する方法【Herbs】「パクチー(コリアンダー)」を栽培する方法観葉植物
【観葉植物】「空気清浄能力」のある「植物」【観葉植物】「コーヒーの木」を育てる方法【観葉植物】「カジュマル」を育てる方法【観葉植物】「アロエ(Aloe)」の育て方【観葉植物】「サンスベリア(Sansevieria)」の育て方【観葉植物】「エアープランツ」の育て方【観葉植物】「モリンガ・オレイフェラ」の育て方農業
「野菜」の「育て方」「ニンニク」の「育て方」多年にわたって収穫ができる「多年生」の「野菜」「果物」「ピーマン」の育て方Gardening
「雑草対策」を効果的にする方法
【観葉植物】「ガジュマル」の豆知識
【観葉植物】
「ガジュマル」の豆知識
「ガジュマル」の豆知識
INDEX
はじめに
「ガジュマル」は、
「多幸の木」「幸せを呼ぶ木」などと呼ばれる「木」で、
「縁起の良い観葉植物」として人気。
単なる観葉植物としてだけでなく、
「キムジナーの伝説」「生命力」「シルエット」「花言葉」などから、
人々に幸運や癒しをもたらす「幸せを呼ぶ木」
として広く親しまれるようになった経緯がある。
Back
「幸せを呼ぶ木」と呼ばれる「ガジュマル」
「ガジュマル」は、
「多幸の木」「幸せを呼ぶ木」などと呼ばれる「木」で、
縁起の良い観葉植物として人気。
「ガジュマル」が、
「幸せを呼ぶ木」と呼ばれるようになったのは、
主に「沖縄の伝説」と、その「生命力の強さ」が影響している。
「沖縄」には、
「精霊 キジムナーの伝説」がある。
「沖縄」には、 古くから伝わる「キムジナー」という「精霊」がいる。
「キジムナー」は、
「赤い髪」の「小さな子ども」の姿をした「精霊」で、
「いたずら好き」だが、「人と友好的な存在」として知られている。
精霊「キムジナー」は、
特に「ガジュマル」の「古い木」に宿ると信じられており、
「キムジナー」は、
「ガジュマルを大切にする人のことを、
近くで見守り、「幸運」「反映」をもたらすと伝えられている。
この「キムジナー」の習性によって、
「ガジュマル」は、
「多幸の木」と呼ばれるようになり、
沖縄の人にとって、
とても神聖な存在として大切にされるようになった。
「ガジュマル」が、
「多幸の木」「幸せを呼ぶ木」と呼ばれるようになったのは、
この「沖縄」の「信仰」「風習」が、
全国へと広がり、
「幸せを呼ぶ木」として親しまれるようになったとされている。
「ガジュマル」の「強靭な生命力」もあり、
「健康」「力強さ」を象徴し、
見る人を「ポジティブ」な印象を与えるとされている。
「強靭な生命力」という特徴も、
「幸せを呼ぶ木」というイメージを強化している。
「ガジュマル」は、
ユニークな形でも人気で、
「ガジュマル」の「幹」が、
ぷっくりと膨らんで、複雑に絡み合った姿が、
可愛らしく人気の要因の1つとなっている。
「ガジュマルの幹」は、
幹や枝から空中に向かって伸び根「気根」が、
地面へと到達すると太くなり、
「ガジュマル」の「主幹」を支え、
独特な形状を形成する。
その「気根」が、
ぷっくりと膨らんだ、複雑に絡み合った根の姿になる。
ぷっくりと複雑に絡み合った「幹と気根」の姿は、
「タコの木」とも呼ばれ、
「多幸(たこう)」という言葉が連想され、
「縁起の良い木」と言われるようになった。
「ガジュマルの花」には、
「健康」「たくさんの幸せ」という花言葉がある。
「ガジュマル」は、
「キジムナーの伝説」「強い生命力」「力強い絡み合った幹」「花言葉」などから、
「多幸の木」「幸せを呼ぶ木」と呼ばれるようになった。
Back
「ガジュマル」の別名「絞め殺しの木」の「由来」
「ガジュマル」は、
「幸せをもたらす木」といわれる一方で、
「絞め殺しの木」という呼ばれ方もする。
これは、
「ガジュマル」が、他の植物や岩などに巻きつきながら生長し、
巻き付かれた植物がやがて枯れはてることに由来する。
ジブリ映画「天空の城ラピュタ」のモデルとなった
カンボジアの遺跡「アンコールワット」では、
遺跡を覆いつくす「ガジュマル」が圧倒的な存在感を示していて、
「絞め殺しの木」と呼ばれることに、
自然と納得してしまう。
Back
「火の精霊 キジムナー」が宿る木「ガジュマル」とは
沖縄では、
火の精霊「キジムナー」が宿る「木」として、
大切にされています。
大きく育った「ガジュマル」の
「気根」の間を通った「2人」は幸せになれる。
という言い伝えもある。
火の精霊「キジムナー」は、
「赤い髪」をした少年の精霊で、
幸せを呼び込む精霊途して知られている。
「多幸の木」と呼ばれるのは、
「根」の伸び方が、
「タコ」の足に似ていることが由来らしい。
Back
「国内最大」の「ガジュマル」
国内最大の「ガジュマル」は、
「樹齢100年」を超えていると言われています。
国内で最も大きな「ガジュマル」は、
鹿児島県・沖永良部島にある「国頭小学校」の校庭に植えられている「ガジュマル」。
「樹齢100年」を超えると言われています。
「新日本名木百選」のひとつでもある。
「和泊町」の「指定天然記念物」にも指定されている。
「沖縄県島尻郡八重瀬町」にある
「世名城」の「ガジュマル」も、
日本最大級の「ガジュマル」として有名。
「樹齢約250年」もあり、「樹高約10m」「幹周り約24m」もある。
Back
「ガジュマル」の「花言葉」と「風水」
「ガジュマル」には、
「健康」という花言葉が付けられている。
「生命力」の象徴のようなガジュマルらしい花言葉。
また、
「風水」では、
「玄関」や「ベランダ」など「入り口」に置くことで、「運気アップ」が期待できるとされている。
「癒しの作用」もあることから、
「寝室」などに置くのもよいとされる。
Back
「ガジュマル」の「花」は咲くの?
「ガジュマル」の「花」は、
春頃には花を咲かせ、
薄黄色でつぼ状の直径1cmほどの花が集って咲く。
「常緑高木」として、
いつも「緑の葉っぱ」をつけているイメージの強い「ガジュマル」だが、
春頃に、「花」を咲かせ、「薄黄色」で、「つぼ状の直径1cmほどの花」が集って咲く。
ただし、
花自体は果実の中に隠れているので、外から見ることはできない。
「ガジュマル」の「花言葉」の意味や由来
「ガジュマル」は、茎や枝から根が飛び出す気根が特徴。
この気根は、アスファルトやコンクリートを突き破るほどのパワーがある。
その気根から生命力を感じることから「健康」という花言葉がつけられたとされている。
「ガジュマル」の「風水効果」
「ガジュマル」は、丸くかわいい葉っぱが下向き生えるため、
「風水」では気分を落ち着かせたり、リラックスさせたりといった風水効果が期待される。
日頃から癒やしを求めている人に良い観葉植物。
また、
大きなものから小さなものまでサイズのバリエーションが豊富なので、
置き場所に合ったものを選べることもうれしいポイント。
「ガジュマル」の「風水」を意識した「飾り方」や「置き場所」
寝室に飾る
「ガジュマル」を「寝室」に置くことで、「ガジュマル」のリラックス効果を利用して、
快適な睡眠空間を作ることができる。
風水的には、
お部屋のインテリアのテイストと合った植木鉢を選ぶことがおしゃれに見せるコツ。
陽の気を発する観葉植物をいくつか一緒に並べるとさらに気持ちが落ち着くそう。
キッチンに飾る
「ガジュマル」は、「キッチン」に置くことで、気の流れがよくなる。
風水では、
キッチンは火と水があるので気が乱れやすい場所とされている。
「ガジュマル」を1鉢置くと、気の乱れが調和されて、落ち着ける空間になる。
玄関に飾る
「北〜北東北」の方向に玄関がある場合は、「ガジュマル」を飾ると良い。
お家へ帰ってきたときにリラックスできる上、「悪い気」を中和する効果が期待できる。
Back
「ガジュマル」とは
ガジュマルの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学名 | Ficus microcarpa |
| 英名 |
Chinese Banyan Malayan Banyan |
| 科・属名 | クワ科イチジク属(フィカス属) |
| 園芸分類 | 観葉植物 |
| 樹高 | 鉢植えの場合では「2m」程度 |
| 耐寒性と耐暑性 | 寒さに弱く、暑さに強い |
| 原産 | 「東南アジア」「台湾」「インド」「オーストラリア」「日本」など |
| 開花期 |
個体によって「花期」は異なる |
| 別名 |
・ベンガルボダイジュ ・多幸の木 ・絞め殺しの木 |
「ガジュマル」は、
「沖縄」から「屋久島」にかけて自生していて、
幅広い地域に生息する「常緑高木」。
独特な形をしており、
日常の手入れが簡単で育てやすい。
初心者の方でも育てやすい「観葉植物」。
「乾燥」や「寒さ」に強く、
繁殖能力も高く、
「ガジュマルの実」を食べた「鳥」「コウモリ」たちが、
種の混ざった「糞」をすることで、
土台となる「植物」などに寄生しながら発芽し、
自生地域を広げる強い生命力を持っている。
日本には、明治時代に入ってから輸入され、
防風林として植栽された。
「気根」「葉」「樹皮」には、「薬効」がある。
「のどの痛み」「のどの腫れ」「神経痛」「関節痛」に効果があるそう。
「ガジュマル」が生育するエリアは、
「熱帯」から「亜熱帯」に分布する。
「常緑高木」で、
太くて、しっかりとした安定感のある「幹」、
厚みがあり、丸みのある恋緑色の「葉」、
などが特徴的。
「生命力」を感じるフォルムをしている。
Back
「ガジュマル」の「種類」
「ガジュマル」は、
世界に「約800種」、
日本には、「約20種の原種や園芸品種」
がある。
日本では、
丸く太った気根の人参ガジュマルと呼ばれる園芸品種が、
観葉植物や盆栽として人気。
ガジュマルの株の選び方
生命力の象徴であることからも分かるように、 葉と幹にツヤがあって健康的な株、そして幹の形がよい株を選ぼう。 「ハダニ」や「アブラムシ」といった「害虫」が付着していないかを、きちんと確認するのが、よいガジュマルの株選びのポイント。
ガジュマルの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
|
一般的によく知られている「ガジュマル」。 「幹」が「ニンジン」のように、「ぷっくら」と「肉厚」なところが、名前の由来。 一般的に園芸で知られている「ガジュマル」といえば、 この「ニンジンガジュマル」を示す。 「ニンジン」のような太く丸いユニークな根っこが特徴的。 育成の途中で少し根を引き抜いて太らせて育てられます。 小さいサイズが多く、テーブルの上に置きたい方などにおすすめ。 | |
|
「センカクガジュマル」は、 「尖閣諸島」に自生している希少性の高い品種。 垂直方向に枝を伸ばすのが特徴で、葉はひし形で光沢があり、肉厚なのが特徴。 日本で流通している多くは、接ぎ木によって育てられたもの。 | |
|
「センカクガジュマル」の突然変異によって誕生した「ガジュマル」。観葉植物の中でも高価で。 「パンダガジュマルは、センカクガジュマルの突然変異(変種)で生まれた品種。 センカクガジュマルよりも葉っぱが丸みを帯びているのが特徴で、数が少なく高価な品種の1つ。 | |
|
「シダレガジュマル」は、 別名「白ガジュマル」、英名を「ベンジャミンツリー」と呼ばれる品種。 「枝垂れ榕樹」「ベンジャミン」「ベンジャミンゴムノキ」とも呼ばれる。 白っぽい樹皮と三つ編みに仕立てられる木の柔らかさを持ち合わせる。 ただし、 三つ編みにできるのは、 若い苗木の間だけなので、最初の仕立てることが重要。 | |
|
「黄金ガジュマル」は、「台湾」で育った園芸品種。 |
Back
「ガジュマル」の「育て方」
「ガジュマル」は、
比較的育てやすい植物。
ユニークな形をした「ガジュマル」は、
見ているだけで元気をもらえるし、癒しにもなる。
観葉植物を育てるのが初めてという方にもおすすめ。
「ガジュマル」の「育て方」は、
日光を好むので、
日当たりの良い場所で置くと良い。
水は、
土の表面が乾いたら、たっぷりと与える。
耐寒温度は、
「5℃~6℃」ぐらいなので、
「秋~冬」にかけては、明るい室内に入れてあげる。
「ガジュマル」は、日光を好む観葉植物であるため、
日の当たる場所に置くのが好ましい。
ただし葉焼けしないよう、
日差しが強い季節は遮光することを忘れてはいけない。
定期的に剪定も行って、
美しく健康的に育ててほしい。
慣れてきたら希少種を育ててみるのもおすすめ。
「ガジュマル」の「年間栽培スケジュール」
| 栽培段階 | 説明 |
|---|---|
| 植え付け・植え替え | 4月後半〜7月 |
| 水やり | 11〜3月は控えめ、4〜10月は表面が乾いてきたら |
| 肥料 | 5〜10月 |
| 剪定 | 4〜7月 |
| 挿し木 | 4月後半〜8月 |
日当たり(置き場所)
「ガジュマル」は、
春から秋にかけてであれば屋外で育てることが可能。
ただし、夏の強い直射日光が常に当たる状態にあると葉焼けを起こすおそれがある。
環境によるが、
遮光ネットや寒冷紗(かんれいしゃ)を使うなどして、
3割から5割程度遮光してやるとよい。
同じく、
気温が高すぎる環境でも葉焼けを起こすことがある。
とくに猛暑や酷暑が続く時期は日陰に移すなどの工夫が必要。
なお遮光ネットや寒冷紗はホームセンターや園芸店はもちろん、
最近は100均でも手に入る。「ガジュマル」を購入すると同時に用意しておく。
一方、
「ガジュマル」には、
耐陰性があることから日光が差し込む屋内でも育てることができる。
とはいえ太陽の光を好むのが「ガジュマル」だ。
健康に育てるためにも日光が当たる場所に置くことを意識する。
なお室内であっても、
直射日光に当たると葉焼けするおそれがある。
レースのカーテンを一枚隔てるなど工夫しよう。
もうひとつ、
室内で育てる場合に気をつけたいのがエアコンや扇風機などの風である。
直接当たると葉が傷むおそれがあるため注意してほしい。
春から秋にかけてであれば屋外で育てることが可能。
ただし、夏の強い直射日光が常に当たる状態にあると葉焼けを起こすおそれがある。
環境によるが、
遮光ネットや寒冷紗(かんれいしゃ)を使うなどして、
3割から5割程度遮光してやるとよい。
同じく、
気温が高すぎる環境でも葉焼けを起こすことがある。
とくに猛暑や酷暑が続く時期は日陰に移すなどの工夫が必要。
なお遮光ネットや寒冷紗はホームセンターや園芸店はもちろん、
最近は100均でも手に入る。「ガジュマル」を購入すると同時に用意しておく。
一方、
「ガジュマル」には、
耐陰性があることから日光が差し込む屋内でも育てることができる。
とはいえ太陽の光を好むのが「ガジュマル」だ。
健康に育てるためにも日光が当たる場所に置くことを意識する。
なお室内であっても、
直射日光に当たると葉焼けするおそれがある。
レースのカーテンを一枚隔てるなど工夫しよう。
もうひとつ、
室内で育てる場合に気をつけたいのがエアコンや扇風機などの風である。
直接当たると葉が傷むおそれがあるため注意してほしい。
管理温度
暑さには強いが寒さには弱いのが「ガジュマル」。
具体的な管理温度の基準があるわけではない。
一般的には5度を下回ると葉が落ちてしまうことがある。
寒さで生長が緩やかになってしまうこともあるため、
屋外で育てる際は気温が低くなるタイミングで室内に移すようにする。
しっかり根が張り健康に育っている「ガジュマル」であれば、
暖かい地域(関東以南など)で屋外越冬できる場合もある。
具体的な管理温度の基準があるわけではない。
一般的には5度を下回ると葉が落ちてしまうことがある。
寒さで生長が緩やかになってしまうこともあるため、
屋外で育てる際は気温が低くなるタイミングで室内に移すようにする。
しっかり根が張り健康に育っている「ガジュマル」であれば、
暖かい地域(関東以南など)で屋外越冬できる場合もある。
用土
熱帯から亜熱帯という高温多湿の気候で育つ「ガジュマル」だが、
水はけが悪い土で育ててしまうと根腐れを起こすおそれがある。
市販の観葉植物用の土で水はけがよいものを選ぶ方が良い。
自分で用土をブレンドしたい場合は、
観葉植物用の土と赤玉土、鹿沼土などを合わせるのがおすすめ。
水はけが悪い土で育ててしまうと根腐れを起こすおそれがある。
市販の観葉植物用の土で水はけがよいものを選ぶ方が良い。
自分で用土をブレンドしたい場合は、
観葉植物用の土と赤玉土、鹿沼土などを合わせるのがおすすめ。
水やり
「ガジュマル」の育て方で重要になるのが、
季節に応じて水やりのタイミングを変えることだ。
夏場など暑い時期は、
土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えて切らさないように。
一方で、
冬場など寒い時期は、
土の表面が乾いてから数日(2〜3日)待って水やりをするのが基本となる。
数日待つ間に「ガジュマル」が乾燥し、樹液の濃度が高まる。
これにより耐寒性がアップする。
ただし、
葉がしおれるといった場合は、水やりの回数を増やすなど工夫してほしい。
季節に応じて水やりのタイミングを変えることだ。
夏場など暑い時期は、
土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えて切らさないように。
一方で、
冬場など寒い時期は、
土の表面が乾いてから数日(2〜3日)待って水やりをするのが基本となる。
数日待つ間に「ガジュマル」が乾燥し、樹液の濃度が高まる。
これにより耐寒性がアップする。
ただし、
葉がしおれるといった場合は、水やりの回数を増やすなど工夫してほしい。
肥料・追肥
「ガジュマル」は肥料を与えなくても育つ植物だが、そうはいっても与えたほうが生長は早い。
春から秋にかけての生長期に、緩効性の化成肥料を置き肥するか10日に1回ほどのスパンで液肥を与えるとよい。
コバエなどの発生を防ぐため、有機肥料よりも化成肥料を選ぶのがおすすめだ。
また「ガジュマル」は冬場に生長が緩やかになる。
このタイミングで肥料を与えると葉が肥料焼けを起こすおそれがあるため気をつけよう。
春から秋にかけての生長期に、緩効性の化成肥料を置き肥するか10日に1回ほどのスパンで液肥を与えるとよい。
コバエなどの発生を防ぐため、有機肥料よりも化成肥料を選ぶのがおすすめだ。
また「ガジュマル」は冬場に生長が緩やかになる。
このタイミングで肥料を与えると葉が肥料焼けを起こすおそれがあるため気をつけよう。
植え替え
「ガジュマル」の植え替えは、
2年以上植え替えていない、
あるいは、
鉢底から根が出てしまっているなどの「根詰まり」を起こしそう
などのタイミングで植え替えをする。
時期としては5〜6月、
遅くとも7月が目安に行う。
このときの用土も、
市販の観葉植物用の土などでOK。
2年以上植え替えていない、
あるいは、
鉢底から根が出てしまっているなどの「根詰まり」を起こしそう
などのタイミングで植え替えをする。
時期としては5〜6月、
遅くとも7月が目安に行う。
このときの用土も、
市販の観葉植物用の土などでOK。
剪定
「ガジュマル」は、よく育つため「剪定」が必要になる。
伸びすぎた枝を切ることで樹形が整うだけでなく、
全体の成長を促進させることにもつながることから大切な作業のひとつ。
・剪定バサミ
・ノコギリ
・癒合剤
「ガジュマル」を剪定すると、切り口から樹液が出てくる。
皮膚に触れるとかぶれることがあるため、手袋は必須。
また切り口から雑菌が入ってしまうこともあるので、
剪定したところには「癒合剤」を塗布するとよい。
・枯れた枝を根元から切る
・外側に勢いよく伸びた枝、内側に向かった枝を全体のバランスを見ながら切る
・重なっている枝のどちらかを切る
・鉢の生え際から生えている枝を切る
・切った箇所に癒合剤を塗布する
剪定を怠ると日光が届かなかったり、
水や養分が全体に行き渡らなくなったりするおそれがあるので気をつける。
植え替え時期と同じ5〜7月に実施するのがおすすめ。
それ以外でも、
夏の生長期に合わせて4〜6月の間には剪定をしておく。
伸びすぎた枝を切ることで樹形が整うだけでなく、
全体の成長を促進させることにもつながることから大切な作業のひとつ。
「ガジュマル」の剪定に必要な道具
・手袋(園芸用)・剪定バサミ
・ノコギリ
・癒合剤
「ガジュマル」を剪定すると、切り口から樹液が出てくる。
皮膚に触れるとかぶれることがあるため、手袋は必須。
また切り口から雑菌が入ってしまうこともあるので、
剪定したところには「癒合剤」を塗布するとよい。
剪定の手順
・まっすぐ上に伸びる枝の先端を切る(高くなりすぎるのを防ぐため)・枯れた枝を根元から切る
・外側に勢いよく伸びた枝、内側に向かった枝を全体のバランスを見ながら切る
・重なっている枝のどちらかを切る
・鉢の生え際から生えている枝を切る
・切った箇所に癒合剤を塗布する
剪定を怠ると日光が届かなかったり、
水や養分が全体に行き渡らなくなったりするおそれがあるので気をつける。
植え替え時期と同じ5〜7月に実施するのがおすすめ。
それ以外でも、
夏の生長期に合わせて4〜6月の間には剪定をしておく。
挿し木
「ガジュマル」は、
剪定した枝を利用して増やすことができる。
切り口から、樹液が出てくるので、触れないように注意しつつ洗い流そう。
次に、上のほうの葉を2〜3枚残して下の葉を落とし、枝を斜めにカットする。
あとは、あらかじめ用意しておいた鉢と用土にその枝を半分程度挿してたっぷりと水を与えれば完成。
1〜2週間は直射日光が当たらない風通しのよい場所に置いて管理し、
3週間程度経ったら少量の液肥を与える。
剪定した枝を利用して増やすことができる。
挿し木による増やし方
剪定した枝の中から元気そうなものを選び、適当な長さ(2〜3節が目安)にカットする。切り口から、樹液が出てくるので、触れないように注意しつつ洗い流そう。
次に、上のほうの葉を2〜3枚残して下の葉を落とし、枝を斜めにカットする。
あとは、あらかじめ用意しておいた鉢と用土にその枝を半分程度挿してたっぷりと水を与えれば完成。
1〜2週間は直射日光が当たらない風通しのよい場所に置いて管理し、
3週間程度経ったら少量の液肥を与える。
害虫
「ガジュマル」は、
病気にかかりにくい植物とされてはいるものの、アブラムシやカイガラムシ、ハダニといった害虫には気をつける。
吸汁されると病気にかかったり枯れたりしてしまうおそれがある。
発見し次第、ピンセットなどで取り除くようにしよう。体長3mm程度の小さなカイガラムシも同様。
吸汁されることで株が弱り、枯れてしまう場合がある。
白い綿毛のようなものがある小さな虫を見つけたら、
即座にピンセットなどで取り除こう。
とくに根の間に入り込みやすいため、見逃さないように注意。
0.5mm程度とさらに小さいのがハダニである。
葉の裏側を吸汁されると葉に白っぽい斑点のようなものができる。
手遅れになると枯れてしまうことがあるため、
定期的に葉の表面や裏側に葉水をしたり、
見つけ次第、殺ダニ剤などを使って駆除する。
病気にかかりにくい植物とされてはいるものの、アブラムシやカイガラムシ、ハダニといった害虫には気をつける。
「ガジュマル」の害虫対策
すす病などを媒介するアブラムシは、吸汁されると病気にかかったり枯れたりしてしまうおそれがある。
発見し次第、ピンセットなどで取り除くようにしよう。体長3mm程度の小さなカイガラムシも同様。
吸汁されることで株が弱り、枯れてしまう場合がある。
白い綿毛のようなものがある小さな虫を見つけたら、
即座にピンセットなどで取り除こう。
とくに根の間に入り込みやすいため、見逃さないように注意。
0.5mm程度とさらに小さいのがハダニである。
葉の裏側を吸汁されると葉に白っぽい斑点のようなものができる。
手遅れになると枯れてしまうことがあるため、
定期的に葉の表面や裏側に葉水をしたり、
見つけ次第、殺ダニ剤などを使って駆除する。
Back
「ガジュマル」の「根っこ」を丸くする方法
「ガジュマル」の木の根本は、
丸くぷっくりとしている印象がある。
あのぷっくり感は、普通に育てていても出てこない。
「ガジュマル」の木の根元の「ぷっくり感」は、
育て方で作り出すものになっている。
「ガジュマル」の「木の根っこ」を丸く見せるには、いくつかの方法がある。
主な方法は以下のいくつかの方法がある。
・「鉢」の「選び方」と「植え付け方」
・剪定による「根の露出」
・「根」の誘引(盆栽的な手法)
・品種選び
鉢の選び方と植え付け方
最も手軽で、初心者にもできる方法。
メリット:
・手軽にできる。
・植物への負担が少ない。
・見た目の変化を比較的早く楽しめる。
デメリット:
・根そのものの形を変化させるわけではない。
・株が小さいと効果が出にくい。
メリット:
・手軽にできる。
・植物への負担が少ない。
・見た目の変化を比較的早く楽しめる。
デメリット:
・根そのものの形を変化させるわけではない。
・株が小さいと効果が出にくい。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 浅くて広口の鉢を選ぶ |
「深さのある鉢」では、 「根」が下に伸びてしまい、丸い形が出にくい。 浅く、そして口の広い鉢に植えることポイント。 「根」が鉢の中に広がりやすくなり、結果的に丸く見える効果がある。 |
| 根を少し持ち上げて植える |
緩やかな傾斜をつけて土を盛り、
根の大部分を土から少しだけ露出させるように植え付ける。 根元が土に埋もれてしまわないように注意する。 |
| 化粧鉢や受皿との組み合わせ |
「鉢」の形や色、そして下に敷く受皿も全体の印象を大きく左右する。 丸みのあるデザインの鉢を選ぶと、視覚的に根の丸さを強調できる。 |
剪定による根の露出(または根上がり仕立て)
「ガジュマル」は、
生命力が強いので、根上がり(根を土から露出させる仕立て方)にすることも可能。
メリット:
・ガジュマルらしい力強い根の表現ができる。
・株の成長とともに、より迫力のある姿になる。
デメリット:
・植物に負担がかかる可能性がある。
・時間がかかる。
・乾燥に注意が必要。
生命力が強いので、根上がり(根を土から露出させる仕立て方)にすることも可能。
メリット:
・ガジュマルらしい力強い根の表現ができる。
・株の成長とともに、より迫力のある姿になる。
デメリット:
・植物に負担がかかる可能性がある。
・時間がかかる。
・乾燥に注意が必要。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 少しずつ土を減らす |
「根元」の 土が被っている部分を、少しずつ(数ヶ月〜半年単位で)減らしていく。 一気に土を減らすと、 根が乾燥して傷んでしまう可能性があるので注意が必要。 |
| 古い土を取り除く |
植え替えの際に、根の周りの古い土を丁寧に落とし、 太い根や形の良い根を選んで露出させる。 |
| 不要な細根の整理 |
露出させる根以外の細くて不規則な根は、 適宜剪定して整理することで、露出させる根の形を際立たせる。 |
根の誘引(盆栽的な手法)
これはより専門的な、盆栽に近い手法になります。根を人為的に誘導して形を作る方法。
メリット:
* より意図的に根の形をコントロールできる。
* 芸術性の高い仕立てができる。
デメリット:
* 非常に時間と手間がかかる。
* 専門的な知識や技術が必要。
* 植物に大きなストレスがかかる可能性もある。
メリット:
* より意図的に根の形をコントロールできる。
* 芸術性の高い仕立てができる。
デメリット:
* 非常に時間と手間がかかる。
* 専門的な知識や技術が必要。
* 植物に大きなストレスがかかる可能性もある。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 幼い苗から始める | 根がまだ柔らかいうちに始めるのが効果的。 |
| ワイヤーや針金で固定する |
根の成長方向を誘導するために、 ワイヤーや針金を軽く巻きつけたり、 土の中に埋め込んだ石などに固定したりして、 根が丸くなるように促す。 |
| 定期的な手入れ |
根の成長に合わせてワイヤーを外し、 新しいワイヤーで固定し直すなど、継続的な手入れが必要。 |
品種選び
これは「今からガジュマルを購入する場合」に有効な方法。
根上がりしやすい品種を探す。
「ガジュマル」の中にも、
特に根が発達しやすく、自然とユニークな形になりやすい個体や品種がある。
購入時に、既に根元が特徴的な形になっているものを選ぶのも一つの手。
メリット:
・最初から好みの形に近いものを選べる。
・手間がかからない。
デメリット:
・既に持っているガジュマルには適用できない。
根上がりしやすい品種を探す。
「ガジュマル」の中にも、
特に根が発達しやすく、自然とユニークな形になりやすい個体や品種がある。
購入時に、既に根元が特徴的な形になっているものを選ぶのも一つの手。
メリット:
・最初から好みの形に近いものを選べる。
・手間がかからない。
デメリット:
・既に持っているガジュマルには適用できない。
注意点
| 水やりと湿度 |
根を露出させる場合、乾燥しやすくなるため、特に水やりには注意が必要。 霧吹きで葉水を与えるなど、湿度管理も重要。 |
| 日当たり |
ガジュマルは日光を好みますが、急な強い直射日光は避ける。 |
| 肥料 |
根を育成する時期には、 バランスの取れた液体肥料などを適量与えると良い。 |
| 無理は禁物 |
「ガジュマル」は、丈夫な植物だが、 急激な環境変化や無理な処置はストレスになり、枯れてしまう原因にもなる。 焦らず、 植物の様子を見ながら少しずつ行う。 |
Back