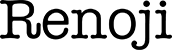Life
DIY Memo
Topics
「養生(保護)」を上手にする方法「木材」の「加工」を上手にする方法「熱加工」を上手にする方法「研磨」を「綺麗」に仕上げる方法「塗装」を「綺麗」に仕上げる方法「接着剤」を使いこなす方法「潤滑剤」を上手に使いこなす方法家具・インテリア
「インテリア」を「綺麗」に仕上げる方法「鏡」を「綺麗」に取り付ける方法運気の良い「玄関」にする方法部品
「DIY」に使える「部品」を使いこなす方法「DIY」に使う「ネジ」を使いこなす方法「DIY」に使う「ナット」を使いこなす方法素材
「材料」を「上手」に「収納」する方法「ゴム」を上手に使いこなす方法「樹脂」を上手に使いこなす方法「プラスチック」を上手に使いこなす方法「青銅」を上手に使いこなす方法「ガラス」を上手に使いこなす方法電動ツール
「ルーター」を使いこなす方法「電動ドライバー」を使いこなす方法「集塵機」を使いこなす方法「サンダー(研磨機)」を使いこなす方法「発泡スチロールカッター」を使いこなす方法
【塗料】「塗装」を「綺麗」に仕上げる方法

INDEX
はじめに
「塗装」は、
「下準備」と「塗装環境」が、とても重要になってくる。
同じ「塗料」を使っても、
「下準備」「塗装環境」によって、
「変色」したり、剥げ落ちたりと、
数年も持たなかったりと、
問題が多くなることもある。
「塗装」の「基本」を知っていると、
長く綺麗な「塗装」に近づくことができる。
Back
「塗装」の流れ
「塗装」には、
色々と下準備が必要で、
手を抜くと、しばらくして
「塗装」が剥げたり、変色したりと、
良いことがない。
しっかりと「塗装の流れ」を把握して、
長持ちする「塗装」ができるようにしたい。
「塗装」をする時の「流れ」
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| Step 1 |
塗装面の「汚れ」「油分」「ごみ」などを取り除く。 「シリコンオフスプレー」を使用すると「油脂成分」を除去できる。 |
| Step 2 |
「塗料」の準備をする。 開封前に、しっかりと容器を振り、 塗料をしっかりと混ぜ合わせる。 紙コップなどの容器に入れ、 刷毛を用意する。 「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」は、 原料のまま使用します。 |
| Step 3 |
最初の「1塗り目」は、 マダラでも良いので、 塗装面全体を塗り上げます。 |
| Step 4 |
「10分~20分」ほど「乾燥」させる。 時間は、塗料によるので「説明書」をご確認ください。 |
| Step 5 |
「2塗り目」は、 まだらで、塗れていない部分の 塗り残しがないように全体を塗り上げます。 すでに塗料で塗られている部分は、 「塗料」が塗りやすくなっているので、 「1塗り目」より、かなり塗りやすくなっているはずです。 |
| Step 6 |
「10分~20分」ほど「乾燥」させる。 時間は、塗料によるので「説明書」をご確認ください。 |
| Step 7 |
「3塗り目」では、 刷毛の跡で、綺麗な模様になるように、 綺麗に全体を塗り上げます。 |
| Step 8 |
触っても大丈夫なように、 「10分~20分」ほど「乾燥」させる。 本乾燥には、「1日~2日」ほど必要。 時間は、塗料によるので「説明書」をご確認ください。 |
最低でも「3回以上」で塗り上げるようにすると、
綺麗に仕上げることができます。
塗装のコツは、
少しずつ丁寧に塗ることです。
綺麗に仕上げるには、
必須のコツコツ作業です。
Back
塗装に必要な道具
塗装に必要な道具は、
・塗料(「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」)
・刷毛・筆・ローラー(塗装面の大きさによって選択する)
・塗料入れ(紙コップなど)
・マスキングテープ
・保護シート(新聞紙・模造紙・ブルーシートなど)
などが必要です。
「紙コップ」がない場合は、
「ペットボトル」をカッターでカットして、
「下部分」を紙コップ代わりにするのも便利です。
Back
「塗装」しにくい材質には「マルチプライマー」

「塗料」が塗りづらい材質
・金属
・モルタル
・ガラス
・陶器
・プラスチック
・アルミ
・ブリキ
などには、
「マルチプライマー」を最初に塗り、
「下塗り」を施工しておくことで、
「ミルクペイント」の塗装が簡単になります。
「マルチプライマー」を塗布することで、
塗料の「密着性」が高まります。
Back
綺麗にスプレー塗装をするコツ
「スプレー塗装」を綺麗にするにはコツがある。
綺麗に「スプレー塗装」するには、
・5回以上に分けて、塗装を完成する
・一度で塗りすぎない、霧状で少しずつ重ね塗り
・塗装間隔は、15分ぐらい空けて、乾燥させる
・一定のスピードで、止まらずにスプレーする
などのコツがあります。
どれを欠いても、失敗します。
「スプレー塗装」の失敗する原因は、
・塗りすぎによる「液だれ」
があります。
一度の塗装で、完成の「5%」ぐらいずつ
薄く着色させるのが、綺麗な塗装をする条件です。
塗りすぎなければ、「液だれ」はしません。
1回の塗装は、
4回ぐらい重ね塗りぐらいにすると、
綺麗に塗装できます。
1回の塗装が終わったら、10分~20分ぐらい乾燥させます。
「液だれ」しない状態になるのを待ちます。
それを5回ぐらい繰り返すと、
綺麗なスプレー塗装ができます。
塗料の性質などによって、
回数や乾燥時間を増やして対応します。
説明書をしっかりと読むことが大切。
Back
「液だれ」は大敵
スプレー塗装を一度にしすぎたときに発生する「液だれ」は、
失敗の原因です。
後で、研磨しても、
なかなか跡が消えないのも、
「液だれ」が嫌われる理由。
一度に多量の塗料を吹き付けてしまうことが原因なので、
スプレー塗装は、
「塗装」「乾燥」を小まめに繰り返すことが、
綺麗な塗装への近道です。
むしろ、
少しのスプレー塗装だと、
乾燥の時間も短いので、
少し「塗装」をしては、
「乾燥」をさせることを、
繰り返すのがベストな方法です。
塗装は、
焦らず、
「少しの塗装」と「乾燥」を
繰り返すことが、
綺麗な塗装の近道です。
Back
境界線をはっきりさせるスプレー塗装
スプレー塗装で、
「境界線」をはっきりとさせたい場合は、
「マスキングテープ」を使用します。
「マスキングテープ」を使うのは、
スプレー塗装では一般的な方法です。
塗装をしたくない面を
「マスキングテープ」で丁寧にコーティングし、
スプレー塗装を行い、
スプレーした塗料が、
「半乾き」の状態になったら、
「マスキングテープ」を丁寧に剥がしていきます。
テープについた塗料と塗装面の塗料が、
綺麗に剥がれるぐらいの乾き具合がベストなので、
完全に乾く前に、
「マスキングテープ」を剥がすのを忘れないようにします。
完全に乾いた状態で、
「マスキングテープ」を剥がすと、
塗装したい面の塗装まで剥がれることがあり、
境界線もガタガタになってしまします。
「マスキングテープ」を剥がすタイミングは、
とても重要です。
マスキングテープを丁寧に張れば、
それだけ綺麗な境界線ができます。
Back
「ぼかし」のあるスプレー塗装をする方法
「ぼかし」のあるスプレー塗装をするには、
穴の空いた「かざし」を使用します。
「かざし」は、
「厚紙」「段ボール」などの中心に、
塗装範囲より少し小さい「穴」を空けます。
穴の空いた「かざし」を
塗装面に当てて、
穴を塗装したい面に合わせます。
「かざし」の上から、
スプレー塗装をすると、
穴の空いた範囲にだけ、
スプレー塗装ができます。
このとき、
塗装面から「かざし」を遠ざけると、
「ぼかし」の範囲が広く、
滑らかな「ぼかし」となり、
塗装面に「かざし」を近づけると、
境界線がはっきりした、
「ぼかし」の少ない塗装面となります。
同じサイズの穴の「かざし」でも、
使い方によって、
色々なアレンジができます。
「かざし」を使用すると、
塗装範囲が広がらず、
綺麗にスプレー塗装ができるので、
とても便利な塗装ツールの一つです。
「かざし」は、
小さな塗装面に塗装をするときの必須の技術です。
Back
小さな塗装範囲にスプレー塗装をする方法
小さな範囲にスプレー塗装をするにはコツがあります。
全体にスプレー塗装をするより、
一部分にだけ、
スプレー塗装をする方が難しい。
コツとやり方を知れば、
比較的簡単に、
部分的なスプレー塗装ができます。
境界線をはっきりさせるスプレー塗装
スプレー塗装で、
「境界線」をはっきりとさせたい場合は、
「マスキングテープ」を使用します。
「マスキングテープ」を使うのは、
スプレー塗装では一般的な方法です。
塗装をしたくない面を
「マスキングテープ」で丁寧にコーティングし、
スプレー塗装を行い、
スプレーした塗料が、
「半乾き」の状態になったら、
「マスキングテープ」を丁寧に剥がしていきます。
テープについた塗料と塗装面の塗料が、
綺麗に剥がれるぐらいの乾き具合がベストなので、
完全に乾く前に、
「マスキングテープ」を剥がすのを忘れないようにします。
完全に乾いた状態で、
「マスキングテープ」を剥がすと、
塗装したい面の塗装まで剥がれることがあり、
境界線もガタガタになってしまします。
「マスキングテープ」を剥がすタイミングは、
とても重要です。
マスキングテープを丁寧に張れば、
それだけ綺麗な境界線ができます。
「ぼかし」のあるスプレー塗装をする方法
「ぼかし」のあるスプレー塗装をするには、
穴の空いた「かざし」を使用します。
「かざし」は、
「厚紙」「段ボール」などの中心に、
塗装範囲より少し小さい「穴」を空けます。
穴の空いた「かざし」を
塗装面に当てて、
穴を塗装したい面に合わせます。
「かざし」の上から、
スプレー塗装をすると、
穴の空いた範囲にだけ、
スプレー塗装ができます。
このとき、
塗装面から「かざし」を遠ざけると、
「ぼかし」の範囲が広く、
滑らかな「ぼかし」となり、
塗装面に「かざし」を近づけると、
境界線がはっきりした、
「ぼかし」の少ない塗装面となります。
同じサイズの穴の「かざし」でも、
使い方によって、
色々なアレンジができます。
「かざし」を使用すると、
塗装範囲が広がらず、
綺麗にスプレー塗装ができるので、
とても便利な塗装ツールの一つです。
「かざし」は、
小さな塗装面に塗装をするときの必須の技術です。
Back
「スプレーガン」の使い方
「エアコンプレッサー」を使って、
「塗料」を「スプレー」のように吹き付けることができる「スプレーガン」。
綺麗に仕上げたいときには、
「塗装」は必須。
色々な物に「色」を付けたい人には、「スプレーガン」は必須のアイテム。
「スプレーガン塗装」に「必要な工具」
| エアコンプレッサーの塗装用パーツ | |
|---|---|
| エアコンプレッサー | |
| スプレーガン | |
| エアホース |
「コンプレッサー」と「スプレーガン」を繋ぐホースで、 空気を送るための道具。 |
| カプラー |
「カプラー」は、 気体や液体などの配管に使用されている、 配管の「接続」「分離」を簡単に、確実に行うための接続部品。 「エアプラグ(オス)」と「エアソケット(メス)」の2種類がある。 「エアホースの両端」に、それぞれ、「コンプレッサー側」に「エアソケット」を取り付ける。 |
| シールテープ |
接続部の漏れを防ぐために、 接続部を密着させるために使用するもの。 「ネジ」に巻きつけてから、ネジ部品を取り付けると、 隙間を埋めて、漏れなどを防止してくれる。 「ねじ山」に「6~7巻き」するのが一般的。 |
| レギュレーター |
「減圧弁」とも呼ばれる部品で、 圧縮された空気を、作業に適切な圧力に調整する役割を持つ。 |
| エアフィルター |
「エアーフィルター」は、 圧縮空気の「水分」「油分」「不純物」「臭気」を 除去する機能を持っている部品。 ・水分を除去するエアフィルター → 「ドレンフィルター」 ・不純物を除去するエアフィルター → 「ラインフィルター」「サブミクロンフィルター」 ・油分を除去するエアフィルター → 「オイルミストフィルター」 ・臭気を除去するエアフィルター → 「臭気除去フィルター」 |
| 塗装前の下地処理 | |
| マスク(有機溶剤からのガス除去用など) | |
| 耐水サンドペーパー | |
| 空研ぎペーパー | |
| APラバーサンディングブロック | |
| ボデーパテ | |
| 脱脂剤 |
「塗装面」の油分を取り除くのに使用する。 塗装前には、必ず脱脂をして、塗装を付着しやすいようにする。 |
| 塗装作業 | |
| マスク(有機溶剤からのガス除去用など) |
「塗装」に使われる「シンナー」などの成分を除去できる「塗装マスク」を使用する。 「有機溶剤」からのガス除去用のマスクが「塗装用マスク」として使われている。 塗料の種類によって、効果のある「マスク」を選択する。 |
| 試し塗り用消耗品(板や新聞など) | |
| 計量器 |
「本塗装用塗料」「硬化剤」「希釈剤」を混ぜる際に、 決められた量を計測するために使用する。 |
| ストレーナー |
調合した塗料をスプレーガンのカップに入れる時に、 ゴミの混入を防ぐために使用する濾過装置。 |
| クリーナー |
「工具用」「皮膚用」の「クリーナー」を用意する。 「工具用」は、使用した工具の洗浄に使用する。 「皮膚」に付着した塗料は、「工具用」ではなく「皮膚用」のクリーナーを用意する。 「ガンクリーナー」「ハンドクリーナー」と呼ばれていて、 「成分」「用途」が異なる。 |
| 塗装スタンド | |
| 下塗り用(プラサフなど) | |
| 本塗り用(カラー塗料) | |
| 硬化剤 |
塗料に硬化剤が含まれていることが多いが、 量が多い塗料には、長期保存ができるように「硬化剤」が含まれていないことがある。 使用する前に、「硬化剤」を投入して使用する。 「塗料」の説明書を良く読んでチェックは必須。 |
| 希釈剤 |
スプレーガンで塗装するための塗料は、 液体粘土が低い流性の高い液体状である必要がある。 「希釈剤」は、スプレーガン用に塗料を調整するのに必須。 |
「スプレーガン塗装」をする「手順」
■ 下地処理
■ プラサフで下塗り塗装
↓
■ 本塗装前の下地処理
■ スプレーガンで本塗装する準備
■ 捨て吹き
■ 本塗装
↓
■ 捨て吹きから本塗装
■ クリア塗装前の下地処理
■ クリア仕上げ(クリア塗装)
・塗装されているなら、「耐水ペーパー」で塗装を剥がす。
・「凹み」「穴空き」がある場合は、「パテ埋め」する。
・「耐水ペーパー」で塗装する面を整える
・均一に細かい傷をつけ、塗料が付着しやすくする。
・「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
・プラサフ(プライマーサーフェイサー)を準備する。
↓・「凹み」「穴空き」がある場合は、「パテ埋め」する。
・「耐水ペーパー」で塗装する面を整える
・均一に細かい傷をつけ、塗料が付着しやすくする。
・「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
・プラサフ(プライマーサーフェイサー)を準備する。
■ プラサフで下塗り塗装
↓
■ 本塗装前の下地処理
・「水研ぎ」=「耐水ペーパー#800~1000」で塗装する面を整える
・「ゴミやホコリの除去」
・「脱脂作業」=「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
↓・「ゴミやホコリの除去」
・「脱脂作業」=「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
■ スプレーガンで本塗装する準備
・塗料に適した「硬化剤」「希釈剤」と使い、塗料の量に合わせて調合する。
・スプレーガンのカップに塗料を移す。
↓・スプレーガンのカップに塗料を移す。
■ 捨て吹き
軽く塗料を吹き付ける「捨て吹き」によって、
塗料の特性をチェックする。
「本塗装」の塗料が付着しやすい下地を作る意味がある。
塗装面との相性などをチェックできるので、
必須の工程。
↓塗料の特性をチェックする。
「本塗装」の塗料が付着しやすい下地を作る意味がある。
塗装面との相性などをチェックできるので、
必須の工程。
■ 本塗装
↓
■ 捨て吹きから本塗装
・ダンボールや新聞紙などに「試し吹き」をして「色」「粘土」「吹き具合」などを確認。
↓■ クリア塗装前の下地処理
・「耐水ペーパー#1000」で塗装する面を整える
・「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
↓・「シリコンオフスプレー」で塗装面を「脱脂」する。
■ クリア仕上げ(クリア塗装)
・塗装面に「艶(つや)」「光沢」をだし、表面保護をする塗装
・塗り過ぎによる「液ダレ」をしないように注意する
・「液ダレ」をしたら、研磨して、「液ダレ」を削り消す
・複数回に分けて重ね塗りをすることで、「艶」「光沢」を出す
・塗り過ぎによる「液ダレ」をしないように注意する
・「液ダレ」をしたら、研磨して、「液ダレ」を削り消す
・複数回に分けて重ね塗りをすることで、「艶」「光沢」を出す
「スプレーガン」の「種類」
「スプレーガン」は、
「塗料の送り出し方法」によって、
大きく「3種類」に分類される。
「スプレーガン」の「種類」
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 重力式スプレーガン |
「ガン上部」にカップがあるのが「重力式スプレーガン」。 「重力式スプレーガン」は、 カップ内の「塗料」が、 「自重」「重力」によって押し出されるように、 「ガン」に送り込まれるので、塗料を残さず噴射できるのが特徴。 |
| 吸上げ式スプレーガン |
「ガン下部」にカップがあるのが「吸上げ式スプレーガン」。 「塗料」を吸い上げて噴霧するタイプなので、 塗料がカップ下部に、少量だが残ってしまう。 「重力式スプレーガン」に比べて、「カップ容量」が大きい。 「塗料タンク」が大きくても、 下部にあることで安定性があり、 操作性も良い。 |
| 圧送式スプレーガン |
「塗料」を「圧送タンク」「加圧タンク」に入れて使用するのが、「圧送式スプレーガン」。同 「高面積塗装」に適している。 |
「エアコンプレッサー」の「役割」「選び方」
「エアコンプレッサー」は、
空気を圧縮し、送り出す役割を持っている機器。
「スプレーガン塗装」の動力源となるツール。
「スプレーガン」は、
「エアコンプレッサー」が作り出した
空気の力で、「塗料」を飛ばして、
塗装を行なっていくもの。
「エアコンプレッサー」を選ぶのに、
需要な選択項目は、
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タンク容量 |
DIYでの「スプレーガン塗装」での使用ならば、 「30L~60L」ほどが必要。 「タンク容量」が大きいほど、「パワフル」で「長時間」の使用が可能になる。 |
| 圧縮方式 (オイル式 or オイルレス式) |
「オイル式」は、空気を圧縮する際に、「オイルがエアに混入する」。 「オイルレス式」は、空気を圧縮する際に、「オイルがエアに混入しない」。 |
| 動作音 |
「サイレント式(静音タイプ)」は、 動作音が小さく(65db~70db)、 住宅街のガレージでの使用などに向いている。 |
「スプレーガン」に使用する「塗料」の「調合方法」
「スプレーガン」に使用する「塗料」の「調合方法」は、
各塗料により、若干異なるが、
考え方は同じことが多い。
必ず説明書などを確認の上、
塗料の調合をする。
「スプレーガン用塗料」は、
「硬化剤入り塗料」の調合割合=塗料(6):硬化剤(4)
「スプレーガン用の希釈した塗料=硬化剤入り塗料(5):希釈剤(4)
の調合割合になっている。「スプレーガン用の希釈した塗料=硬化剤入り塗料(5):希釈剤(4)
十分に撹拌して、しっかりと混ぜた後に、
次の工程に移る。
塗料によって、若干異なるが、
「硬化剤入り塗料」を作成し、
「硬化剤入り塗料」を「希釈剤」で薄めるのが流れ。
購入した「塗料」が、
「硬化剤入り」なのかのチェックも必要。
「塗料」を扱う時は、
「塗装用マスク」を必ず着用すること。
「スプレーガン」の「使い方」
「スプレーガン」の「使い方」には、
| スプレー方向 |
「スプレーガン塗装」は、 「縦吹き」or「横吹き」で塗装をする。 「塗装面」の特性に合わせて、「縦吹き」「横吹き」を選択する。 | ||
| 傾き |
「スプレー塗装」では、 塗装する対象物に対して、 「スプレーガン」を「垂直」に構えるのが基本。 | ||
| 距離 |
「スプレー塗装」では、 塗装する対象物に対してスプレーガンを「一定の距離」を保ち、 移動させながら「塗装」をする。 | ||
| 間隔 |
「スプレー塗装」では、 間隔を調整することで、 均一の塗装ができる。 「オーバースプレー」と呼ばれる塗装方法には、 「1回目」で塗装した部分の「約半分」に重なるように、 次の塗装し、塗装面を均一にすることができる。 |
Back
「アメリカントラッド」の色調を目指した塗料「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」

「ミルク」の乳由来成分で作った「水性」の「合成樹脂塗料」。
「アメリカントラッド」の色調を
忠実に再現することを目指して作成された塗料で、
「ミルクペイント」の由来は、「アメリカ開拓時代」。
「ミルクカゼイン」を利用した塗料が使用され、
「家具」などに使用されていた。
塗料の「顔料」として身の回りにある「土」「レンガ」などを使用し、
落ち着いた色調「アーリーアメリカン•アンティーク調」のものが多かった。
使用している「乳由来成分」は、
「森永乳業製」とのこと。
ラベルの説明によると、
成分は、
・水
・合成樹脂(アクリル)
・顔料
・ミルクカゼインペプチド
で構成されていました。
用途別に、
・DIY用
・屋外用
・室内かべ用
・メディウム
の「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」がありました。
サイズは、
・70ml(2度塗り:0.35〜0.45㎡) ¥473(本体価格¥430)
・200ml (2度塗り:1〜1.4㎡)¥990(本体価格¥900)
・450ml(2度塗り:2.2〜3.1㎡) ¥1,870(本体価格¥1,700)
・1.2L(2度塗り:6~8.4㎡) ¥4,070(本体価格¥3,700)
の「4種類」。
昔ながらの
「クリーミー」で「マット」な「仕上がり」が特徴で、
「質感」が「漆喰」にも似ているので、
日本でも人気が出てきている「塗料」です。
 実際に「スノーホワイト」を使ってみましたが、
実際に「スノーホワイト」を使ってみましたが、マットな仕上がりで、
確かに「漆喰」に似ていました。
少し滑らかなテカリがある「漆喰」という感じでした。
なかなか良い仕上がりなので、
とても気に入っています。
「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」のカラーバリエーション

「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」の
カラーバリエーションは、
「全26色」が用意されていました。
これから増えるかもしれません。
詳しくは。
公式WEBをご確認ください。
売り場には、
比較的多くのカラーが用意されていましたが、
・スノーホワイト
・ピスタチオグリーン
・クリームバニラ
などのカラーが綺麗でした。
金属の風合いを再現した「メディウム」というタイプもありました。
こちらも、いつか利用してみたい塗料。
カラーバリエーション「全26色」
・スノーホワイト
・ローストカカオ(miniのみ)
・インクブラック
・アッシュグレー(miniのみ)
・ハニーマスタード
・クリームバニラ
・サンフラワーオレンジ
・ヘンプベージュ
・ターメリックイエロー(miniのみ)
・ピスタチオグリーン
・ガーネット(miniのみ)
・グリーンアーミー
・サンセットパープル(miniのみ)
・ライムミント(miniのみ)
・フロリダピンク
・クロコダイルグリーン
・シトラスピンク(miniのみ)
・ターキーブルー(miniのみ)
・ゴールデンレッド
・ムーンライト(miniのみ)
・アンティークコーラル
・インディアンターコイズ
・ビンテージワイン
・トリトンブルー
・ヘーゼルナッツ(miniのみ)
・ディキシーブルー
「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」の塗り方

「TURNER'S MILK PAINT(ミルクペイント)」は、
クリーミーなので、
塗った時にまだらになりやすい傾向があります。
刷毛で、一度で塗ろうとすると、
上手に塗れないので、
少しずつ伸ばすように、
複数回に分けて、塗り上げるのがこつ。
1度塗り終えたら、
塗料によって、「10分〜20分」ほど時間を置いてから、
次の塗りをはじめてください。
ミルクペイント共通注意事項
・塗装は下地が充分に乾燥した状態で行う。
・気温5度以下での塗装は避ける。
・使用後の刷毛・筆等は、乾かないうちに水洗いする。
・皮膚に付着した場合は、石鹸水で洗い落とす。
・目に入った場合は、多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける。
・誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受ける。
・こどもの手の届かないところに保管する。
・気温5度以下での塗装は避ける。
・使用後の刷毛・筆等は、乾かないうちに水洗いする。
・皮膚に付着した場合は、石鹸水で洗い落とす。
・目に入った場合は、多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける。
・誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受ける。
・こどもの手の届かないところに保管する。
「2度塗り」を想定した「塗装可能面積」は、
・70ml = 0.35〜0.45㎡
・200ml = 1〜1.4㎡
・450ml = 2.2〜3.1㎡
・1.2L = 6~8.4㎡
ほどが目安となっています。
塗装可能な材質は、
・無塗装の木部
・紙
・金属(マルチプライマー使用)
・モルタル(マルチプライマー使用)
などがあります。
塗装不可能な材質には、
・ポリオレフィン(PE,PP)系のプラスチック
・ナイロン
・軟質塩ビ
などがあり、
「塗膜が剥がれたり」「割れが発生する」などの可能性がある。
使用後は必ず密閉し、
直射日光・高温多湿を避けられる場所に保存する。
「乳由来成分」が原料なので、「腐敗」する可能性があります。
テーブルなどの耐久性が必要な場合は、
「上塗り」として「トップコートクリア(UVカット)」を使用した方が良いケースもあり。
Back