Life
掃除 & 洗濯
掃除
洗剤
「汚れ」に適した「洗剤」を選ぶ方法汚れ
「油汚れ」を落とす方法「水あか」を落とす方法場所
「キッチン」を「綺麗」に維持する方法「部屋」を「綺麗」に維持する方法「浴室」を「綺麗」に維持する方法Goods
「食器」を「綺麗」に維持する方法「冷蔵庫」を「綺麗」に維持する方法「ドラム型洗濯機」を「綺麗」に維持する方法「窓」を「綺麗」に維持する方法「鏡」を「綺麗」に維持する方法「エアコン」を「綺麗」に維持する方法「壁」を「綺麗」に維持する方法「シール」を「綺麗」に剥がす方法洗濯
「服」を「綺麗」に維持する方法Material(素材)
「革(レザー)」素材を「綺麗」に「長持ち」させる方法「フェイクレザー」素材を「綺麗」に「長持ち」させる方法収納
「服」を「綺麗」に「収納」する方法
【掃除】「服」を「綺麗」に維持する方法
【洗濯】
「服」を「綺麗」に維持する方法
「服」を「綺麗」に維持する方法
「アクセサリー」の「メンテナンス」方法をまとめています。
「宝石」「貴金属」には、
それぞれ特徴があり、
「メンテナンス」の方法も異なります。
「NG」なお手入れ方法も、
「宝石」「貴金属」にはあります。
ご確認の上、お手入れをするのが重要です。
間違えると、取返しの付かないダメージを与えてしまいます。
水洗いができない宝石は、
・真珠
・トルコ石
・オパール
などがあります。
「ゴールド(金)」は、
・酸性(汗・皮脂)に弱く
・傷になりやすい
という特徴があります。
詳しくは、
下記をご参照ください。
INDEX
■ 「アクセサリー」を使った後のお手入れ
■ 「アクセサリ―」の細かい部分には「つまようじ」
■ 「チェーンネックレス」は「中性洗剤」を入れた「水」に漬け置き
■ 「ネックレス」の「チェーン」が絡まった時の対処方法
■ 「時計」ガラス面の軽い傷には「歯磨き粉」
■ 「ゴールド」のお手入れは「お湯」
■ 熱に強い「ダイヤモンド」だけは「煮沸」してもOK
■ 「真珠」のお手入れは「オリーブオイル」
「靴」を「綺麗」に維持する方法
■ 「靴」汚れの原因■ 「靴」を購入したらすべきこと
■ 「靴」の保管方法
■ 「靴」は「夕方」に購入する
■ 靴を「1日」履いたら「2日」の休息を
■ 「靴ずれ」の防止対策
■ 白い靴が「黄ばむ」のは○○が原因
■ 「靴」に付く汚れを予防する方法
■ 白い「運動靴」には「ベビーパウダー」
■ 「バナナの皮」でも「革」素材を綺麗にできる
■ 小さな傷は、同色の「クレヨン」
■ 「牛乳」は万能の「コーティング剤」
■ 「黒い靴」の汚れ落としには「新聞紙」
「撥水生地」の「撥水性」を復活させる方法
■ 「撥水生地」の「撥水性」を復活させる方法「洗濯物」の「くさい臭い」をなくす方法
■ 「洗濯物の臭い」とは■ 「生乾き臭」の「原因」
■ 「生乾き臭」を無くすための方法
■ 「洗濯物臭」を「予防」する方法
■ 「洗濯槽」の「黒カビ」「汚れ」が「生乾き臭」の原因のことも
■ 【余談】英語の「Smell」と「Odor」の違い
「衣服」に付着した「血液のシミ」を除去する方法
■ 「血液のシミ」の「特性」■ 「血液のシミ」は「アルカリ性成分」で落とす
■ 「血液のシミ」はまず「水洗い」で落とす
■ 「血液のシミ」は「大根おろし」で落とす
■ 「血液のシミ」は「マジックリン」で落とす
■ 「血液のシミ」は「セスキ炭酸ソーダ」で落とす
■ 「血液のシミ」は「塩素系洗剤(カビキラー)」で落とす
■ 最強の「血液のシミ」を落とせる「洗剤」は.......
■ 外出先での緊急の染み抜き対応方法
■ 「シミ取り用洗剤」の選び方
昔ながらの知恵
■ 「血液」のシミを落とす方法
■ 「果汁」のシミを落とす方法
■ 「牛乳」「卵」のシミを落とす方法
■ 「赤ワイン」のシミを落とす方法
■ 「コーヒー」「紅茶」のシミを落とす方法
■ 「醤油(しょうゆ)」のシミを落とす方法
■ 「ソース」のシミを落とす方法
■ 「ファンデーション」の汚れをとる方法
■ 服についた「口紅」を落とす方法
■ 服についた「マニキュア」を落とす方法
■ 「果汁」のシミを落とす方法
■ 「牛乳」「卵」のシミを落とす方法
■ 「赤ワイン」のシミを落とす方法
■ 「コーヒー」「紅茶」のシミを落とす方法
■ 「醤油(しょうゆ)」のシミを落とす方法
■ 「ソース」のシミを落とす方法
■ 「ファンデーション」の汚れをとる方法
■ 服についた「口紅」を落とす方法
■ 服についた「マニキュア」を落とす方法
「アクセサリー」を使った後のお手入れ
「アクセサリー」を使用した後は、
必ずお手入れが必要です。
アクセサリを使用すると、
必ず「汗」「皮脂」が付着します。
そのまま放置すると、
「変色」などの「化学反応」を起こし、
使用できない状態になることもあります。
必ず「アクセサリー」を使用後は、
お手入れをしましょう。
「アクセサリー」使用後のお手入れ方法 ・汚れがひどい時は、「中性洗剤」を入れた「ぬるま湯」に浸す
・「豚」「タヌキ」などの柔らかいブラシで汚れを落とし、しっかりすすぐ
・必ず乾いた「布」で全体を拭き取る
「アクセサリー」を拭く「布」は、
「ベルベット」などの柔らかい布が良い。
水洗いできない宝石 ・真珠
・トルコ石
・オパール
Back
「アクセサリ―」の細かい部分には「つまようじ」
「アクセサリー」の細かい細工の部分に付着した汚れは、
「つまようじ」で汚れを落とします。
「つまようじ」をそのまま使用したり、
先端を「ハンマー」で軽くつぶしたり、
汚れ部分の状況に応じて、
アレンジしながら、
細かい部分の汚れを落とすことができます。
「指輪」の装飾部分や、
時計のベルト部分、
ネックレスのチェーンなど、
使用できる箇所は多いです。
「つまようじ」の他には、
「柔らかいブラシ」「筆」などが効果的です。
Back
「チェーンネックレス」は「中性洗剤」を入れた「水」に漬け置き
「ネックレス」の「チェーン」部分の汚れは、
「中性洗剤」を数滴入れた「水」に、
1時間ほど漬け置きすると、
かなりの汚れを落とすことができます。
気になるしつこい汚れは、
毛の柔らかい「ブラシ」「筆」などで、
「中性洗剤」を漬けて磨くと、
綺麗に落とすことができます。
Back
「ネックレス」の「チェーン」が絡まった時の対処方法
「ネックレス」の「チェーン」が絡まった時の対処方法 細い「ネックレス」になるほど
ありがちな「絡まり」。
細くなるほど、
絡まりをほどくのが大変。
絡まった「ネックレス」は、
「針」を使うと、
「絡まり」がほどけやすくなります。
チェンの一つに「針」を通して、
持ち上げると、スルスルとほどけてくれます。
「針」がない場合は、
「ベビーパウダー」が効果的。
絡まった部分に振りかけると、
スルスルと絡まりがほどけてくれます。
Back
「時計」ガラス面の軽い傷には「歯磨き粉」
「時計」のガラス面に付いた
細かい「傷」には、
「歯磨き粉」が効果的、
「布」「ガーゼ」などに、
「歯磨き粉」を付けて磨くだけです。
小さな「傷」であれば、
「歯磨き粉」を付けて磨くだけで、
ほとんど目立たなくなると思います。
Back
「ゴールド」のお手入れは「お湯」
「ゴールド(金)」は、
「酸性」に弱いので、
「汗」「皮脂」などの「酸性」成分に弱い傾向があります。
比較的柔らかい金属でもあるので、
使用後は、
「柔らかい布」で、全体をしっかり拭き取ります。
汚れが目立つ場合は、「お湯」を付けた「布」で、
優しく拭き取ると、汚れが綺麗にとれます。
硬いもので拭くと、
「ゴールド(金)」は簡単に傷が付きます。
ご注意ください。
Back
熱に強い「ダイヤモンド」だけは「煮沸」してもOK
「ダイヤモンド」は、
他の宝石に比べ、
圧倒的に「熱」に強い宝石。
唯一「熱湯」でお手入れができ、
「煮沸」して煮込んでお手入れができる宝石とのこと。
「中性洗剤」を入れた「熱湯」に、
漬け置きするだけで、
かなりの汚れが落ちます。
酷い汚れの場合は、
「粉せっけん」を少し加え、
「筆」「柔らかいブラシ」「つまようじ」などで、
汚れを書き出したり、
更に煮込んで、
しつこい汚れを落としても大丈夫らしい。
「熱湯」に漬けこんだり、
「煮沸」をした場合は、
「熱」が取れるまで、
拭かずに、布の上に放置し、
「熱」が冷めたら、柔らかい布で、
全体を拭いて上げる。
Back
「真珠」のお手入れは「オリーブオイル」
「真珠」は、
水洗いできない宝石の一つです。
「汗」「化粧品」にも弱く、
デリケートな宝石です。
「真珠」のお手入れの方法は、
「柔らかい布」で、全体をこまめに拭くこと。
たまに、「オリーブオイル」を染み込ませて拭くと良い。
Back
「靴」汚れの原因
「靴」の汚れの原因は、
・泥汚れ
・黄ばみ
が主な原因と言われています。
「泥汚れ」
「泥汚れ」は、「土」「砂」「泥」などが、
「靴」の表面に付着し、
「茶色い汚れ」となります。
「泥汚れ」は、
比較的簡単に落とすことができるので、
ブラシなどで簡単に綺麗にすることができます。
黄ばみ
「黄ばみ」は、「アルカリ性洗剤」の「アルカリ性成分」が残ってしまい、
太陽の紫外線に「アルカリ性成分」が反応して、
「黄色」に変色してしまったことで、
「黄ばみ」汚れとなってしまいます。
他には、
細菌の「糞尿」が「黄ばむ」原因ともなっています。
「アルカリ性成分」の「黄ばみ」は、
「中性洗剤」「酸性成分(お酢 or クエン酸)」
などで漬け置き、
しっかりと「中和」させることで、
「黄ばみ」を落とすことができます。
細菌の「糞尿」による「黄ばみ」は、
「アルカリ性洗剤」「漂白剤」で、
綺麗にすることができます。
「漂白剤」は、「白」の生地のみに使用可能です。
「セスキ炭酸ソーダ」も効果があるそうです。
Back
「靴」を購入したらすべきこと
「靴」を購入したら、
まず、すべきことがあります。
ひと手間かけることで、
「靴」を綺麗に長く使用することができます。
「靴」を購入したら「すべき事」は、
・防水スプレー
・シリコンスプレー
などをすることです。
「防水スプレー」「シリコンスプレー」は、
「靴」に塗布することで、
コーティング効果が生まれ、
汚れが付きにくくなります。
「防水スプレー」の撥水効果は、
「雨対策」だけでなく、
「汚れ」の付着防止にもなります。
「シリコンスプレー」は、
「ゴム」の劣化を遅らせる効果があり、
紫外線などにも強く、
汚れを付きにくくします。
劣化したゴムの艶(つや)を取り戻すこともできるアイテムです。
コーティング作用もあるので、
汚れも付きにくくなり、
ゴム部分も綺麗さが長持ちします。
Back
「靴」の保管方法
「靴」を保管する時には、
・洗濯をする
・湿気対策をする
・ラップに包む
という対策をすると、
「靴」を痛めずに保管することができます。
長期間保管する場合には、
「ラップ」「ビニール袋」などで包むことで、
劣化防止になるそうです。
「靴」の構成部品の「ゴム」などは、
「酸素」に触れると劣化が進むと言われています。
「ラップ」「ビニール袋」で包むことで、
「酸素」から遮断し、
長期間の保存が可能になると言われています。
「靴」を保管する前には、
必ず「洗濯」をしましょう。
「細菌」が付いていると、
劣化が早くなり、
菌の糞尿などは、「黄ばみ」の原因とも言われています。
長期間の保管前には、
「洗濯」「殺菌」が大切になります。
Back
「靴」は「夕方」に購入する
靴を「1日」履いたら「2日」の休息を
「靴ずれ」の防止対策
「靴ずれ」の防止対策は、
・「踵(かかと)」部分に「紙製テープ」を貼る
・「踵(かかと)」部分に「蝋(ロウ)」を刷り込む
・「踵(かかと)」部分に「石けん」を刷り込む
などの方法があります。
あらかじめ、
「靴ずれ」予防対策をしておくと、
かなりの違いが生まれます。
Back
白い靴が「黄ばむ」のは○○が原因
「靴」が「黄ばむ」のは、
「アルカリ性物質」が紫外線に反応することで、
「黄色」に変色してしまう性質があるから。
「靴」を洗う洗剤の多くが、
「アルカリ性」の洗剤。
その「アルカリ性洗剤」の成分が、
靴の繊維に残り、
太陽の紫外線に反応して、
「靴」が「黄ばむ」という反応が発生する。
「黄ばむ」のを予防するには、
靴を洗ったときに、
しっかりとすすぎ、
アルカリ性成分を洗い流すことが大切。
「靴」が既に黄ばんでしまった場合は、
「酸性」成分で中和させると良い。
「中性洗剤」「酸性成分(お酢 or クエン酸)」を使用し、
ぬるま湯に付けた状態で、
しっかりと「アルカリ性物質」を洗い流し、
中和させることで、
本来の白さなどに、靴が戻ります。
酷い場合は、
「中性洗剤」「酸性成分(お酢 or クエン酸)」に、
2時間~3時間ほど漬けこんでから洗うのが良い。
最近では、
「オキシクリーン」という「酸素系漂白剤」が、
漂白に効果的との噂を耳にします。
つけ置きをすると、綺麗に漂白されるとのことです。
Back
「靴」に付く汚れを予防する方法
汚れを予防する方法として、
・シリコンスプレー
・撥水スプレー(防水スプレー)
・「蝋(ロウ)」
などがあります。
汚れが付きにくくなるので、
購入後にしておくと、
靴が汚れにくくなります。
シリコンスプレー
「シリコンスプレー」は、何かと万能なスプレー。
「シリコンオイル」が原料で、
塗ると保護コーティングの役目もしてくれます。
購入したらすぐに、
「布」などに吹き付けて、
拭きながら、刷り込みます。
数か月間ぐらいで効果がおちてしまうので、
定期的にメンテナンスすると良いです。
撥水スプレー(防水スプレー)
撥水スプレー(防水スプレー)は、「シリコンスプレー」と同様に、
「撥水効果」と「コーティング効果」があります。
靴全体に、スプレーするだけで、
簡単に塗ることができます。
「撥水」すると同時に、
汚れを付きにくくしてくれます。
購入後にすぐ行うのがおすすめ。
効果の持続性が短めなので、
1か月ごとぐらいにスプレーするのが良い。
蝋(ロウ)
「蝋(ロウ)」は、昔ながらの方法。
刷り込むように、
塗りつけることで、
撥水効果とコーティング効果があります。
Back
白い「運動靴」には「ベビーパウダー」
白い「運動靴」の細かい所は、
「ベビーパウダー」を使うと綺麗になるらしい。
「靴ひも」「靴ヒモの穴」などに付いた黒い汚れに、
「ベビーパウダー」を刷り込み、
はたき落とすことで、
汚れを吸着してくれて綺麗になるそうです。
「ベビーパウダー」の白い粉が、
お化粧のように働き、
白く見えるようにもなるそうです。
残った「ベビーパウダー」は、
次に靴を洗ったときに、
汚れと一緒に落とせるので、
そこでも綺麗になる貢献をしてくる。
Back
「バナナの皮」でも「革」素材を綺麗にできる
「バナナの皮」の内側に付いている白い部分は、
「革製品」のような
滑らかな素材の汚れを落とすのに効果的。
優しくこすってあげると、
クリームや研磨剤のように、
汚れを綺麗に落とすことができます。
Back
小さな傷は、同色の「クレヨン」
「クレヨン」は、油性分なので、
「ワックス」や「蝋」のような効果があります。
小さな傷に、
同色の「クレヨン」を刷り込むことで、
小さな傷は、綺麗に見えなくなります。
刷り込んだ後は、布などで綺麗に拭き取れば完成です。
色が異なると目立つことがあるのでご注意下さい。
Back
「牛乳」は万能の「コーティング剤」
「黒い靴」の汚れ落としには「新聞紙」
黒い靴で、
特に「黒い革靴」の汚れ落としには、
「新聞紙」が便利です。
「新聞紙」で「黒い靴」を磨くと、
汚れを落としてくれて、
余計な水分を吸収し、
新聞紙のインクによって、
艶が出て綺麗になります。
特に、「黒い革靴」に効果的。
Back
「撥水生地」の「撥水性」を復活させる方法
「撥水生地」の「撥水性」を復活させる方法があります。
「撥水生地」メーカーが提示する内容でもあるので、
公式WEBなどにも掲載されているはずです。
「撥水生地」の種類によって、
方法が若干異なるようなので、
「洗濯表示タグ」や「公式WEB」などで、
実行前に必ずご確認下さい。
「撥水生地」の仕組みは、
「撥水基」と呼ばれる微細な「突起」が、
いくつも立ち並ぶことで、
水を弾く仕組みを構成しています。
「撥水基」は、水の分子よりも細かいので、
「撥水基」が立ち並ぶと隙間に入ることができなくなります。
「撥水基」によって
「撥水生地」に染み込むことができなくなった水は、
表面を流れるように弾かれます。
「撥水生地」の防水は、
「撥水基」による仕組みによるものです。
「撥水機能」が弱くなった状態というのは、
「撥水基」が倒れたりしてしまうことで、
水の分子が入る隙間ができている状態。
「撥水機能」は、
「撥水基」の状態を元に戻すことで、
「撥水力」が復活するようになっているそうです。
「撥水基」を起こして、規則正しく立ち並ぶようにすることが重要です。
「撥水生地」と呼ばれる生地の種類
「撥水生地」には、
・ゴアテックス社製品
などの様々な種類の生地があります。
それぞれの生地で、
処理方法が若干異なる可能性があります。
公式WEBや、「洗濯タグ」で処理方法をご確認下さい。
・ゴアテックス社製品
などの様々な種類の生地があります。
それぞれの生地で、
処理方法が若干異なる可能性があります。
公式WEBや、「洗濯タグ」で処理方法をご確認下さい。
「撥水力」を復活させる方法
「撥水力」を復活させる方法は、
「撥水基」を起こしてあげる作業になります。
「撥水基」を起こし復活させるには、
簡単に言えば、
「乾燥機能付き洗濯機」であれば、
乾燥までを行えば、
「撥水力」が復活するそうです。
「ドライヤー」の「熱風」でも、
「撥水基」が起き上がり、
復活するそうです。
洗濯後に、
陰干しをして乾燥させた後、
低温(80~120℃)のアイロンを、
必ず「あて布」してかけると、
「撥水基」が立ち上がるそうです。
「アイロン」は、
「高温」でかけると、
「撥水生地」「ゴム部分」などが溶けてしまうので、
「絶対NG」の行動とのこと。
「撥水基」を起こしてあげる作業になります。
「撥水基」を起こし復活させるには、
・洗濯をする
・乾燥させる
・熱を加える
という作業だけです。・乾燥させる
・熱を加える
簡単に言えば、
・乾燥機をかける
・ドライヤーをかける
・低温アイロン(80~120℃)をかける
という方法があります。・ドライヤーをかける
・低温アイロン(80~120℃)をかける
「乾燥機能付き洗濯機」であれば、
乾燥までを行えば、
「撥水力」が復活するそうです。
「ドライヤー」の「熱風」でも、
「撥水基」が起き上がり、
復活するそうです。
洗濯後に、
陰干しをして乾燥させた後、
低温(80~120℃)のアイロンを、
必ず「あて布」してかけると、
「撥水基」が立ち上がるそうです。
「アイロン」は、
「高温」でかけると、
「撥水生地」「ゴム部分」などが溶けてしまうので、
「絶対NG」の行動とのこと。
「撥水性能」が復活しない場合の対応策
「撥水基」が立ち上がらず、
「撥水性能」が復活しない場合は、
・市販の「撥水スプレー」を使う
・撥水剤を使う
などの方法もあります。
しかし、
注意が必要です。
「撥水スプレー」「撥水剤」の中には、
「透湿性」を失わせてしまうものがあります。
「透湿生地」には、
「ニクワックス」などの専用の撥水剤を使用します。
「撥水剤」は、
繊維を個別にコーティングするので、 どのような繊維にも使えます。
「撥水剤」に漬け込むことで、
繊維を全体的にコーティングします。
プロも「撥水剤」を利用して、
撥水効果を適用しています。
「撥水剤」は、
温度管理をしっかりすることが大切。
「撥水性能」が復活しない場合は、
・市販の「撥水スプレー」を使う
・撥水剤を使う
などの方法もあります。
しかし、
注意が必要です。
「撥水スプレー」「撥水剤」の中には、
「透湿性」を失わせてしまうものがあります。
「透湿生地」には、
「ニクワックス」などの専用の撥水剤を使用します。
「撥水剤」は、
繊維を個別にコーティングするので、 どのような繊維にも使えます。
「撥水剤」に漬け込むことで、
繊維を全体的にコーティングします。
プロも「撥水剤」を利用して、
撥水効果を適用しています。
「撥水剤」は、
温度管理をしっかりすることが大切。
Back
「血液のシミ」の「特性」
「血液」の「成分」は、
「約90%」は「水分」。
残りの「約10%」は、
・「アルブミン」「グロブリン」「血液凝固因子」等の「タンパク質」
・少量の糖質
・脂質
・無機塩類
などで構成されている。
付着直後の「血液のシミ」は、
「冷水」で簡単に「洗い流す」ことが可能だが、
時間が経過すると、
「水分」がなくなり、
他の成分が凝固に付着してしまい、
「血液のシミ」は落ちにくくなる。
更に、
「熱」「日光」にさらされると、
「血液のシミ」は、
更に除去しにくくなる。
Back
「約90%」は「水分」。
残りの「約10%」は、
・「アルブミン」「グロブリン」「血液凝固因子」等の「タンパク質」
・少量の糖質
・脂質
・無機塩類
などで構成されている。
付着直後の「血液のシミ」は、
「冷水」で簡単に「洗い流す」ことが可能だが、
時間が経過すると、
「水分」がなくなり、
他の成分が凝固に付着してしまい、
「血液のシミ」は落ちにくくなる。
更に、
「熱」「日光」にさらされると、
「血液のシミ」は、
更に除去しにくくなる。
| 成分 | 説明 |
|---|---|
| アルブミン |
血液中に「100種類以上」存在する「タンパク質(総タンパク)」の中で、 「約60%」ほどという、最も多く含まれる占める「タンパク質」。 「アルブミン」は、 主に「肝臓」で生成される「たんぱく質」。 「血漿タンパク」の中で、血管内に「水分」を保持する最大の働きをしている。 「血液中」の「水分量」を調整する重要な働きをしている。 血液中の「アルブミン」が低下すると、 血管の外に「水分」が漏れ出し、 「全身のむくみ」「腹水」「胸水(お腹や胸に水がたまること)」などの症状が出る。 |
| グロブリン |
血液成分の中で、 「免疫」の機能を担当している成分らしい。 「水」には溶けないが、 「薄い塩類溶液」に溶け、 「熱」で「凝固」するという特性がある。 |
| 血液凝固因子等のタンパク質 |
「プロトロンビン」「フィブリノーゲン」などがある。 |
| 少量の糖質 | |
| 脂質 | 「酸性成分」 |
| 無機塩類 |
Back
「血液のシミ」は「アルカリ性成分」で落とす
「血液」は、
「タンパク質」が主な成分で、
「血液のシミ」が除去しにくい原因となっている。
「タンパク質」を「除去」「分解」するには、
「アルカリ性成分」で行える。
「アルカリ性成分」は、
「タンパク質」の「構造」を緩め、
「分解」することができる。
「タンパク質」を「分解」することができる
「アルカリ性成分」を活用することで汚れを落とすことが可能。
Back
「タンパク質」が主な成分で、
「血液のシミ」が除去しにくい原因となっている。
「タンパク質」を「除去」「分解」するには、
「アルカリ性成分」で行える。
「アルカリ性成分」は、
「タンパク質」の「構造」を緩め、
「分解」することができる。
「タンパク質」を「分解」することができる
「アルカリ性成分」を活用することで汚れを落とすことが可能。
「アルカリ性」の「洗剤」
| pH値 | 性質 | 商品名 |
|---|---|---|
| pH 7 | 中性 | 真水(参考) |
| pH 8 | 弱アルカリ性 | 重曹 |
| pH 9 | 弱アルカリ性 | セスキ炭酸ソーダ |
| pH 10 | 弱アルカリ性 | 石鹸 |
| pH 11 | アルカリ性 | オキシクリーン |
| pH 12 | アルカリ性 | アルカリ電解水 |
| pH 13 | アルカリ性 | カビキラー・キッチンハイター |
Back
「血液のシミ」はまず「水洗い」で落とす
「血液のシミ」は、
必ず「水洗い」で洗い落とします。
「お湯洗い」は、
血液成分を溶かして、
汚れを広げてしまいます。
初期段階では、
「お湯」で「血液のシミ」を洗うのは「NG」。
「血液中のタンパク質」を固まらせてしまうので、
「血液のシミ」を定着させてしまうそうです。
「血液のシミ」の場合は、
まず、「水洗い」を必ずして、
落ちなかった場合に、
次のステップに進みます。
Back
必ず「水洗い」で洗い落とします。
「お湯洗い」は、
血液成分を溶かして、
汚れを広げてしまいます。
初期段階では、
「お湯」で「血液のシミ」を洗うのは「NG」。
「血液中のタンパク質」を固まらせてしまうので、
「血液のシミ」を定着させてしまうそうです。
「血液のシミ」の場合は、
まず、「水洗い」を必ずして、
落ちなかった場合に、
次のステップに進みます。
Back
「血液のシミ」は「大根おろし」で落とす
「大根おろし」には、
「アミラーゼ」という
「タンパク質」を分解する成分が含まれている。
「血液」の「タンパク質」を分解することで、
「血液のシミ」を除去することができる。
「水洗い」でも落ちない「血液」の汚れは、
「大根おろし」を使用して、
落とします。
「大根おろし」を「ガーゼ」などの「布」で包み、
「血液のシミ」の部分を優しく叩くように、
「大根おろしの成分液」を染み込ませる。
しつこい「血液のシミ」の場合は、
少し時間を置きます。
目に見えて、
「血液のシミ」が除去されたら、
「水洗い」をして終了です。
Back
「アミラーゼ」という
「タンパク質」を分解する成分が含まれている。
「血液」の「タンパク質」を分解することで、
「血液のシミ」を除去することができる。
「水洗い」でも落ちない「血液」の汚れは、
「大根おろし」を使用して、
落とします。
「大根おろし」を「ガーゼ」などの「布」で包み、
「血液のシミ」の部分を優しく叩くように、
「大根おろしの成分液」を染み込ませる。
しつこい「血液のシミ」の場合は、
少し時間を置きます。
目に見えて、
「血液のシミ」が除去されたら、
「水洗い」をして終了です。
Back
「血液のシミ」は「マジックリン」で落とす
「大根おろし」に含まれる
タンパク質分解酵素「アミラーゼ」と似ている成分が含まれている
なので、
「血液のシミ」を落とすことができる。
「血液のシミ」の部分に、
「マジックリン」を吹き付けて、
そのまま時間を置くだけでよい。
「スポンジ」を使って、
「叩く」ように落としても良い。
水で洗い流して、
「血液のシミ」が、少し残っているなら、
同じ作業を繰り返す。
Back
「血液のシミ」は「セスキ炭酸ソーダ」で落とす
「アルカリ性」なので、
「タンパク質」を分解する効果があり、
「血液のシミ」に効果的。
「セスキ炭酸ソーダ」は、
「アルカリ性」が強いですが、
「漂白力」はそれほど強くないので、
「洗濯物」全般に使用できる。
「色もの」の「衣類」に使用するなら、
「塩素系洗剤」では、
「色」まで落としてしまう可能性があるので、
「セスキ炭酸ソーダ」「重曹」などを使用するのが良い。
Back
「血液のシミ」は「塩素系洗剤(カビキラー)」で落とす
「タンパク質」の分子構造を変化させ、
「分解」することで、
「タンパク質の汚れ」を落とす。
「塩素」は、
強力な「酸化剤」なので、
「タンパク質」の「ペプチド結合」を切断して、
「アミノ酸」へと「分解」する。
「アミノ酸」になることで、
「水分」に溶けやすく、混ざりやすくなる。
ゆえに、「タンパク質の汚れ」を綺麗に除去することができる。
「塩素系洗剤」には、
「界面活性剤」も含まれていて、
「油」と「水」を混ぜて「乳化」させて、
浮かび上がらせる作用もあり、
その力も加わり、
「タンパク質の汚れ」を更に「除去」しやすくしてくれる。
「タンパク質系の汚れ」を除去するのに、とても適している。
「塩素系洗剤」の主成分は、
「次亜塩素酸ナトリウム」を主成分としていて、
高い「殺菌力」「漂白力」を持っている。
「塩素系洗剤」の種類
・カビキラー・キッチンハイター
Back
最強の「血液のシミ」を落とせる「洗剤」は.......
実践してみて、
「血液のシミ」に効果的な「最強」の「洗剤」は、
「塩素系洗剤」でした。
「血液のシミ」の場所に吹きかけて、
「10分ぐらい」で、痕跡が見つけられないぐらい綺麗になりました。
「白い衣服」ならば、「血液のシミ」には「塩素系洗剤」です。
「色のある衣服」であれば、「セスキ炭酸ソーダ」が「最強」の洗剤でした。
「色のある衣服」の場合は、
「塩素系洗剤」では、
「色」まで落としてしまうぐらいの「漂白効果」がある。
「セスキ炭酸ソーダ」は、
「漂白効果」はあるが、「強く」はない。
Back
外出先での緊急の染み抜き対応方法
外出先で、急にシミ取りをしたい時に使えるツールは、
・ウェットティッシュ(水性の汚れ)
・クレンジングシート(油性の汚れ)
・アルコールシート(油性の汚れ)
・アルコール消毒液(油性の汚れ)
などがあります。
擦らずに、叩くようにして、
シミ汚れを落とすことができます。
緊急対応用で染み抜き用では無いので、
応急処置程度で利用できると考えてください。
染み抜き用洗剤にはかないません。
Back
「シミ取り用洗剤」の選び方
「シミ取り用洗剤」は、
「液体タイプ」が主流で、
液体タイプの「シミ取り用洗剤」をどう使うかの工夫がされているみたいです。
「水性汚れ」「油性汚れ」「酸性汚れ」「アルカリ性汚れ」のすべてに対応しているようなので、
1本あれば、ほとんどの汚れに対応できるようになってます。
「シミ取り用洗剤」の使用形態は、
・液体ボトルタイプ
・スプレータイプ
・携帯タイプ
・電動タイプ
などがあるみたいです。
狭い範囲のシミ汚れには、
・液体ボトルタイプ
・携帯タイプ
などが良く使われています。
シミ汚れに、「シミ取り用洗剤」を付けてから洗う時に便利です。
広い範囲のシミ汚れには、
・スプレータイプ
が便利です。
シミ汚れに、スプレーを吹きかけるだけでよいので、
漬け置き洗いなどには便利そうです。
乾いた頑固なシミ汚れには、
・電動タイプ
が便利。
電動で振動して叩き出しをしてくれるので、
めったにないけど、
一家に一台あると便利だと思います。
評判のシミ取り用洗剤
評判のいい「シミ取り用洗剤」として知られるのは、
などの洗剤があります。
花王「ワイドハイター クリアヒーロー ラク泡スプレー」
酸素系漂白剤でおなじみ「ワイドハイター」の「シミ取り用漂白剤」。シミ汚れにスプレーするだけの便利アイテム。
などの洗剤があります。
圧倒的な洗浄力と高評価のライオン「トップ プレケア シミ用」
かなりの洗浄力で、「シミ取り用洗剤」の中ではトップクラスらしいです。
シミ汚れを叩きやすいスポンジヘッドになっているので、
手を汚さずに、シミ汚れに洗剤を付けれるようになっています。
圧倒的な洗浄力ということで、
家に常備しておくのは、この一本という人も多いそうです。
個人的には、スプレータイプも欲しい気がします。
叩き出し用にこの一本とスプレータイプの一本と2つ欲しい。
コストコで人気の漂白系洗剤「グラフィコ「オキシクリーン マックスフォース」」
使ったことがないけど、
評判が良いのでメモ中。
洗濯前に汚れにスプレーしておくと、
シミ汚れも凄く綺麗になるという評判。
でも、価格が高いのが気になる。。。。。
コストコで購入するなら安いのかな?
定番の酵素系漂白剤「ワイドハイター」シリーズの花王「ワイドハイター クリアヒーロー ラク泡スプレー」
花王「ワイドハイター クリアヒーロー ラク泡スプレー」。
手ごわいシミも綺麗にしてくれると評判。
定番の「ワイドハイター」シリーズで、
安心の「花王」ブランド。
自宅に欲しい「染み抜き用電動振動ハンディ」
Back
「血液」のシミを落とす方法
「血液」のシミは、
必ず「水洗い」で洗い落とします。
「お湯洗い」は、
血液成分を溶かして、
汚れを広げてしまいます。
「水洗い」でも落ちない「血液」の汚れは、
「大根おろし」を使用して落とします。
「大根」に含まれる「酵素」によって、
シミを落とすことができます。
適量の「大根おろし」を布などで包み、
「血液」のシミ部分を叩き落とします。
Back
「果汁」のシミを落とす方法
「果汁」のシミは、
軽いものであれば、
「お酢」で落とすことができます。
「果汁」が洋服についた場合、
すぐにつまみ洗いをすれば、
シミにならないので大丈夫。
「果汁」が付いたのを、
放置しておくと、
茶色い頑固なシミになります。
茶色い頑固なシミは、
水洗いで落とすことは難しいので、
「お酢」を付けた布で、
叩き出すように落とします。
「お酢」で落ちない場合は、
「ホウ酸水」を使って同じように、
叩き洗いをします。
Back
「牛乳」「卵」のシミを落とす方法
「牛乳」「卵」などの、
「動物性タンパク質」を含んだ食材は、
放置すると布地が変色してしまいます。
付いた直後であれば、
水で絞ったタオルで拭き取り、
その後、しっかりと繊維にあった洗い方で、
しっかりと汚れを落とします。
Back
「赤ワイン」のシミを落とす方法
「コーヒー」「紅茶」のシミを落とす方法
「コーヒー」「紅茶」は、
染色の材料として用いられることもあるので、
服などについてしまうと、厄介なシミになりやすい。
こぼしてすぐの場合は、
「水」で落とせますが、
シミが残った場合は、
「糖分」の入っていない「炭酸水」を使って叩くように拭き取ると、
「コーヒー」「紅茶」のシミを落とすことができます。
Back
「醤油(しょうゆ)」のシミを落とす方法
「醤油(しょうゆ)」のシミは、
お酒で押さえることで落し取ることができます。
「醤油(しょうゆ)」のシミの下に布をおき、
お酒をたっぷりと、「醤油(しょうゆ)」のシミにかけ、
綺麗な布で、上から抑える。
「醤油(しょうゆ)」のシミが下に落ちていくので、
繰り返し行うことで、
「醤油(しょうゆ)」のシミを落とすことができる。
ポイントは、「擦らないこと」。
上から押さえたり、叩いたりして、
「醤油(しょうゆ)」のシミを落とすのがポイントです。
Back
「ソース」のシミを落とす方法
「ソース」のシミは、
「汗止めパウダー」などを振りかけて、
「ソース」のシミを取ることができる。
「汗止めパウダー」は、
粒子が細かく吸収性に優れているので、
「ソース」を吸い上げてくれる。
パウダーがしっかり吸収してくれたら、
粉を落として、濡れタオルで、叩くようにして落とす。
Back
「ファンデーション」の汚れをとる方法
「ファンデーション」が、洋服についてしまうことは、
よくあるそうです。
「ファンデーション」は、
「アルコール」で落とすことができるので、
「アルコール」を含む「化粧水」を
コットンに含ませて、
トントンと叩いて拭き取ると、
「アルコール」成分のおかげで、
汚れが綺麗に取れます。
仕上げは、
乾いたタオルか、
硬く絞ったタオルなどで拭き取ってください。
洋服を痛めないように、
力を入れず、
根気よく、優しく、
少しずつ行うのがポイントです。
Back
服についた「口紅」を落とす方法
「口紅」は、
油分で構成されているので、
水で洗っても落ちない上に、
色素が広がるので、
水洗いはNGです。
「口紅」を落とすには、
「バター」を使って、
汚れをもみほぐします。
口紅の油分が溶け出し、
薄められます。
その後、
アルコールを含ませた布で、
丁寧に優しく少しずつ叩いて落とします。
Back
服についた「マニキュア」を落とす方法
「マニキュア」は、
「ベンジン」や「シンナー」で、
叩き出すように落とし、
その後、漂白します。
「ベンジン」「シンナー」の代わりに、
「灯油」を使うことも可能です。
しかし、
「ベンジン」「シンナー」「灯油」は、
「綿」「ポリエステル」以外の繊維素材を傷める可能性があります。
注意が必要です。
Back
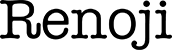
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2063cdfe.b6c6ceb3.2063cdff.0e01dca2/?me_id=1261122&item_id=10122992&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F224%2F4901301310224.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2063cdfe.b6c6ceb3.2063cdff.0e01dca2/?me_id=1261122&item_id=10243828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F095%2F4961161600095.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2063cdfe.b6c6ceb3.2063cdff.0e01dca2/?me_id=1261122&item_id=10620825&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F516%2F4901609009516.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2063cdfe.b6c6ceb3.2063cdff.0e01dca2/?me_id=1261122&item_id=10557381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F478%2F4901301511478.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214eeb47.14ca488e.214eeb48.3339f927/?me_id=1332839&item_id=10008515&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fonesmart%2Fcabinet%2F9%2F4903301527039.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214f72d9.269e5422.214f72da.1bf7aa8a/?me_id=1388565&item_id=10005902&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbellpear%2Fcabinet%2Fr_1599565455%2F4928508116444.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1de9dbba.511604c5.1de9dbbb.5f824ca2/?me_id=1254471&item_id=10069197&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsundrug%2Fcabinet%2F32zakka2%2F4901301259349.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214f7920.61b48b7c.214f7921.c51d766e/?me_id=1280896&item_id=10097059&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Furutoragion%2Fcabinet%2Fshopping69%2Fhcw-shw10-n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/214f7cfa.67b4d92f.214f7cfc.dfba019e/?me_id=1366524&item_id=10001451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwholesale-tokyo%2Fcabinet%2F06347286%2Fcompass1602745050.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)