Life
掃除 & 洗濯
掃除
洗剤
「汚れ」に適した「洗剤」を選ぶ方法汚れ
「油汚れ」を落とす方法「水あか」を落とす方法場所
「キッチン」を「綺麗」に維持する方法「部屋」を「綺麗」に維持する方法「浴室」を「綺麗」に維持する方法Goods
「食器」を「綺麗」に維持する方法「冷蔵庫」を「綺麗」に維持する方法「ドラム型洗濯機」を「綺麗」に維持する方法「窓」を「綺麗」に維持する方法「鏡」を「綺麗」に維持する方法「エアコン」を「綺麗」に維持する方法「壁」を「綺麗」に維持する方法「シール」を「綺麗」に剥がす方法洗濯
「服」を「綺麗」に維持する方法Material(素材)
「革(レザー)」素材を「綺麗」に「長持ち」させる方法「フェイクレザー」素材を「綺麗」に「長持ち」させる方法収納
「服」を「綺麗」に「収納」する方法
【掃除】「キッチン」の「汚れ」を落とす方法
【掃除】
「キッチン」の「汚れ」を落とす方法
詳しくは、
下記をご参照ください。
INDEX
■ はじめに
■ 「油汚れ」を「効率的」に落とす方法
■ 「キッチンペーパー」は「油汚れ」に最適
■ 「油汚れ」が良く落とせる「キッチンクロス」を選ぶのも重要
■ 「油汚れ」には「アルコール」
■ 「水」を「沸騰」させて蒸気で「油汚れ」を柔らかくする
■ 「小麦粉」で「油汚れ」を落とせる
■ 「アルカリ性」の「米の研ぎ汁」は「酸性」の「油汚れ」に効果的
■ 「油汚れ」が多い場所は「暖かい季節」に掃除する
■ 「油汚れ」が良く落とせる「キッチンクロス」を選ぶのも重要
■ 「油汚れ」には「アルコール」
■ 「水」を「沸騰」させて蒸気で「油汚れ」を柔らかくする
■ 「小麦粉」で「油汚れ」を落とせる
■ 「アルカリ性」の「米の研ぎ汁」は「酸性」の「油汚れ」に効果的
■ 「油汚れ」が多い場所は「暖かい季節」に掃除する
「キッチン」の「換気扇」を「綺麗」に維持する方法
■ 付着している軽い「油汚れ」は「キッチンペーパー」で拭き取る■ 油汚れには「アルカリ性」洗剤
■ 「重曹溶液」に漬けこんで「油汚れ」を綺麗にする方法
■ 「重曹」ペーストを塗って「油汚れ」を綺麗にする方法
■ 手の届きにくい場所には「重曹スプレー」
■ 「油汚れ」は「煮沸」でスッキリ
■ 最強クラスの「アルカリ性洗剤」で「油汚れ」を落とす
「キッチンコンロ」を綺麗に維持する方法
■ 「油汚れ」は「キッチンペーパー」で簡単に綺麗になる■ 日々の軽い汚れには「台所用中性洗剤」
■ 「油汚れ」は「アルコールスプレー」で綺麗にする
■ 「油汚れ」は「重曹スプレー(アルカリ性洗剤)」で綺麗にする
■ 「五徳」を綺麗にする方法
■ 「焦げ付き」には「重曹水」で「煮沸」
■ 「焦げ付き」には「重曹ペースト」
■ 「しつこい焦げ付き」は傷が付くけど最終兵器は「スチールウール」
「冷蔵庫」を「綺麗」にする方法
■ 「冷蔵庫掃除」は「水拭き」「乾拭き」が基本■ 「アルコール」で「拭き掃除」するのが簡単
■ 「わさび水」で「冷蔵庫」の「カビ予防」
■ 「冷蔵庫」の「臭い」には「重曹」が使える
■ 「炭」で「冷蔵庫内」を「消臭」できる
「キッチン」の「シンク」を「綺麗」にする方法
■ 「シンク」を「ピカピカ」にするのに使える「アイテム」■ 「排水口」の「ヌメリ」を「抑制」する「方法」
■ Gallery
はじめに
「油汚れ」を「効率的」に落とす方法
 「油汚れ」は、
「油汚れ」は、小さな汚れであれば、
簡単に落とせるが、
「広い範囲」の「油汚れ」は、
効率的に掃除をしないと、
かなり手間のかかる「掃除」になる。
「油汚れ」を「効率的」に落とす「手順」
・「スクレーパー(ヘラ)」で「油の塊」を除去する
・「キッチンペーパー」で「油分」を吸収させる
・「キッチンクロス」で、綺麗に拭き取る
・「洗剤(アルカリ性・中性)」で洗い落とす
・「キッチンクロス」で「水分」を拭き取る
・洗い残しを「キッチンペーパー」で拭き取る
という流れが、
「油汚れ」を掃除する効率的な方法。
・「キッチンペーパー」で「油分」を吸収させる
・「キッチンクロス」で、綺麗に拭き取る
・「洗剤(アルカリ性・中性)」で洗い落とす
・「キッチンクロス」で「水分」を拭き取る
・洗い残しを「キッチンペーパー」で拭き取る
という流れが、
「油汚れ」を掃除する効率的な方法。
Back
「キッチンペーパー」は「油汚れ」に最適
「油」を良く吸収するように作られている。
「キッチンペーパー」は「油分」を吸収させるのに最適。
「フライパン」の過剰な「油分」を吸収させるにも、
「キッチンペーパー」が使われることでも知られる。
「キッチンペーパー」は、
使って廃棄するだけで良いので、
とても効率的。
Back
「油汚れ」が良く落とせる「キッチンクロス」を選ぶのも重要
 「キッチンクロス」には、
「キッチンクロス」には、「油」をよく吸収する「キッチンクロス」がある。
「キッチン」の掃除には、
「道具」を選ぶのも大切。
「繊維」の特性によって、
「油汚れ」を吸着させる原理のようですが、
「油分」を簡単に除去できるのは、
かなり効率がよくなる。
「油分」が除去できれば、
洗剤を使用して、
短時間で綺麗にすることができる。
「油」をよく吸収する「キッチンクロス」はおすすめ。
1つは常備しておいた方がいよい。
Back
「油汚れ」には「アルコール」
 「キッチン」には多い「油汚れ」。
「キッチン」には多い「油汚れ」。「アルコール」には、
「油」「汚れ」を分解する効果がある。
普段の「油汚れ」を掃除するのには、
「アルコール」は最適。
「スプレータイプ」の「キッチン用アルコール」も販売されているので、
「1つ」置いておけば、
「キッチン掃除」に役立つ。
「アルコール」を含む「お酒」などを使用しても、
「油汚れ」を落とすことができる。
「お酒」の種類によって、
「臭い」が残ったりする。
Back
「水」を「沸騰」させて蒸気で「油汚れ」を柔らかくする
 「キッチン掃除」をする前に、
「キッチン掃除」をする前に、「水」を「沸騰」させて、
蒸気で「油汚れ」を柔らかくすると、
「油汚れ」が落としやすくなる。
「換気扇掃除」をする前にも、
蒸気で「油汚れ」を柔らかくすると、
「汚れ」が落としやすくなる。
Back
「小麦粉」で「油汚れ」を落とせる
 「小麦粉」を
「小麦粉」を「油汚れ」の上に撒くことで、
「小麦粉」が「油分」を吸収し、
拭き取ると、綺麗になる。
「小麦粉」に「少量の水」を加えて、
「ペースト」にすることで、
「油汚れ」に付けて、「ブラシ」でこすり落とすことができる。
「小麦粉」は、
粒子が細かいので、
細かいところに入り込みやすく汚れを落としやすい。
含まれる「デンプン」も、
「汚れ」を吸着する効果がある。
Back
「アルカリ性」の「米の研ぎ汁」は「酸性」の「油汚れ」に効果的
 「アルカリ性」の「米の研ぎ汁」は、
「アルカリ性」の「米の研ぎ汁」は、「酸性」の「油汚れ」を掃除するのに効果的。
「油」を「研ぎ汁」が吸収してくれる。
「研ぎ汁」を「油の汚れ落とし」に使うとスムーズ。
「油」が落ちる「受け皿」に、
「お米の研ぎ汁」を入れておくと、
「油汚れ」を吸収してくれて、
洗い物が楽になる。
「重曹」「コーヒーかす」「水溶き片栗粉」も、
「油」を「中和」「吸収」してくれるので、
「米の研ぎ汁」の代わりになる。
Back
「油汚れ」が多い場所は「暖かい季節」に掃除する
付着している軽い「油汚れ」は「キッチンペーパー」で拭き取る
付着している軽い「油汚れ」は、
「キッチンペーパー」で拭き取る。
「キッチンペーパー」は、
「油」の吸着性がとても高いので、
「キッチンペーパー」で拭き取るだけで、
簡単な「油汚れ」は、
簡単に「除去」することができる。
残った頑固な「油汚れ」を
他の方法で集中的に綺麗にするのが効率的。
Back
「キッチンペーパー」で拭き取る。
「キッチンペーパー」は、
「油」の吸着性がとても高いので、
「キッチンペーパー」で拭き取るだけで、
簡単な「油汚れ」は、
簡単に「除去」することができる。
残った頑固な「油汚れ」を
他の方法で集中的に綺麗にするのが効率的。
Back
油汚れには「アルカリ性」洗剤
キッチン掃除は、
家の掃除の中でも、
「油汚れ」が多い場所。
換気扇やコンロなど、
掃除をしにくい場所や、
手間のかかる場所が多い。
キッチンの掃除は、
研くことで、汚れを落とそうとすると、
色々な部分が傷ついてしまうので、
化学反応を利用して、汚れを落とすのが、
最適な方法です。
酸性の「油汚れ」を落とすのに有効なのは、
・アルカリ性の洗剤
・アルコール
などが有効な洗剤です。
アルカリ性の洗剤は、
酸性の「油汚れ」を、中和して落とすことができるので、
酸性の「油汚れ」に使う洗剤として知られています。
アルコールは、
油を溶かす性質を持っているので、
吹きかけては、布で拭き取る
という動作を繰り返すと、
「油汚れ」をスッキリと落とすことができます。
油の量が多いと、かなりのアルコール量が必要です。
「油汚れ」には、「アルカリ性」の洗剤が効果的。
と聞いたことがある人は多いと思います。
油汚れは、「酸性」です。
汚れは、中和して、「中性」の状態にすると、
汚れが良く落ちます。
「酸性」の汚れ
・トイレ --- 「尿はね」「尿石」「水あか」「アンモニア臭」
・浴室 --- 「洗い場の床」「椅子」「洗面器などの水あか」「石けんカス」「鏡の水あか」
・台所 --- 「シンク内の水あか」「石鹸カス」「蛇口や電気ポットの水あか」「魚の生臭さ」
・洗面所 --- 「水あか」「石鹸カス」
・リビング --- 「たばこのニオイ」
などがあり、「アルカリ性」洗剤で、中和しながら汚れを落とします。
「アルカリ性」の汚れは、
・キッチン --- 「換気扇やコンロ」「グリル」「壁の油汚れ」「コンロやグリルの焦げ」「シンクや排水口のぬめり」「野菜くずの悪臭」
・お風呂 --- 「ぬめり」「皮脂汚れ」「湯あか」
・洗濯 --- 「血液などのたんぱく汚れ」「洗濯槽のカビ」
・リビング --- 「手あか」「タバコのヤニ」
などがあり、「酸性」の洗剤で、中和しながら汚れを落とします。
「酸性洗剤」「アルカリ性洗剤」ともに、
素材に影響を与えてしまうので、
素材に影響を与えたくない時や、
なんの汚れかわからない時は、
「中性洗剤」を使用するのが良いです。
「軽い酸性」「軽いアルカリ性」の汚れは、
中性洗剤で十分落とすことができます。
中性洗剤の適している汚れなどは、
・手垢
・ホコリ
・くすみ
・油汚れ
・食品汚れ
などがあります。
アルカリ性の洗剤
・アルカリ性洗剤・重曹
・セスキ炭酸ソーダ
アルカリ性の洗剤は、背面を見ると、
「酸性洗剤」「中性洗剤」「アルカリ性洗剤」
のいずれかかを、必ず記載してくれているので、
洗剤の特性を確認してから利用します。
Back
「重曹溶液」に漬けこんで「油汚れ」を綺麗にする方法
「油汚れ」を中和することができる
アルカリ性成分「重曹」を
水に溶かして「重曹溶液」にすることで、
酷い「油汚れ」も、軽い「油汚れ」も、
「重曹溶液」に「1時間」ほど漬け込むことで、
比較的簡単に綺麗にすることができます。
酷い「油汚れ」の場合は、
「重曹」の量を増やしたり、
複数回「重曹溶液」に漬けこむようにしてください。
「重曹」のアルカリ成分で「中和」できる量は限られています。
長い時間漬けこんでも、
「油汚れ」の量が多いとすべてを「中和」することはできないので、
複数回か、「重曹の量」を増やしてください。
「重曹」を扱う時の注意点。
「重曹」のアルカリ成分は、
人の「皮膚」も溶かします。
ゴム手袋は、必ず着用してください。
素手で行うと、
皮膚が溶け「ヒリヒリ」と傷むことになります。
結構大変なことになるので、
ご注意下さい。
「重曹溶液」を作るには、
換気扇のファンがすっぽり入るぐらいの器を用意して、
「水」と「重曹」の割合は、「100 : 5」ぐらいの割合で、 重曹が溶けるまで、1分ほど混ぜてあげれば完成です。
Back
「重曹」ペーストを塗って「油汚れ」を綺麗にする方法
「油汚れ」が酷い場合は、
「重曹ペースト」を直接塗りつけるのも良い方法です。
手に直接付かないようにゴム手袋は必須です。
「油」が固着して、岩みたいになっていたり、
油汚れがゴムみたいになっている時に、
「重曹ペースト」は有効。
「重曹」が「ペースト状」になるまで、少しずつ「水」を加え、かき混ぜることを繰り返して、
「重曹ペースト」が完成したら、
酷い「油汚れ」部分に塗りつけていきます。
サランラップなどに、ペーストを付けて、
包み込むのも良いと思います。
形状によって、ペーストが密着できる環境づくりが重要。
Back
手の届きにくい場所には「重曹スプレー」
大きすぎる場合や、
細かい場所などで、
「重曹溶液」に漬け込みができない時には、
「水」に「重曹」を溶かした「重曹溶液」をスプレーボトルで吹きかけると、
細かい場所の「油汚れ」も中和分解することができます。
ガスコンロなどに最適。
汚れが酷い場合は、「重曹」の量を増やす。
「重曹溶液」は、「7日」ぐらいで使い切る。
Back
「油汚れ」は「煮沸」でスッキリ
鍋に入るぐらいのものは、
「煮沸」をすると、
「油汚れ」が溶けて、 スッキリと綺麗になります。
「油汚れ」は、
温めると「液化」する習性があるので、
「煮沸」することで、
「油汚れ」を「液化」させ、
一緒に「汚れ」を落としてしまうことができる。
「液化」した「油汚れ」は、
「水」と分離する習性もあるので、
自然と「水面」に浮いてきます。
一緒に、汚れを分離させてくれるので、
とても助かります。
対象物が大きすぎて、
高さが足りない場合は、
ひっくり返すか、
転がすかで対応します。
大きすぎるものは、 「シンク」で熱湯をかけたりして、
対応します。
「浴槽」を使用するのは、
あまりおすすめしません。
「お風呂」の「湯沸し器」に、
「油汚れ」が入り込む可能性があります。
Back
最強クラスの「アルカリ性洗剤」で「油汚れ」を落とす
「油汚れ」は、
「酸性」の「汚れ」なので、
「アルカリ性洗剤」で掃除するのが効果的。
「重曹」は、
「アルカリ性」なので、
「油汚れ」の「洗剤」として知られていますが、
実は、「pH(ペーハー値)」は、「8(弱アルカリ性)」。
「油汚れ」を落とせますが、 それほど強力ではありません。
実は、
家庭には、
さらに強力な「アルカリ性洗剤」があります。
比較的多くの家庭で使われています。
それは、
・カビキラー
・キッチンハイター
です。・キッチンハイター
「pH(ペーハー値)」で、
アルカリ性最大値「pH 13(強アルカリ性)」でもあります。
使用する際は、
「手袋」「マスク」「換気」が必須のアイテムです。
体調に変化が起きるので、
慎重にご使用ください。
どうしても落とせない「油汚れ」などの
「酸性汚れ」にご利用ください。
使用の際は、
あくまで自己責任でお願いします。
Back
「油汚れ」は「キッチンペーパー」で簡単に綺麗になる
「キッチンペーパー」は、
キッチンでは必須のアイテムです。
料理にも使えて、
掃除にも使える、
かなり万能なアイテム。
キッチンの日々の「油汚れ」は、
「キッチンペーパー」で軽く拭くだけで、
かなり綺麗な状態を維持できます。
換気扇周辺の「油汚れ」も、
かなり吸収してくれます。
Back
日々の軽い汚れには「台所用中性洗剤」
日々の軽い汚れには「台所用中性洗剤」
「キッチンコンロ」は、「油汚れ」が主な汚れです。
定期的に「台所用中性洗剤」を
「キッチンペーパー」「スポンジ」「布」
などに付けて、拭き取るだけで、
綺麗になります。
Back
「油汚れ」は「アルコールスプレー」で綺麗にする
「油汚れ」は「アルコールスプレー」で綺麗にする
「アルコール」は、「油」を溶かす性質があるため、
「油汚れ」を綺麗に落とすことができます。
洗剤の種類にも寄りますが、
「油汚れ」なら「アルコール」の方が綺麗になります。 「中性洗剤」は、
「油」を中和できないので、
「アルコール」の方が「油汚れ」を落とせる性質を持っています。
Back
「油汚れ」は「重曹スプレー(アルカリ性洗剤)」で綺麗にする
「油汚れ」は「重曹スプレー(アルカリ性洗剤)」で綺麗にする
「油汚れ」は、「酸性」の汚れなので、
「アルカリ性」の洗剤で「中和」することで、
かなり綺麗にすることができます。
「重曹」は、
比較的強い「アルカリ性」物質なので、
水に溶かしたり、
ペースト状にしたりすることで、
「アルカリ性洗剤」として使用することができます。
Back
「五徳」を綺麗にする方法
「五徳」を綺麗にするには、
・日々の軽い汚れには「台所用中性洗剤」
・頑固な汚れには「つけ置き洗い」
・酷い汚れには「煮沸洗い」
・食器洗浄機に入れて洗う
などの方法があります。・頑固な汚れには「つけ置き洗い」
・酷い汚れには「煮沸洗い」
・食器洗浄機に入れて洗う
掃除が終わった後は、
焦げとサビ防止に「サラダ油」を塗っておくと良いようです。
「ステンレス製五徳」の「変色」には、
専用のクリーナーがあります。
Back
「焦げ付き」には「重曹水」で「煮沸」
「焦げ付き」の汚れは、
「削り落とす」と「傷」がつくので、
できるだけ、
「洗剤」などを利用して、
化学反応で落とすのがおすすめ。
「焦げ付き」は、
「油汚れ」などが多いので、
「酸性」の「汚れ」。
「アルカリ性」成分で綺麗に落とすことができます。
しかし、
「焦げ付き」は、
簡単に落ちてくれません。
「鍋」に、
「重曹」を水に溶かして、
「沸騰」させることで、
「焦げ付き」は落とすことができます。
「キッチンコンロ」は、
「煮沸」で来ませんが、
「五徳」などの付属部品で、
鍋に入るものは、
すべて「重曹」で煮沸してみましょう。
沸騰してから「10分~20分」ほどで、
簡単な「焦げ付き」は落とせるはずです。
Back
「焦げ付き」には「重曹ペースト」
「キッチンコンロ」の「焦げ付き」は、
「煮沸」できないので、 「重曹ペースト」を使用します。
「重曹」に、
少し「水」加えて、
「ペースト状」にしたものを、 「焦げ付き」部分に塗ります。
乾燥しないように、
上から「サランラップ」「ビニール」で覆い、
「重曹ペースト」をズレないように保護します。
後は、
一晩ぐらい放置するだけ。
翌朝には、
「焦げ付き」がふやけ、
簡単に落とすことができるようになっています。
ホームセンターなどで、
「重曹ペースト」のような製品も販売されています。
Back
「しつこい焦げ付き」は傷が付くけど最終兵器は「スチールウール」
本当に汚れが良く落ちる。
「五徳」の「焦げ付き」などにも最適です。
ですが、
細かい「擦り傷」が付きます。
傷が付かない素材かを確認してから利用してください。
「キッチンコンロ」によっては、
「スチールウール」が「NG」のものもあります。
説明書を必ず読んでから。
テフロン加工してあると、
簡単に削り取ってしまうので、
「スチールウール」は絶対に使用しないこと。
「ガスコンロ」の
硬くなった「焦げ付き」が落ちない時などは、
「スチールウール」で優しくこすってあげると、
ほとんどの「焦げ付き」を落とせます。
力を入れすぎると、
素材を簡単に傷つけるので注意。
「スチールウール」は、
「鉄」の細い糸をまとめたものなので、
繊細ですが、強力で、汚れを削り落としてくれます。
「鉄」なので、
強く削り過ぎると、素材を簡単に傷つけます。
使用にはご注意ください。
「スチールウール」の良い点は、
「汚れ」を凄く落としてくれることと、
価格が凄く安いところ。
100円ショップでも購入できるので、
かなりお手軽。
100円なのに、6個ぐらい入っています。
「スチールウール」は、着火剤としても使えます。
着火した後に、酸素濃度が濃くすると、
凄く燃焼します。
空気中でも、地味に燃えるので、
「新聞紙」の下に、「スチールウール」を置き、
その上に、「薪」を組んだら、
比較的簡単に、着火することができます。
「火吹き棒」で酸素を送り込むと、赤く激しく燃焼します。
「スチールウール」を伸ばして、
電池の両端に触れさせても、
着火することができます。
Back
「冷蔵庫掃除」は「水拭き」「乾拭き」が基本
 「冷蔵庫」を「掃除」するときは、
「冷蔵庫」を「掃除」するときは、「水拭き」をしてから、
「乾拭き」するのが「基本」。
「乾拭き」が必須なのは、
「水拭き」の水分が残っていると、
「雑菌」が繁殖し、
「生乾き臭」のような「臭い」が発生することがある。
なので、
「水拭き」の後の「乾拭き」は、必須となっている。
Back
「アルコール」で「拭き掃除」するのが簡単
 「冷蔵庫」を掃除する時に、
「冷蔵庫」を掃除する時に、「アルコール」を使用すると、
「乾拭き」をしなくても良くなる。
「アルコール」は、
「揮発」する時に、「殺菌作用」があるので、
「乾拭き」をしなくても、
「雑菌」などの繁殖がしない。
「冷蔵庫」の「掃除」には、
「アルコール」を使用するのがおすすめ。
Back
「わさび水」で「冷蔵庫」の「カビ予防」
 「冷蔵庫」の「カビ予防」には、
「冷蔵庫」の「カビ予防」には、「わさび」を「水」に溶かした
「わさび水」を使用することもできる。
「わさび」の辛み成分「アリルイソチオシアネート」には、
「抗菌作用」があり、
「カビの防止」に使える。
「冷蔵庫」の中だけでなく、
色々な場所の掃除に使える。
Back
「冷蔵庫」の「臭い」には「重曹」が使える
 「重曹」には、
「重曹」には、「臭い」を抑える効果もあり、
「重曹」を小皿に入れて、
「冷蔵庫」に置いておくだけでも効果がある。
「重曹水」を作り、
「冷蔵庫内」に噴霧して、
綺麗に拭き取るだけで、
「汚れ」「臭い」を抑えることができる。
Back
「炭」で「冷蔵庫内」を「消臭」できる
 「炭」「備長炭」には、
「炭」「備長炭」には、消臭効果があり、
「冷蔵庫内」に入れておくことで、
「消臭」をすることができる。
他にも、
余った「パン」や、
焼きすぎた「パン」は、
「オーブンんトースター」で、
「真っ黒」になるまで焼くことで、
「冷蔵庫」入れて「消臭」に使用することもできる。
Back
「シンク」を「ピカピカ」にするのに使える「アイテム」
「シンク」の「汚れ」を綺麗にするのに、
普段から使用している「アイテム」が使えたりする。
料理ついでに、
残った切れ端などを使って、
「シンク」の掃除をすると効率的。
| アイテム | 説明 |
|---|---|
| 小麦粉 |
細かい「粒子」が、研磨剤のように「シンク」の汚れを落としてくれる。 「スポンジ」などに付け、「シンク」を磨くだけで、 「油汚れ」や「こびりついた汚れ」を吸着してくれる。 簡単に、「ツルツル」な「シンク」になる。 |
| ジャガイモの皮 |
「皮」の内側で拭くと、「デンプン」が汚れを吸着してくれて綺麗になる。 |
| ミカンの皮 |
「ミカンの皮」には、「油」を「中和」する成分が含まれており、 丸めて、拭くことで、「シンク」が綺麗に。 |
| 使用済みの「ラップ」 |
「水垢」「油汚れ」などのこびりついた「汚れ」を落とすことができる。 「荒い汚れ」を落とすのに最適。 |
| 炭酸飲料 |
「炭酸飲料」などの残りでも良いので、 「シンク」をこすると、不思議と「ピカピカ」になる。 「炭酸」が抜けてしまったものでも同じ効果がある。 |
| 大根の切れ端 |
「大根の切れ端」で、「シンク」を磨くと、 「水垢」「ベタつき」が、綺麗に落ちる。 汚れがひどい場合は、 「重曹」「クレンザー」を使うと効果がアップする。 傷の心配が少ないのが良い点。 |
Back
「排水口」の「ヌメリ」を「抑制」する「方法」
「排水口」の「ヌメリ」は、
「アルミ」「銅」を活用すると、
「汚れ」「ヌメリ」の発生を抑制することができる。
| 銅 |
「10円玉」を「排水口」に入れておくと、 「銅」の「殺菌」「防汚」の効果によって、 「ヌメリ」の防止となる。 「10円玉」は、「黒っぽく」なったら交換する時期。 |
| アルミ |
「アルミ」は「水」と反応すると、 「金属イオン」が発生し、 「ヌメリ」の原因となる「バイ菌」を撃退してくれて、 「ヌメリ」が付着しにくくなる。 |
Back
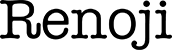
 「キッチン」は、
「キッチン」は、![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2063cdfe.b6c6ceb3.2063cdff.0e01dca2/?me_id=1261122&item_id=10645679&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F506%2F14506.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

 「油汚れ」は、
「油汚れ」は、![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2348041d.e1924cd0.2348041f.8f0a34f8/?me_id=1232650&item_id=10023719&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fra-beans%2Fcabinet%2Fd7%2F1046002.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)