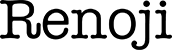旅メモ
旅メモ【日本編】
旅Memo【関東地方編】
旅Memo【茨城県編】
Category
「茨城県」の「基本情報」「茨城県」の「アウトドア」「旅」に役立つ「旅情報」
「茨城県」の「定番スポット」「茨城県」にある「愛犬同伴OK」の「旅スポット」「茨城県」にある「Beach(海水浴場)」「茨城県」にある「キャンプ場」筑波エリア大洗エリア旅Spot
鹿島神宮息栖神社(いきすじんじゃ)大洗サンビーチ海水浴場旅グルメ
「茨城県」の「御当地グルメ」「茨城県」を訪れたら食べたい美味しそうな「飲食店」「茨城県」にある美味しそうな「回転寿司店」「茨城県」にある美味しそうな「焼肉店」御当地レストラン「坂東太郎」旅の宿
「茨城県」にある魅力的な「旅の宿」「茨城県」の「日帰り入浴施設」「茨城県」にある「愛犬」と一緒に宿泊できる「旅の宿」「茨城県」にある「仮眠」「車中泊」ができる「スポット」
【茨城県】鹿島神宮
【茨城県】
鹿島神宮
INDEX
■ はじめに
■ 「鹿島神宮」は「愛犬同伴NG」
■ 「鹿島神宮」は「東国三社」の1つ
■ 「国譲り神話」とは
■ 「鹿島神宮」とは
■ 「鹿島神宮」の「御祭神」
■ 「鹿島神宮」の「歴史」
■ 「鹿島神宮」の「見どころ」
■ 「鹿島神宮」の「祭事」
■ Gallery
はじめに
「鹿島神宮」は、
「香取神宮」「息栖神社」と共に、
「東国三社」と言われる歴史ある「神社」の1つ。
「紀元前660年(神武天皇元年)」に創建されたとされている。
歴史がとても長い「古社」の一つ。
Back
「鹿島神宮」は「愛犬同伴NG」

「鹿島神宮」は、
「愛犬同伴NG」となっていた。
「鹿島神宮」公式WEBにも、
改めて、「愛犬同伴NG」という内容が掲載されていました。
トラブルも発生しているようなので、
「愛犬同伴」での参拝をしないように「ご注意」ください。
「鹿島神宮」公式WEBの「掲載文」
ペット(犬猫等)の境内連れこみ禁止について
令和5年5月2日
鹿島神宮境内は御祭神をお祀りしている場所です。
その境内は清浄が保たれていなければならない場所とされており、元々ペット(犬猫等)の立ち入りを禁止しておりましたが、
昨今、境内にペットをお連れの方と参拝者の方のトラブルが多数発生し、多くのお声を頂くようになりました。
当宮では、御祭神の神域を守り清浄を保つため、また参拝者間のトラブルを避けるため、
アレルギー(犬猫アレルギー)の方の発症を防ぐため、境内へのペット(犬猫等)の連れ込みを禁止致します。
皆さまの御理解と御協力をお願い申し上げます。
※盲導犬・介助犬の同伴は許可致します。
令和5年5月2日
鹿島神宮境内は御祭神をお祀りしている場所です。
その境内は清浄が保たれていなければならない場所とされており、元々ペット(犬猫等)の立ち入りを禁止しておりましたが、
昨今、境内にペットをお連れの方と参拝者の方のトラブルが多数発生し、多くのお声を頂くようになりました。
当宮では、御祭神の神域を守り清浄を保つため、また参拝者間のトラブルを避けるため、
アレルギー(犬猫アレルギー)の方の発症を防ぐため、境内へのペット(犬猫等)の連れ込みを禁止致します。
皆さまの御理解と御協力をお願い申し上げます。
※盲導犬・介助犬の同伴は許可致します。
Back
「鹿島神宮」は「東国三社」の1つ

「鹿島神宮」は、
「日本神話」の時代から続く、
「長い歴史」「深い信仰」に支えられた、日本を代表する「神社」の一つ。
「鹿島神宮」は、
「香取神宮(千葉県香取市)」「息栖神社(茨城県神栖市)」と共に、
「東国三社」の1つにもなっている。
東国三社
「東国三社」の「3つの神社」は、
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、活躍した「神々」を祀っていて、
古くから人々の信仰を集めてきた。
「日本神話」における、
「国譲り」の際に活躍した
・武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)(鹿島神宮): 鹿島神宮の主神で、国譲りの際に大国主神を従わせた神として登場します。 ・経津主大神(フツヌシノカミ)(香取神宮): 香取神宮の主神で、武甕槌大神とともに国譲りに参加した神です。 に加え、
「土地」を開拓したといわれる「岐神(クシノカミ)」
・岐神(クシノカミ)(息栖神社): 息栖神社の主神で、国土を開拓した神として伝えられています。 を祀っている。
東国三社(鹿島神宮、香取神宮、息栖神社)は、国譲り神話に深く関わっています。 武甕槌大神(タケミカヅチノカミ): 鹿島神宮の主神で、国譲りの際に大国主神を従わせた神として登場します。 経津主大神(フツヌシノカミ): 香取神宮の主神で、武甕槌大神とともに国譲りに参加した神です。 岐神(クシノカミ): 息栖神社の主神で、国土を開拓した神として伝えられています。
古くから「関東地方の総鎮守」として崇敬されてきた。
「三重県伊勢市」にある最初の神宮「伊勢神宮」に匹敵するほどの信仰を集めていたと言われている。
「江戸時代」には、「お伊勢参りのみそぎ参り」と言われ、
「伊勢神宮」の参拝後に、「東国三社」を参拝することが一般的だった。
「東国三社」は、
「パワースポット」としても有名で、
「東国三社」の「各神社」は、それぞれ「強い霊力」を持つ「パワースポット」としても知られている。
「東国三社」の特徴
| 神社名 | 特徴 |
|---|---|
| 鹿島神宮 |
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、 活躍した「武甕槌大神」を祀っていて、 「勝負の神様」として知られている。 「力強いエネルギー」を感じられる「パワースポット」。 「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、 「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、 「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。 「力」と「勇猛さ」を象徴する神。「武力」で相手を圧倒する。 「武甕槌大神」が、「力」によって「国」を平定した。 |
| 香取神宮 |
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、 活躍した「経津主大神」を祀り、 「学業成就」「交通安全」の「神様」として信仰されている。 静かで厳かな雰囲気の神社。 「経津主大神(フツヌシノカミ)」は、 「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」と共に、 「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、 「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。 「知恵」と「策略」を象徴する神。「巧みな言葉」や「仕掛け」で相手を説得する。 「経津主大神」は、「知恵」と「策略」によって「国譲り」を成功させた。 |
| 息栖神社 |
「土地」を開拓したといわれる「岐神(クシノカミ)」を祀り、 「土地の神様」として崇敬されている。 古くからの歴史と神秘的な雰囲気が魅力。 「岐神(クシノカミ)」は、 「日本神話」において、土地を開拓し、人々に農耕を教えたとされる神様。 「国譲り神話」には、活躍が記載されていないが、日本の国土形成に大きく貢献した神。 荒れ果てた土地を開墾した「土地の開拓」、 人々に農耕の方法を教え、食料の自給自足を実現させた「農耕の指導」、 様々な「文化」「技術」を伝えた「文化の伝承」 などの実績があったそう。 |
Back
「国譲り神話」とは

「国譲り神話」は、
日本の古代神話「日本神話」において、
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を中心とする「高天原(たかまがはら)の神々」が、
「地上」を治めていた「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に「国を譲る物語」。
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を中心とする
「高天原(たかまがはら)の神々」が、
「天照大御神」の子「邇邇藝命(ニニギノミコト)」が、
「高天原」から地上へ降り、「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」よう要求した。
この時に、
「鹿島神宮」「香取神宮」の「御祭神」である
「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」と「経津主大神(フツヌシノカミ)」が、
「使者」の中心的な1人として、それぞれ活躍した。
「大国主神(おおくにぬしのかみ)」は、
最初は抵抗するも、最終的に、
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」の意向を受け入れ、「国を譲る」ことを決意する。
「島根県出雲市」にある「出雲大社」は、
国を譲った「大国主神(おおくにぬしのかみ)」を祀るために、
「創建」された「神社」で、
格式の高い神社であり、「縁結び」の御利益がある神社として、
「出雲大社」は知られている。
「国譲り神話」の持つ意味は、
「天照大御神」の「子孫」である「天皇」が、
「日本の統治者」となる「正当性」を示すために用いられている。
「天照大御神」を中心とした「高天原の神々」と、
「大国主神」を中心とした「出雲の国神々」を統合し、
「一つの国家」としての「日本」を形成する物語として位置づけられている。
「地方を治めていた神々」と、「中央を治める神々」との関係を示し、
「中央集権的な国家形成のプロセス」を神話的に表現している。
「国譲り神話」は、
日本の歴史と文化を理解する上で非常に重要な神話。
「国譲り神話」を通じて、
「日本の神々」「古代の人々の信仰」「国家形成の過程」など、
より深く知ることができるようになっている。
Back
「鹿島神宮」とは

「茨城県鹿嶋市」に鎮座する「鹿島神宮」は、
全国に点在する「鹿島神社」の「総本社」。
「日本神話」に登場する「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を祀る
古くから存在する神社「古社」。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
日本神話において「国譲り」の際に活躍し、日本の国土を平定したとされる「神様」。
「神武天皇」の「東征」の際に、
「神武天皇」を助け、その「神恩」に報いるために、
「紀元前660年(神武天皇元年)」に、
「鹿島神宮」が創建されたと伝えられている。
歴史が古く、
「奈良時代」の「713年(和銅6年)」に編纂(へんさん)が開始され、
「721年(養老5年)」頃に完成したとされる
「約1300年前」の古書「常陸国風土記」に、「鹿島神宮」の名前が記されており、
古くから信仰を集めていることが知られている。
「常陸国風土記」は、
「常陸国(現在の茨城県の大部分)」の「地理」「歴史」「伝説」などをまとめた「地方誌」。
Back
「鹿島神宮」の「御祭神」

「鹿島神宮」の「御祭神」は、
「日本神話」に登場する「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
日本神話において「国譲り」の際に活躍し、日本の国土を平定したとされる「神様」。
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、
活躍した御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「勝負の神様」として知られている。
「力強いエネルギー」を感じられる「パワースポット」。
「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、
「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。
「力」と「勇猛さ」を象徴する神。「武力」で相手を圧倒する。
「武甕槌大神」が、「力」によって「国」を平定した。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「天照大御神」の子孫にあたる日本最初の「天皇」である
「神武天皇」の「東征」を行っている時に、
「神武天皇」を助けた功績などを残していた。
その「神恩」に報いるために、
「紀元前660年(神武天皇元年)」に、
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を祀る
「鹿島神宮」が創建されたと伝えられている。
Back
「鹿島神宮」の「歴史」

「鹿島神宮」の「創建」は、
「紀元前660年(神武天皇元年)」で、
創建され多のは、
「神武天皇」の「東征」の際にも、
「神武天皇」を助け、その「神恩」に報いるためと言われている。
「古代~中世」になると、
「朝廷」から「蝦夷の平定神」として、また「藤原氏」から「氏神」として崇敬された。
「平安時代」には、
朝廷の重要な祭事が行われたり、「国家的な神社」としての地位を確立していた。
「江戸時代」になると、
「徳川家康」をはじめとする「武家」からの信仰も厚く、
「社格」は、「官幣大社」に昇格した。
「近代」以降でも、
「明治維新後」には、その「格式」は保たれ、
現在では、「神社本庁」の「別表神社」に指定されている。
Back
「鹿島神宮」の「見どころ」

「鹿島神宮」の「見どころ」には、
下記のような施設がある。
| 施設 | 説明 |
|---|---|
| 本殿 | 三間社流造の美しい本殿は、国の重要文化財に指定されている。 |
| 拝殿 | 朱塗りの鮮やかな拝殿は、荘厳な雰囲気を醸し出している。 |
| 神苑 | 広大な神苑には、様々な種類の樹木が生い茂り、四季折々の美しい風景を楽しむことができる。 |
| 宝物館 | 国宝や重要文化財をはじめとする貴重な宝物の数々を収蔵している。 |
Back
「鹿島神宮」の「祭事」

「鹿島神宮」で、「年間」を通して行われる「祭事」には、
下記のような「祭事」がある。
「鹿島神宮」の「祭事」一覧
| 祭事 | 内容 |
|---|---|
| 御船祭 | 「12年」に一度行われる大祭で、神輿が海を渡る様子は圧巻。 |
| 白馬祭 | 「1月7日」に行われる神事で、白い馬が神前に奉納される。 |
| 祭頭祭 | 「3月9日」に行われる神事で、一年の無病息災を祈願。 |
Back