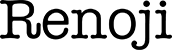旅メモ
旅メモ【日本編】
旅Memo【関西地方編】
旅Memo【兵庫県編】
Category
「兵庫県」の「基本情報」旅Info
「兵庫県」の「定番スポット」「兵庫県」にある「愛犬同伴OK」の「旅スポット」旅に役立つ「旅情報」【エリア別編】
神戸エリア神戸 有馬温泉エリア淡路島エリア姫路エリア旅Spot
世界遺産「姫路城」伊弉諾神宮道の駅「うずしお」旅グルメ
「兵庫県」を訪れたら食べたい美味しそうな「御当地グルメ」「兵庫県」にある美味しそうな「回転寿司店」「兵庫県」にある美味しそうな「焼肉店」旅の宿
「兵庫県」にある魅力的な「旅の宿」「兵庫県」の「日帰り入浴施設」「兵庫県」にある「愛犬」と一緒に宿泊できる「旅の宿」「兵庫県」にある「仮眠」「車中泊」ができる「スポット」
【兵庫県】「国生み」の大業を成し遂げた「伊弉諾大神」を祀る「伊弉諾神宮」
【兵庫県】
「国生み」の大業を成し遂げた「伊弉諾大神」を祀る「伊弉諾神宮」
INDEX
■ はじめに
■ 「伊弉諾神宮」は「愛犬同伴OK」
■ 「伊弉諾神宮」とは
■ 「国生み神話」とは
■ 「日本」のある「土地」が形成された「順番」
■ 「伊弉諾神宮」の御祭神「伊弉諾大神」は「天照大御神(あまてらすおおかみ)」の「親」
■ 「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が「天照大御神(あまてらすおおかみ)」に国家統治の大権を譲った理由
■ 「伊弉諾神宮」に「縁結び」「夫婦円満」の御利益がある理由
■ 「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が死んだ理由
■ 「「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が生んだ「神々」
■ 「おのころ島神社」は「愛犬同伴OK」
■ 「おのころ島神社」とは
■ 「南あわじ市」にある、もう一つの「おのころ島神社」
■ 「伊弉諾神宮」には「無料駐車場」がある
■ 「伊弉諾神宮」への「地図」
■ 「おのころ島神社」には「無量駐車場」が完備されている
■ 「おのころ島神社」への「地図」
■ 「伊弉諾神宮」周辺の「旅スポット」
■ Gallery
はじめに
 *Image is 伊弉諾神宮
*Image is 伊弉諾神宮
Address : 〒656-1521 兵庫県淡路市多賀740
国家統治の大権を御子神「天照大御神」に委譲され、国生みの神功を果たされた「伊弉諾大神」が、淡路島多賀の地に幽宮(かくりのみや)を構え余生を過ごした「幽宮」の旧跡。日本最古の神社。約1万5000坪の広大な境内。
「国生み」の大業をなされた
「伊弉諾大神」を祀っている日本最古の神社「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」。
「国生み」の舞台となった「淡路島」。
「伊弉諾神宮」は、
日本の国土を造ったとされる「伊弉諾大神」が、
余生を過ごした住居跡に建てられた神社。
詳しくは、
下記をご覧ください。
Back
「伊弉諾神宮」は「愛犬同伴OK」

「伊弉諾神宮」は、「愛犬同伴OK」。
「伊弉諾神宮」は、 「愛犬」を連れて、参拝することが可能となっていました。
「境内」の中も、
「リード」で歩かせることもできるそうです。
ですが、
「日本」の中でも、
かなり神聖な場所とされているので、
「スリング」「キャリーバッグ」などを利用する方が、マナーかと思います。
長く愛犬と一緒に参拝が続けられるように、
「おしっこ」「うんち」などはさせないように、
気を付ける必要があるかと。
「おのころ島神社」は「愛犬同伴OK」
「おのころ島神社」は、「愛犬同伴OK」でした。鳥居をくぐって、
「社務所」があるので、確認したところ「愛犬同伴OK」とのことでした。
「キャリーバッグ」に入れ、
他の参拝者の迷惑にならないようにすれば、
一緒に参拝できます。
階段を上った所に、「お社」があるので、
「ペットカート」は無理だ。
島の周囲を歩ける歩道がありました。
愛犬と一緒に散策できるので、
参拝の前後に、お散歩してあげると良いと思います。
駐車場の周辺も、
比較的、散歩がしやすいので、
「おしっこ」などは、境内から離れたところで、
させるようにした方が良いと思います。
Back
「伊弉諾神宮」とは

「兵庫県淡路島」にある
「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」は、
国生みの神功を果たされた「伊弉諾大神」が、
余生を過ごした「幽宮」だった場所に建てられた「神社」。
「日本最古の神社」で、
「敷地面積」は、「約1万5000坪」という広大な広さの「境内」を持つ。
国生みの神功を果たされた「伊弉諾大神」は、
共に国生みの神功を果たされた
「妻」である「伊弉冉尊(イザナミ)」の死などにより、
最後に生み残した「三貴神」である
「天照大御神(あまてらすおおかみ)」「月読尊(つきよみのみこと)」「須佐之男命(すさのおのみこと)」のうち、
国家統治の大権を御子神「天照大御神」へと委譲した。
そして、
最初にお生みになられた「淡路島多賀」の地に、
「幽宮(かくりのみや)」を構え余生を過ごした。
その「伊弉諾大神」が過ごした「幽宮(かくりのみや)」の場所が、
のちに「御神陵」が建てられ「聖地」とされ、「神社」が創始された。
そして、
「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」となって、現在に至っている。
「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」に祀られている
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の二柱。
「伊弉諾大神」は、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」のこと。
地元では、
「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」を「いっくさん」という愛称で呼び、親しまれている。
他にも、
「日之少宮」「淡路島神」「多賀明神」「津名明神」
という愛称も使用され、崇められている。
明治時代に、御陵地を整地し、
御陵を中心に、神域の周囲に「濛」が巡らされた。
正面の「神池」や、背後の湿地は、この周濛の遺構とされている。
「建物」や「工作物」は、
大部分が、「明治九年から同二十一年」に、「官費」で造営されたもの。
「境内面積」は、「約1万5000坪」。
江戸時代あたりでは、更に広い敷地が「神域」として、
禁足の地とされていたそう。
Back
「国生み神話」とは

日本という国ができるはるか前の、
日本列島になる地上ができる時のお話が「国生み神話」。
「天地」が始まる頃に、
神々が住む「高天原(たかまがはら、たかあまはら、たかあまのはら、たかのあまはら、たかまのはら)」が、
澄み渡った高い空の上にあったと言われている。。
「高天原」には、
「天御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」という「お三方の神さま」が御出現したそう。
その後、
日本のあたりが、ただの「海」だった時代に、
「高天原に住む神々」が、
「下界」に新たな「国」を造ることを決定し、
「伊邪那岐命(イザナギのミコト)=伊弉諾命」「伊邪那美命(イザナミのミコト)=伊弉冉命」の二柱の神様に、
下界での「国作り」を命じられ、「天の沼矛(あまのぬぼこ)」という「矛」を授けたそうです。
命を受けた「伊邪那岐命」「伊邪那美命」は、
「高天原」にある「天の浮橋」から、下界を眺めていた時に、
「天の沼矛」を海水に差し降ろし、かき混ぜたところ、
「天の沼矛」から落ちた潮が、積り固まり、
「於能凝呂島(おのころじま)」ができたそう。
現在の「おのころ島神社」の場所と言われている。
他にも、「於能凝呂島(おのころじま)」だったとされる候補地はあるが、
「おのころ島神社」の場所が、最有力とされているらしい。
「伊邪那岐命」「伊邪那美命」は、
「おのころ島」に降り立ち、
大きな柱「天の御柱(あまのみばしら)」を建てた。
「天の御柱(あまのみばしら)」の周りを、
「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)」は左から、
「伊邪那美命(いざなみのみこと)」は右から、
廻りあったところ、
「男女」としての恋心が生まれたとのこと。
「伊邪那岐命」「伊邪那美命」は、
「おのころ島」で生活をはじめ、
多くの「神々」を産み、島々を形成したとのこと。
最初に、「淡路島」、
次いで、「四国」「隠岐島」「九州」「壱岐島」「対島」「佐渡島」を、
最後に「本州」を生み出した。
「八つの島」が形成されたことから、「大八島国」と言われている。
島々ができると、
「伊邪那岐命」「伊邪那美命」との間には、
多くの神様が生まれたそう。
その一人に、
太陽を神格化した「伊勢神宮」の御祭神「天照大御神」もいらっしゃる。
「伊邪那岐命」「伊邪那美命」は、
「天照大御神」の「親(親神様)」でもある。
ここから「日本」の多くの神話が生まれてくる。
日本神話の一つ「天の岩戸」も、
「天照大御神」のエピソードの一つ。
「おのころ島神社」は、
「日本の始まりの地」として崇敬されている。
「おのころ島神社」は、「伊弉諾神宮」から程近い場所にある。
Back
「日本」のある「土地」が形成された「順番」
「伊弉諾神宮」の御祭神「伊弉諾大神」は「天照大御神(あまてらすおおかみ)」の「親」

「伊弉諾神宮」の御祭神として祀られている 「伊弉諾大神」こと「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」は、
日本の「皇室の祖先神」とされる太陽の神「天照大御神(あまてらすおおかみ)」の「親」。
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が、
最後に生んだ3人の神「三貴神」が、
・天照大御神(あまてらすおおかみ)
・月読尊(つきよみのみこと)
・須佐之男命(すさのおのみこと)
の「3神」。
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の子供、
つまり「息子」「娘」にあたる存在となる。
太陽の神「天照大御神(あまてらすおおかみ)」は、
その前に、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
多くの神を生んでいた。
「三貴神」より前に生まれた「神々」は、
「具体的な場所」や「自然現象」を司る「神々」であると同時に、「抽象的な概念」を表す存在でもあるため、
「三貴神」とは、異なり、兄弟関係にはないそう。
最後に生んだ3人の神「三貴神」は、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が、
「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を追いかけていった「黄泉の国」から戻った後に、
「禊」をした際に、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の身体から生まれたとされている。
「天照大御神(あまてらすおおかみ)」は、「左目」から、
「月読尊(つきよみのみこと)」は、「右目」から、
「須佐之男命(すさのおのみこと)」は、「鼻」から生まれたと伝えられている。
「アマテラス」は、「太陽の神」として高天原を治め、
「ツクヨミ」は、「月の神」、
「スサノオ」は、「海の神」
としてそれぞれ異なる領域を司った。
「三貴神」より前に生まれた「神々」
| 神 | 特徴 |
|---|---|
| 国土を司る神々 | |
| 大八島国之神 | 八つの島々を司る神 |
| 大戸之神 | 国の戸を守る神 |
| 大屋戸之神 | 国の屋根を守る神 |
| 自然現象を司る神々 | |
| 風神 | 風を司る神 |
| 雷神 | 雷を司る神 |
| 山神 | 山を司る神 |
| 海神 | 海を司る神 |
| その他 | |
| 高天原神 | 高天原を司る神 |
| 国之常立神 | 国の常世(とこよ)を司る神 |
Back
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が「天照大御神(あまてらすおおかみ)」に国家統治の大権を譲った理由

「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
「夫婦」となり、
「国造り」の大役を成し遂げていたが、
ある日、 「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が、
太陽の神「天照大御神(あまてらすおおかみ)」に、国家統治の大権を譲ったのは、
夫婦となり、
協力して、「国造り」の大役をになっていた
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が、
「火の神」を生んだ時に、大きなヤケドを負って、死んでしまったところから始まる。
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」 愛する妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を連れ戻そうと、
「黄泉の国(死後の世界)」まで行ったが、
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の変貌ぶりに、泣く泣く1人で戻った。
その時の精神的なショックから、
「国家統治の大権」を担うことができないと判断した為、
余生を1人で過ごすために、 太陽の神「天照大御神(あまてらすおおかみ)」に、
「国家統治の大権」を授けたとされている。
太陽の神「天照大御神(あまてらすおおかみ)」は、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が、
最後に生んだ3人の神「三貴神」の1人。
3人の神「三貴神」は、
・天照大御神(あまてらすおおかみ)
・月読尊(つきよみのみこと)
・須佐之男命(すさのおのみこと)
の「3神」。
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が、
「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を追いかけていった「黄泉の国」から戻った後に、
「禊」をした際に、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の身体から生まれたとされている。
「天照大御神(あまてらすおおかみ)」は、「左目」から、
「月読尊(つきよみのみこと)」は、「右目」から、
「須佐之男命(すさのおのみこと)」は、「鼻」から生まれたと伝えられている。
Back
「伊弉諾神宮」に「縁結び」「夫婦円満」の御利益がある理由

「伊弉諾神宮」には、
「縁結び」「夫婦円満」の御利益があると言われている。
夫婦だった 「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を祀っていることも1つの理由。
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
「夫婦」という関係性の「起源」にもなっていて、
全ての「縁の始まり」を象徴している都も言われている。
「国造り」の大業の中、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が、
「おのころ島」に降り立った時に、
大きな柱「天の御柱(あまのみばしら)」を建て、 「天の御柱(あまのみばしら)」の周りを、
「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)」は左から、
「伊邪那美命(いざなみのみこと)」は右から、
廻りあったところ、
「男女」としての恋心が生まれたとのこと。
「国造り」の途中で、
「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が、
「火の神」を生むときに、大ヤケドを負い、亡くなってしまった時も、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」は、
愛する妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を連れ戻すために、
「黄泉の国」まで行ったそう。
「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」を連れ戻すことができなかったが、
「夫婦愛」の強さを象徴するエピソードとなっている。
それらのエピソードなどから、
「伊弉諾神宮」は、
「縁結び」「夫婦円満」の御利益があると言われている。
境内には、
「樹齢約900年」の「夫婦大楠」と呼ばれる「クスノキ」がある。
「二つの樹」が、根元で一体となったこの「大楠」は、
「夫婦の絆」の象徴として人々に親しまれていて、
「夫婦円満」「安産子授」「縁結び」のご利益があるとされている。
Back
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が死んだ理由

「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
火の神「カグツチ」を生んだ時に、
その火によって、「身体」を焼かれてしまい、
その傷が原因で亡くなった。
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の死は、
この世に「死」が生まれたことを意味する。
それまで、「神々」は、「永遠」の存在だったが、
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の死によって、
「神々」も、「死」を迎える存在となった。
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の「死」は、
単に、1人の神が亡くなったという出来事だけではなく、
「日本神話の世界観」を形成するのに、大きな意味を持った。
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の死後、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」は、
悲しみから、様々な神を生み出した。
| 神の名前 | 特徴 |
|---|---|
| 泣沢女神 | 涙から生まれた神「泣沢女神」。 |
| 武御雷神 | 怒りから生まれた神「武御雷神」。 |
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の「死の原因」となった
火の神「カグツチ」は、
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」により殺されてしまう。
それが、
後の「日本神話」の中で、
火の神「カグツチ」の子供たちとの間に、深い因縁が生まれ、
大きな影響を与えることになる。
Back
「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が生んだ「神々」

「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」と「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は、
「日本神話」において、「国生み」と「神生み」を行った「夫婦神」で
数多くの「神々」を生み出した。
「国生み」で生まれたもの
| 総称 | 説明 |
|---|---|
| おのころ島 | 大きくして今の「淡路島」かも。。 |
| 淡路島 | 「おのころ島」を大きくしたのかも。。。。 |
| 四国 | |
| 隠岐島 | |
| 九州 | |
| 壱岐島 | |
| 対馬 | |
| 佐渡島 | |
| 本州 | 日本列島を構成する島々 |
| その他の島々 | 数え切れないほどの島々が生まれた |
「神生み」で生まれた主な神々
造化三神
「造化三神」は、天地開闢の際に、最初に生まれた「神々」で、宇宙の創造に関わったと考えられている。
| 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) | 宇宙の創造主 |
| 高御産巣日神(タカミムスビノカミ) | 高天原を司る神 |
| 神産巣日神(カムムスビノカミ) | 産業を司る神 |
妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の死
| 火の神「カグツチ」 | 妻「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」が産んだ際に、その火によって「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」は命を落とす。 |
三貴神
「三貴神」は、「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」の身体から、最後に生まれた神々で、「太陽」「月」「海」を司る重要な「神々」。
| 天照大御神(アマテラスオオミカミ) | 「太陽神」であり、日本の国家神道において「最高位の女神」 |
| 月読尊(ツクヨミノミコト) | 月の神 |
| 須佐之男命(スサノオノミコト) | 海の神であり、暴れ者としても知られている |
その他の神々
| 風神 | 「風」の神 |
| 雷神 | 「雷」の神 |
| 山神 | 「山」の神 |
| 海神 | 「海」の神 |
| 泣沢女神 | 涙から生まれた神「泣沢女神」。 |
| 武御雷神 | 怒りから生まれた神「武御雷神」。 |
Back
「おのころ島神社」とは

「自凝島神社(おのころじまじんじゃ)」は、
「兵庫県南あわじ市(旧三原町)」にある神社。
「おのころ島神社」と表記されることが多い。
「おのころ島」は、
漢字で書くと「自凝島」と表記する。
「おのころ島」が出来た時に、「自ずと凝り固まって島が出来た」ことから、
「自凝島」という名前になったと言われている。
「おのころ島神社」は、
「国生み神話」の中で、1番最初に作られた土地「おのころ島」として知られる場所にある神社で、
「国生み」の「聖地」となっている。
「伊弉諾命」「伊弉冉命」による「国生み」の歴史舞台として、
神聖な場所として崇敬されている。
「古事記」「日本書紀」によると、
「伊弉諾命」「伊弉冉命」は、
「天の浮橋」にお立ちになり、天の沼矛(あまのぬぼこ)を持って海原をかき回すと、
滴る潮が、凝り固まり、「島」を形成したと言われている。
その時に出来た島が、「自凝島(おのころ島)」と記されている。
「おのころ島神社」が「鎮座」する「丘」が、
「伊弉諾命」「伊弉冉命」両神による
「国産み」「神産み」の舞台となった「自凝島(おのころじま)」であると伝えられている。
「伊弉諾命」「伊弉冉命」の二神は、
「おのころ島」に降り立ち、
「八尋殿(やひろでん)」を建て、
最初に「淡路島」を造り、
次々と、現在の日本列島の始まりとなる「大八洲(おおやしま)」を
形成したと記されているそう。
「淡路島」の次に、
「四国」「隠岐島」「九州」「壱岐島」「対島」「佐渡島」を生み出し、
最後に「本州」を生んだそう。
「おのころ島神社」には、
「伊弉諾命」「伊弉冉命」の二神が祀られており、
「縁結び」「安産」の神として、親しまれている。
「伊弉諾命」「伊弉冉命」の「二神」は、
「天照大御神」の「親神」。
最後に生み残した「三貴神」は、
・天照大御神(あまてらすおおかみ)
・月読尊(つきよみのみこと)
・須佐之男命(すさのおのみこと)
の「3神」。
昭和57年3月に建立され、
「高さ:21.7m」の朱塗りの「大鳥居」がランドマークとなっている。
この鳥居は、「平安神宮」「厳島神社」と並び、
「日本三大鳥居」の一つに数えられている。
御祭神は、
・伊弉諾命(イザナギのミコト)
・伊弉冉命(イザナミのミコト)
の二柱(二神)を「主祭神」とし、
「菊理媛命(キクリヒメのミコト)」を「合祀」している。
「菊理媛命(キクリヒメノミコト)」は、
「伊弉諾命」「伊弉冉命」が喧嘩をした際に、
仲を取り持った事から「縁結び」の神様と慕われるようになったそう。
この「三神」が祀られていることから、強力な「縁結び」のパワースポットとしても人気があるそう。
Back
「南あわじ市」にある、もう一つの「おのころ島神社」
「おのころ島」の場所には、「2説」ある。
そして、
淡路島には、自凝神社という神社が複数存在する。
その中でも、「南あわじ市」の「自凝神社(おのころ神社)」が、
古くから「おのころ島」の聖地として崇められてきた。
もう一つの有力説は、
同じ「南あわじ市」の南の海に浮かぶ「沼島」にある
もう一つの「自凝神社(おのころじんじゃ)」。
現在のところ、「国生み神話」の「おのころ島」は、
2説が有力説といわれており、このどちらかが「おのころ島」と言われている。
「おのころ神社(沼島)」には、
「土生(はぶ)港」より船に乗り沼島漁港へ渡り、
船着場から「徒歩:約10分」で辿り着ける。
Back
そして、
淡路島には、自凝神社という神社が複数存在する。
その中でも、「南あわじ市」の「自凝神社(おのころ神社)」が、
古くから「おのころ島」の聖地として崇められてきた。
もう一つの有力説は、
同じ「南あわじ市」の南の海に浮かぶ「沼島」にある
もう一つの「自凝神社(おのころじんじゃ)」。
現在のところ、「国生み神話」の「おのころ島」は、
2説が有力説といわれており、このどちらかが「おのころ島」と言われている。
「おのころ神社(沼島)」には、
「土生(はぶ)港」より船に乗り沼島漁港へ渡り、
船着場から「徒歩:約10分」で辿り着ける。
Back
「伊弉諾神宮」には「無料駐車場」がある
「伊弉諾神宮」には、「参拝者用」の「無料駐車場」が用意されていて、
「大鳥居」のある交差点を曲がって、
少し入ったところに、「無料駐車場の入口」がある。
駐車場内には、区分ラインもなかったので、
互いに気遣って、車を駐車するスタイルだった。
Back
「伊弉諾神宮」への「地図」
「伊弉諾神宮」へは、
「津名一宮IC」で高速を降りて、
車で20分ほどの「西北」の方向にある。
「伊弉諾神宮」の周辺には、
「バス停」もあった。
調べてみたら、
「神戸」の「三宮」にある「神戸三宮BT」から
「伊弉諾神宮」で下車できる「バス」があるそう。
「神戸三宮BT」から「伊弉諾神宮」までの
バスに乗っている時間は、「1時間10分」ほどらしい。
Back
「おのころ島神社」には「無量駐車場」が完備されている
「おのころ島神社」には、
「参拝者用」の「無料駐車場」が用意されていました。
「10台」ほどが駐車できるようになっていましたが、
もう少し駐車で着そうなスペースの取り方をしていたので、
広々としている感じがした駐車場。
「おのころ島神社駐車場第2」という「駐車場」もあって、
こちらは、「大鳥居」の正面にある「駐車場」。
大型バスがメインの駐車場で、
こちらも広々としていて、普通車は「12台」ほど駐車できるようでした。
駐車場の所に、「バス停」もあった。
Back
「おのころ島神社」への「地図」
「車」だと「西淡三原IC」で降りて、
「東」の方向に進むとあるが、
大きな道路があまりなく、
地元道を走っていくと、「おのころ島神社」に辿り着く感じ。
「おのころ島神社」の周辺には、
「お店」「飲食店」「商業施設」などはない。
「畑」が多いエリアにある感じ。
「淡路島」には、「電車」がないらしく、
訪れるには、「バス」「タクシー」を使ってアクセスするしかないようです。
「伊弉諾神宮」からは、
直線距離で、「約18km」ほど。
「バス」を乗り継いで訪れることができるらしい。
一番便利なのは、「レンタカー」が良いみたいです。
「バス」は運行時間・運行本数が限られていて、
「タクシー」もバス停によっては、見つからず、
タクシー会社に連絡して派遣してもらうスタイルのようです。
料金的にも、
「バス」「タクシー」を使うと、往復で「一人5000円」ほどかかるようです。
自由に旅するには、「レンタカー」が良いかもしれません。
Back
「伊弉諾神宮」周辺の「旅スポット」
淡路市
Address : 〒656-1521 兵庫県淡路市多賀740
御子神「天照大御神」の「親神」である「伊弉諾大神」。「国生み」の神功を果たされた後に、「国家統治」の大権を御子神「天照大御神」に委譲され、淡路島多賀の地に幽宮(かくりのみや)を構え余生を過ごした「幽宮」の旧跡。日本最古の神社。約1万5000坪の広大な境内。
南あわじ市
Address : 〒656-0423 兵庫県南あわじ市榎列下幡多415
「自凝島神社(おのころじまじんじゃ)」は、「国生み神話伝承地」となっていて、国生み神話の舞台「おのころ島」ゆかりの神社。昔は、御原入江の中にあって「おのころ島」と呼ばれていた場所。国生み神話では、最初の島として知られる。「古事記」で「イザナギ」と「イザナミ」の「国生みの聖地」とされる丘に建つ神社。「おのころ島神社」の大鳥居は、「平安神宮」「厳島神社」と並び「日本三大鳥居」の一つ。
Address : ジョイポート南淡路 〒656-0501 兵庫県南あわじ市福良港 うずしおドームなないろ館
淡路と四国の間にある幅約1.3kmの激しい潮流が特徴で、世界最大級の渦潮が発生している海峡「鳴門海峡」。
神戸市
Back