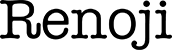Life
美容 & 健康
ボディケア
自分の「能力」を最大限に発揮する方法「集中力」を高める方法「身体」がムズムズして落ち着かない時の解消方法「健康寿命」を伸ばす方法「体の老化」を抑制する方法身体の「老廃物の排出(デトックス)」をする方法「むくみ」を解消する方法「身体の疲れ」を除去する方法「自律神経」を整える方法「筋肉痛」を解消する方法「化膿」「炎症」しやすい「体質」の「改善方法」「身体」を「アルカリ性」に保つ方法「眠気」を覚ます方法「質の良い睡眠」をとる方法効率的に「ダイエット」をする方法体のしくみ
「尿」の役割部位
「肩こり」を解消する方法「目」をスッキリとさせる方法「脳」を使いこなす方法「綺麗」な「指」を手にいれる方法「鼻づまり」を「解消」する方法家庭の医学(治療方法)
「風邪(かぜ)」の「治し方」「喉の痛み」を治す豆知識皮膚にできた「イボ」の治し方「痛風」の「正体」と「痛み」を「解消」「治療」する方法「ガン(癌)」を「予防」する方法季節
「冷え性」を解決する方法「暑い夏」に効率的に「身体」を冷やす方法
【健康】「風邪(かぜ)」の「治し方」
【健康】
「風邪(かぜ)」の「治し方」
「風邪(かぜ)」の「治し方」
INDEX
はじめに
「風邪」を早く治す豆知識をまとめています。
「風邪」は、
地味に厄介。
寝込むほどでもなかったり、
凄く喉が痛かったりと。。。。。
何が原因かわからずに、 熱が出て、
辛い思いをすることが多いのが「風邪」。
「風邪」が酷くなったら、
病院に行った方が良いですが、
ちょこっとの不調であれば、
家で治したいのが本音。
家庭でもできる「風邪対策」をまとめてみました。
詳しくは、
下記をご参照ください。
Back
「風邪」を「治す」のに「効果的な方法」
「風邪」を「治す」のに「効果的な方法」には、
「ビタミンC」を多く「摂取」することや、
「お風呂に入らない」など、
色々と言われてきましたが、
研究が進むと、
「ビタミンC」ではなく、
「風邪」には、「ビタミンD」の方が効果的とわかったり、
「風邪の時はお風呂に入らない方が良い」と言われていたが、
最近では、「血行」を良くし、「免疫力」を高めるために、
「風邪」の時は、「お風呂」に入った方が良いと、
昔とは、色々と変わっているらしい。
下記のような「方法」が、
最近の「研究」などによって、
「風邪」に「効果的な方法」となっているようです。
「風邪」を「治す」のに「効果的な方法」一覧
| 「ビタミンD」を摂取する |
「ビタミンD」の方が、「風邪」を治すのに「必要」ということが、 最近になってわかったらしい。 |
| 身体が温かくなるぐらい「歩く」 |
「身体」が温かくなるぐらいに「歩く」と、 「血流」が良くなり、免疫力があがり、 「風邪」の引き始めぐらいなら治ってしまう。 |
| 「お風呂」に入る |
「お風呂」で「身体」を温めることで、 「免疫力」があがり、「風邪」が治りやすくなるらしい。 |
| 十分な睡眠: |
「風邪」の時は、十分な「睡眠」をすることが重要で、 「免疫力」が高まる。 「風邪」になると、 「身体」が「ウイルス」と戦うために多くのエネルギーを消費する。 普段より披露が蓄積される。 夜間の睡眠は、「成長ホルモン」が分泌され、身体の修復が活発に行われる時間帯。 |
| 水分補給 |
「風邪」の時は、「発熱」「咳」などで体内の「水分」が失われやすい。 こまめな「水分補給」が必要。 「水」「お茶」だけでなく、「スープ」「果汁」などもおすすめ。 |
| 温かい食事 |
「温かい食事」は、「身体」を芯から温めてくれて、血行を促進してくれる。 「消化」の良い「温かい食事」を心がける。 「油っこいもの」「刺激物」は避ける。 |
| 栄養バランスのよい「食事」 |
「身体」は、活動するのに、「ビタミン」「ミネラル」を必要とする。 「風邪」の時も必要なので、「栄養バランス」の良い「食事」を摂取することが大切。 「栄養」を十分に、摂取して「風邪」に対抗する。 |
| 加湿 |
「乾燥」は、 「のど」「鼻」の「粘膜」を傷つけ、風邪を悪化させることがある。 「加湿器」などを使用し、室内の湿度を適切に保つことが大切。 |
| 室温管理 |
「寒さ」は、免疫力を低下させるので、 「快適な温度」に、調整することが必要。 |
| 薬の服用 |
「風邪」の「ウィルス」を撃退するには、 「薬」を服用することも大切。 市販の風邪薬は、症状に合わせて効果的なものが多く販売されている。 薬剤師に相談して、自分に合った薬を選んでおくと良い。 |
| うがい・手洗い |
「身体」の表面、「口の中」などに付着した「ウイルス」に効果的。 「風邪」を引く前には効果的。 「風邪」を引いた後は、身体の深部になるので、あまり効果がない。 加えて、風邪を引いて、公共の場での「うがい」は、 「ウィルス」を拡散させてしまう可能性があるらしいので、 「職場」「学校」での「うがい」はやめておこう。 |
Back
「風邪」の時に、「身体を温める」のは、何故?
「風邪」を引いたときに、「身体」を温めるのは、
「風邪」に対して、効果的な影響があるから。
「身体」を温めることで得られる「効果」一覧
| 免疫力の向上 |
「身体」を温めることで、「血液循環」が良くなり、 「免疫細胞」が活発に活動できるようになる。 「免疫細胞」は、体内に侵入した「ウイルス」と戦うために重要な役割を果す。 |
| ウイルス増殖の抑制 |
多くの「ウイルス」は、「低温」の環境で、活発に「増殖」する傾向がある。 「身体」を温めることで、「ウイルス」が活動しにくい環境を作り、「増殖」を抑える効果も期待できる。 |
| 筋肉の緊張緩和 |
「風邪」を引くと、「身体」がだるく感じたり、筋肉が緊張したりすることがある。 「身体」を温めることで、筋肉がリラックスし、痛みや不快感を軽減する効果も期待できる。 |
| 発汗による解毒 |
「発汗」することで、体内に溜まった「老廃物」「毒素」を排出することができる。 |
「身体」を温める具体的な「方法」一覧
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 温かい「飲み物」 | 温かいお茶、スープ、生姜湯など、体を温める飲み物をこまめに飲みましょう。 |
| 温かい「食事」 | 温かいご飯や味噌汁など、温かい食事を摂るようにしましょう。 |
| 「湯船」に浸かる | 温かいお湯にゆっくりと浸かることで、全身を温めることができます。 |
| 「暖房器具」を使う | 部屋を暖かく保つために、暖房器具を使いましょう。 |
| 「首」「手首」「足首」を温める | これらの部分は大きな血管が通っているため、温めることで体の芯まで温まります。 |
| 歩く |
「熱」が出る前であれば、 少し早めに「歩く」と、 「血流」が良くなり、身体も温まる。 免疫力も向上すると言われている。 |
| 「有酸素運動」をする |
「熱」が出る前であれば、 「体温」を上げるために、 軽い「有酸素運動」をするのも、「風邪」には効果的。 |
Back
「風邪」の引き始めには「お風呂」は効果的
風邪の引き始めには、
「お風呂」に入って、
「血流」を良くするのが効果的です。
「血流」が良くなることで、
身体の隅々に、
酸素と栄養を届け、
不純物・排泄物など、
滞っていたものを排出してくれます。
「血流」が良くなることで、
風邪などへの「抵抗力」も強くなるので、
風邪の引き始めであれば、
お風呂で治すことが可能です。
Back
「高熱」が出たら「身体」を冷やして「通常体温」を「キープ」
「風邪」を引いて、「高熱」が出たら、
「体温」が上がり過ぎないように「冷やす」ことが必要になる。
そして、「通常体温」の少し上ぐらいの体温をキープする。
「人の身体」は、
「低温」だと「免疫力」が「半分以下」になってしまい、
「高温」すぎても、身体の機能が維持できなくなって危険になり、亡くなることもある。
丁度良い「体温」でなければ、
「人の身体」は、生きていけないようになっている。
「高熱」が出た時の「対処方法」
| 対処方法 | 説明 |
|---|---|
| 「水」をたくさん飲む |
「発汗」により「身体」を冷やそうとする「機能」を促す。 「汗をかく」のは、「身体の放熱機能」なので、 十分に活用して、自律神経などのバランスも整えられる。 |
| 「首」「脇」「鼠径部」「膝裏」「肘」を冷やす |
「関節」となる 「首」「脇」「鼠径部」「膝裏」「肘」は、 「骨」の部分よりも、「血管」を冷やしやすく、 「身体」を冷やすときに「効果的」な部分。 「水」を含ませた「タオル」や、 「保冷剤」などを置くと、 「関節部分」の「肉」「血液」などが冷やせる。 |
| 「冷湿布」を貼る |
市販の「冷湿布」は、身体を冷やすのに効果的。 「首」「脇」「鼠径部」「膝裏」「肘」などに貼ることで、 効果的に、身体を冷やすことができる。 |
| 濡らしたタオル |
「濡らしたタオル」も、「揮発効果」による「冷却効果」があるので効果的。 冷たすぎず、じっくりと「身体」を冷やしてくれる。 「首」「脇」「鼠径部」「膝裏」「肘」に置いておくだけでも冷却効果がある。 |
| 「冷たい飲み物」を飲む |
「冷たい飲み物」を飲むだけで、 「身体の内部」の「熱」を吸収してくれる。 「水分補給」も兼ねることができるので、 |
| 「アイスクリーム」を食べる |
少ない量で、身体を内側から冷やすのに最適。 「かき氷」「棒アイス」なども効果的。 |
| 低温の空間で生活する |
「高熱」が出た時は、 「汗」を掻くので、 「室温」を下げておくと、 「汗」が冷却されて、「体温」も下げることができる。 |
| 体温を下げる「食べ物」を食べる | 「なす」「ゴーヤ「ミント」「レモングラス」など。 |
| 「水分」の多い「食べ物」を食べる |
「水分」を多く摂取して、 「発汗」「排尿」などと一緒に、 「熱」の排出してくれる。 「水分の多い食べ物」には、 「スイカ」「メロン」「イチゴ」「グレープフルーツ」 「キュウリ」「トマト」「レタス」「セロリ」 などがある。 |
| 「カリウム」を多く含む「食べ物」を食べる |
「カリウム」は、 「利尿作用」があるため、 「排尿」と一緒に「熱」も体外に排出してくれる。 「カリウム」を多く含む「食べ物」には、 「バナナ」「アボカド」「大根」「ほうれん草」 などがある。 |
| 「ぬるめのお風呂」に入る |
寒くならない程度のぬるいお風呂に入ると、 「水」に「体温」が奪われるので、 「高熱」になった「体温」を下げることができる。 |
Back
「喉」が痛い時の治し方
「喉」が痛くなった時には、
下記の方法を試すと、
ほとんどの「喉の痛み」が治ります。
科学的な根拠などはわかりませんが、
基本的な予防策の域なので、
気軽に試すことができます。
「喉」が痛くなった時には、
・うがいをする
・のど飴を舐める
・うがい薬でうがいをする
・お風呂に入る
・アルコール濃度高めのお酒を飲む
・薬(風邪薬・炎症止め(ロキソニン)など)を飲む
・喉にシップ(鎮痛消炎薬入り)を貼る
などの方法を実行すると、・のど飴を舐める
・うがい薬でうがいをする
・お風呂に入る
・アルコール濃度高めのお酒を飲む
・薬(風邪薬・炎症止め(ロキソニン)など)を飲む
・喉にシップ(鎮痛消炎薬入り)を貼る
「喉の痛み」が改善していきいます。
「シップ(炎症鎮静剤入り)」は、
かなり効果があるので、
痛みが酷い時などに、
「喉」に貼って眠ると、
かなり改善するのでオススメです。
Back
「喉の痛み」には鎮痛消炎効果のある「湿布」を貼る
「喉」の痛みが酷くなった時は、
「鎮痛消炎効果」のある「湿布」を
「喉」に貼ると、
痛みが和らぎ、良くなります。
通常だと、
「ロキソニン」などの「解熱鎮痛消炎効果」のある
「錠剤」などを服用して治しますが、
酷くなった「喉の痛み」には、
「錠剤」だけの服用では足りないこともあります。
「鎮痛消炎効果」のある「湿布」は、
薬局でも市販されています。
「喉」の痛む部分に貼り付けることで、
「鎮痛消炎」の働きを助けることができます。
「鎮痛消炎効果」のある「湿布」
「鎮痛消炎効果」のある「湿布」は、
「鎮痛消炎効果」を持つ成分である
・ケトプロフェン(モーラステープ)
・ロキソプロフェン(ロキソニンテープ)
のいずれかが使用されている。
どちらでも、
「鎮痛消炎効果」の優劣はないそうです。
モーラステープ
「ロキソニンテープ」
「鎮痛消炎効果」を持つ成分である
・ケトプロフェン(モーラステープ)
・ロキソプロフェン(ロキソニンテープ)
のいずれかが使用されている。
どちらでも、
「鎮痛消炎効果」の優劣はないそうです。
モーラステープ
「モーラステープ」は、
鎮痛消炎成分「ケトプロフェン」を使用し、
「シクロオキシゲナーゼ(COX)」を阻害することによって、
炎症を引き起こす「プロスタグランジン」が生成されるのを抑制し、
「炎症」「痛み」「熱」を抑制する効果を発揮する。
鎮痛消炎成分「ケトプロフェン」を使用し、
「シクロオキシゲナーゼ(COX)」を阻害することによって、
炎症を引き起こす「プロスタグランジン」が生成されるのを抑制し、
「炎症」「痛み」「熱」を抑制する効果を発揮する。
「ロキソニンテープ」
「ロキソニンテープ」の鎮痛消炎成分は、
「ロキソプロフェン」で、
「ケトプロフェン」と同じ効果を持っている。
「錠剤」などで、
「飲み薬」などでも使用されている。
「ロキソニン」という名前で知られている。
「ロキソプロフェン」で、
「ケトプロフェン」と同じ効果を持っている。
「錠剤」などで、
「飲み薬」などでも使用されている。
「ロキソニン」という名前で知られている。
Back
昔ながらの「風邪」の治し方「緑茶でうがい」
昔ながらの「風邪」の治し方の一つに、
簡単で、効果的な方法の「緑茶でうがい」があります。
「緑茶」には、
「抗菌作用」のある「カテキン(タンニン)」が含まれていて、
風邪予防に効果的な「ビタミンC」も豊富。
「緑茶」で「うがい」をする時は、
いつもより濃い目にするのも効果的だそうです。
「緑茶」に含まれる成分で、
・カテキン(タンニン) = 「抗菌作用」「抗酸化作用」
・テアニン = 「神経細胞保護作用」「リラックス作用」
・ビタミンC = 「皮膚や粘膜の健康維持」「抗酸化作用」
・ビタミンB2 = 「皮膚や粘膜の健康維持」
・ビタミンE = 「抗酸化作用」
・ミネラル(カリウム、カルシウム、リン、マンガンなど) = 「生体調節作用」
などが、・テアニン = 「神経細胞保護作用」「リラックス作用」
・ビタミンC = 「皮膚や粘膜の健康維持」「抗酸化作用」
・ビタミンB2 = 「皮膚や粘膜の健康維持」
・ビタミンE = 「抗酸化作用」
・ミネラル(カリウム、カルシウム、リン、マンガンなど) = 「生体調節作用」
「風邪」に効果的で、
身体の機能を正常に戻す効果があると言われている。
「緑茶」には、
人の身体を健康に維持する成分が豊富に含まれている。
「緑茶」の「成分」と「効果」
| 成分 | 説明 |
|---|---|
| カテキン(渋味成分) |
お茶の「ポリフェノール」。 ・血中コレステロールの低下 ・体脂肪低下作用 ・がん予防 ・抗酸化作用 ・虫歯予防 ・抗菌作用 ・抗インフルエンザ作用 ・血圧上昇抑制作用 ・血糖上昇抑制作用 ・口臭予防(脱臭作用) |
| タンニン |
「タンニン」は、お茶のポリフェノール「カテキン」の別名。 茶葉に含まれる「タンニン」は、 「エピカテキン」「エピガロカテキン」などの「カテキン類」と その没食子酸エステル誘導体。 「苦み」「渋味」を持つ成分で、 「茶葉」の味覚を決める重要な成分。 |
| カフェイン(苦味成分) |
・覚醒作用(疲労感や眠気の除去) ・持久力増加 ・二日酔い防止 ・利尿作用 |
| テアニン(うま味成分) |
・神経細胞保護作用 ・リラックス作用(α波出現) |
| ビタミンC |
・皮膚や粘膜の健康維持(コラーゲン形成) ・抗酸化作用 |
| ビタミンB2 |
・皮膚や粘膜の健康維持 |
| 葉酸 |
・神経管閉鎖障害の発症予防 ・動脈硬化予防 |
| β-カロテン |
・夜間の視力維持 |
| ビタミンE |
・抗酸化作用 |
| サポニン |
・血圧低下作用 ・抗インフルエンザ作用 |
| フッ素 |
・虫歯予防 |
| γ-アミノ酪酸(通称:GABA) |
・血圧低下作用 |
| ミネラル(カリウム、カルシウム、リン、マンガンなど) |
・生体調節作用 |
| クロロフィル |
・消臭作用 |
Back
昔ながらの「風邪」の治し方「にんにく味噌」
昔ながらの「風邪」の治し方の一つに
「にんにく味噌」があります。
「にんにく」は、
「滋養」「強壮」に効くことで、
昔から知られています。
風邪にも効果を発揮してくれる食材の一つ。
皮がついたたまま焼いて、
蒸し焼きされた「にんにく」を
そのまま食べても、
「風邪」に効果があります。
皮が付いたまま焼いて、
蒸し焼きにした「にんにく」を、
「おろし金」で擦り、
適量の「おろしにんにく」と「味噌」を混ぜ、
「お湯」を注いで飲むと、
「風邪」に効果的と言われていました。
焼いた「にんにく」は、
完全に火が通ると、
臭いもなくなるので、
食べやすくなります。
Back
昔ながらの「風邪」の治し方「梅干しの黒焼き」
昔ながらの「風邪」の治し方で、
「梅干しの黒焼き」があります。
「梅干し」が、
風邪に効果的なのは、
定番として知られています。
身体に良く、
疲れを早くとってくれる「クエン酸」が、
豊富に含まれていて、
血液の流れを綺麗にしてくれる効果もある。
「殺菌作用」があるので、
風邪の引き始めには最適の食材の一つ。
「梅干しの黒焼き」は、
その効果を摂取しやすいようにした調理法の一つ。
「梅干しの黒焼き」は、
「梅干し2個」を網などで、
焦げ目が付くまで焼く。
茶碗に入れて、
「熱湯」を注いで、
「梅干しの黒焼き」の実をほぐす。
「おろししょうが」を少量加えて、
暖かいうちに飲む。
身体がポカポカして、
殺菌もされて、
風邪も治りやすくなります。
Back
昔ながらの「風邪」の治し方「卵酒」
「風邪」の定番メニューの一つ「卵酒」。
だいぶ昔には、
よく聞いた「卵酒」ですが、
最近は、まったく聞かなくなりました。
海外でも、
「お酒」に「卵」を入れたり、
「砂糖」を入れたりと、
お酒を温めて、栄養を加えるという風習は、
昔からあるようです。
「卵酒」の作り方
・「卵」をよくかき混ぜ、「はちみつ」を入れる。
・「お酒」を熱めに温める。
・「お酒」の火を弱めるか、消す。
・用意した「卵」を「お酒」をかき混ぜながら、少しずつ注ぐ。
加熱しながら、「卵」を加えると、
凝固しやすく、固くなりがちになるので、
「卵」を混ぜる時は、「加熱」をやめ「余熱」にする。
・「お酒」を熱めに温める。
・「お酒」の火を弱めるか、消す。
・用意した「卵」を「お酒」をかき混ぜながら、少しずつ注ぐ。
加熱しながら、「卵」を加えると、
凝固しやすく、固くなりがちになるので、
「卵」を混ぜる時は、「加熱」をやめ「余熱」にする。
「卵」は、
「完全栄養食」として注目を集めている食材。
人が、健康を維持するために必要な栄養素を
バランスよく含んでいる。
「健康」「美容」にとても良いと言われています。
昔ながらの知恵ですが、
現在でも、理にかなっている
風邪に良い料理。
Back
昔ながらの「風邪」の治し方「しょうが湯」
「風邪」の時は、 「しょうが」も家庭の風邪療法として、
良く知られています。
身体が「ぽかぽか」と温まり、
「鼻づまり」「せき」「熱」などの
風邪の色々な症状に効果があると言われいます。
「しょうが湯」の作り方
・「しょうが」を擦りおろし、しぼって「しぼり汁」をつくる
・「しぼり汁」をグラスなどに入れる
・「はちみつ」「レモン果汁」を加える
・熱い「お湯」を注いで、かき混ぜたら完成。
・「しぼり汁」をグラスなどに入れる
・「はちみつ」「レモン果汁」を加える
・熱い「お湯」を注いで、かき混ぜたら完成。
Back
昔ながらの風邪予防「みかんの皮」
「みかんの皮」は、
漢方では「陳皮」と呼ばれ、
風邪に効果があり、
胃腸に薬効があるとされている。
「みかんの皮」の使い方
・そのまま食べる
・「みかん茶」にする
・お風呂に入れる
・日干しして、粉末状にし、「料理」「ふりかけ」にして食べる
・「みかん茶」にする
・お風呂に入れる
・日干しして、粉末状にし、「料理」「ふりかけ」にして食べる
Back
食材を使った「鼻水」対策
昔ながらの知恵で、
「食材」を利用した「鼻水」の対策があります。
「鼻」が詰まって、苦しい時に、
「食材」で対応することができる。
「長ネギ」「たまねぎ」を使った「鼻水対策」
「ネギ」「タマネギ」の成分の中に、
「鼻」の通りを良くする成分が含まれている。
その成分を利用し、
「嗅ぎ薬」を作ると、
「鼻水対策」ができます。
「長ネギ」の場合
「タマネギ」の場合
「長ネギ」「タマネギ」ともに、
「バンドエイド」などで固定しておくと便利。
「鼻」の通りを良くする成分が含まれている。
その成分を利用し、
「嗅ぎ薬」を作ると、
「鼻水対策」ができます。
「長ネギ」の場合
・「長ネギ」を「3cm」ぐらいカットする
・「ネバネバ」した部分を取り出す
・鼻の穴の下や周辺に、「ネバネバ」部分の「ネギ」を充てる
・鼻がすっと通り、楽になる
・「ネバネバ」した部分を取り出す
・鼻の穴の下や周辺に、「ネバネバ」部分の「ネギ」を充てる
・鼻がすっと通り、楽になる
「タマネギ」の場合
・「タマネギ」を少量スライスする
・鼻の穴の下や周辺に、スライスした「タマネギ」をを充てる
・鼻がすっと通り、楽になる
・鼻の穴の下や周辺に、スライスした「タマネギ」をを充てる
・鼻がすっと通り、楽になる
「長ネギ」「タマネギ」ともに、
「バンドエイド」などで固定しておくと便利。
「大根おろし」を使った「鼻水対策」
「大根おろし」を使った「鼻水対策」には、
「大根おろし」の「おろし汁スープ」の作り方
・「大根おろし」の「おろし汁スープ」を飲む。
・「脱脂綿」に「大根おろし」の「おろし汁」を付けて鼻に詰める。
などの方法がある。・「脱脂綿」に「大根おろし」の「おろし汁」を付けて鼻に詰める。
「大根おろし」の「おろし汁スープ」の作り方
・「大根おろし」の「おろし汁」を煮立てる
・「ニンニク」を「一片」をすりおろす
・煮立てた「おろし汁」に、おろした「にんにく」を加える
・かき混ぜて、ひと煮立ちさせる
・熱いうちに飲む
・「ニンニク」を「一片」をすりおろす
・煮立てた「おろし汁」に、おろした「にんにく」を加える
・かき混ぜて、ひと煮立ちさせる
・熱いうちに飲む
Back
食材を使った「せき対策」
昔ながらの知恵で、
食材を使った「せき対策」もあります。
・キンカンの砂糖煮
・ザクロの砂糖漬けエキス
・ギンナンの油漬け
・ザクロの砂糖漬けエキス
・ギンナンの油漬け
キンカンの砂糖煮
「キンカン」は、
冬になると売られているのを見かけます。
のど飴などにも含まれている「キンカン」は、
昔からの「風邪薬」。
「キンカンの砂糖煮」の作り方は、
冬になると売られているのを見かけます。
のど飴などにも含まれている「キンカン」は、
昔からの「風邪薬」。
「キンカンの砂糖煮」の作り方は、
・「キンカン」に6本ほどの切れ目を入れる
・一晩「水」につけて苦味を採る(2~3回ほど水交換する)
・鍋に「砂糖200g」「水1カップ」を入れ、ゆっくりと煮詰める
・煮詰まって、柔らかくなったら完成
・一晩「水」につけて苦味を採る(2~3回ほど水交換する)
・鍋に「砂糖200g」「水1カップ」を入れ、ゆっくりと煮詰める
・煮詰まって、柔らかくなったら完成
ザクロの砂糖漬けエキス
女性のホルモンバランスを保つ効果がある「ザクロ」。
風邪の「せき」にも効果がある。
「ザクロの砂糖漬けエキス」の作り方
風邪の「せき」にも効果がある。
「ザクロの砂糖漬けエキス」の作り方
・「ザクロ」の実を「輪切り」にする
・「白砂糖」に漬け込んで保存する
・「砂糖漬けエキス」が出て来るのを待つ
・「白砂糖」に漬け込んで保存する
・「砂糖漬けエキス」が出て来るのを待つ
ギンナンの油漬け
「ギンナン」は、
「強精」「強壮」の妙薬として知られ、
「アレルギー」「喘息」の「せき」にも効果がある。
「せき」がしつこい時におすすめ。
「ギンナンの油漬け」の作り方
「強精」「強壮」の妙薬として知られ、
「アレルギー」「喘息」の「せき」にも効果がある。
「せき」がしつこい時におすすめ。
「ギンナンの油漬け」の作り方
・生の「ギンナン」の殻を割る
・フライパンで、軽く煎る
・「薄皮」をむく
・「乾燥殺菌」した「広口びん」に「ギンナン」を入れる
・「ごま油」を「ギンナン」が隠れるぐらいに注ぐ
・冷暗所に保存する
・フライパンで、軽く煎る
・「薄皮」をむく
・「乾燥殺菌」した「広口びん」に「ギンナン」を入れる
・「ごま油」を「ギンナン」が隠れるぐらいに注ぐ
・冷暗所に保存する
Back
海外の「風邪対策」
海外にも、
日本の昔ながらの方法に似た「風邪対策」があるそうです。
中国
同量の「水」「お酢」を鍋に入れ、
沸騰させた蒸気で、部屋を温める。(吸入法)
沸騰させた蒸気で、部屋を温める。(吸入法)
オーストラリア
熱く温めた「ミルク」に、
「ラム酒」を加え、卵の「黄身」をそのまま落として完成。
暖かいうちに飲むと、身体が温まり、
風邪に効果的らしい。
「ラム酒」を加え、卵の「黄身」をそのまま落として完成。
暖かいうちに飲むと、身体が温まり、
風邪に効果的らしい。
オランダ
・「ブランデー」で作る「卵酒」
・「ワイン」を温め、「砂糖」を加えた「ホットワイン」。
・「ワイン」を温め、「砂糖」を加えた「ホットワイン」。
スイス
「紅茶」に、
「ウィスキー」を混ぜて飲む。
「ウィスキー」を混ぜて飲む。
イタリア
「紅茶」に、
「レモン果汁」を「1個分」入れて飲む。
「レモン果汁」を「1個分」入れて飲む。
インド
「紅茶」に、
「しょうが」の「しぼり汁」を入れて飲む。
「しょうが」の「しぼり汁」を入れて飲む。
Back