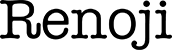Life
美容 & 健康
ボディケア
自分の「能力」を最大限に発揮する方法「集中力」を高める方法「身体」がムズムズして落ち着かない時の解消方法「健康寿命」を伸ばす方法「体の老化」を抑制する方法身体の「老廃物の排出(デトックス)」をする方法「むくみ」を解消する方法「身体の疲れ」を除去する方法「自律神経」を整える方法「筋肉痛」を解消する方法「化膿」「炎症」しやすい「体質」の「改善方法」「身体」を「アルカリ性」に保つ方法「眠気」を覚ます方法「質の良い睡眠」をとる方法効率的に「ダイエット」をする方法体のしくみ
「尿」の役割部位
「肩こり」を解消する方法「目」をスッキリとさせる方法「脳」を使いこなす方法「綺麗」な「指」を手にいれる方法「鼻づまり」を「解消」する方法家庭の医学(治療方法)
「風邪(かぜ)」の「治し方」「喉の痛み」を治す豆知識皮膚にできた「イボ」の治し方「痛風」の「正体」と「痛み」を「解消」「治療」する方法「ガン(癌)」を「予防」する方法季節
「冷え性」を解決する方法「暑い夏」に効率的に「身体」を冷やす方法
【身体】「脳」を使いこなす方法
【身体】
「脳」を使いこなす方法
「脳」を使いこなす方法
INDEX
■ はじめに
■ 「脳」が「スッキリ」とした状態で、「1日」を過ごす「方法」
■ 「脳」の「仕組み」
■ 「脳内物質」とは
「脳内物質」
■ 「ドーパミン」とは
■
■ 「ドーパミン」が生成される「場所」
■ 「脳内」で「ドーパミン」が「分泌」される「影響」
■ 「ドーパミン」の「生成過程」
■ 「ドーパミン」が良く分泌される状況
■ 「運動」によって分泌される「ドーパミン」は「脳」をスッキリにする
■ 「ドーパミン」の分泌を促進する「食べ物」
■ 「ドーパミン」が「過剰分泌」された時の「影響」
■ 「ノルアドレナリン」とは■ 「ドーパミン」が生成される「場所」
■ 「脳内」で「ドーパミン」が「分泌」される「影響」
■ 「ドーパミン」の「生成過程」
■ 「ドーパミン」が良く分泌される状況
■ 「運動」によって分泌される「ドーパミン」は「脳」をスッキリにする
■ 「ドーパミン」の分泌を促進する「食べ物」
■ 「ドーパミン」が「過剰分泌」された時の「影響」
■ 「ノルアドレナリン」が「生成」される「場所」
■ 「ノルアドレナリン」が「分泌」された時の「影響」
■ 「ノルアドレナリン」と「アドレナリン」の違い
■ 「ノルアドレナリン」の「生成」
■ 「理想」の働き方は、「ノルアドレナリン」と「ドーパミン」を使い分ける
■ 「適度なストレス」をたまに受けると「仕事」の「効率」「質」を高める
■ 「アドレナリン」とは■ 「ノルアドレナリン」が「分泌」された時の「影響」
■ 「ノルアドレナリン」と「アドレナリン」の違い
■ 「ノルアドレナリン」の「生成」
■ 「理想」の働き方は、「ノルアドレナリン」と「ドーパミン」を使い分ける
■ 「適度なストレス」をたまに受けると「仕事」の「効率」「質」を高める
■ 「セロトニン」とは
■ 「セロトニン」が「分泌」される「主な場所」
■ 「セロトニン」の「影響」
■ 「セロトニン」の「合成」と「分泌」
■ 「セロトニン」の材料となる必須アミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれる「食べ物」
■ 「セロトニン生成」に必要な「ビタミンB6」が豊富に含まれる「食べ物」
■ 「セロトニン」を「活性化」する「方法」
■ 「メラトニン」とは■ 「セロトニン」の「影響」
■ 「セロトニン」の「合成」と「分泌」
■ 「セロトニン」の材料となる必須アミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれる「食べ物」
■ 「セロトニン生成」に必要な「ビタミンB6」が豊富に含まれる「食べ物」
■ 「セロトニン」を「活性化」する「方法」
■ 「アセチルコリン」とは
■ 「アセチルコリン」が「生成」される「場所」
■ 「アセチルコリン」の「影響」
■ 「アセチルコリン」の「生成」を促進する方法
■ 「アセチルコリン」が、よく「分泌」される「状況」
■ 「アセチルコリン」の原料「レシチン」を豊富に含む「食べ物」
■ 「エンドルフィン」とは■ 「アセチルコリン」の「影響」
■ 「アセチルコリン」の「生成」を促進する方法
■ 「アセチルコリン」が、よく「分泌」される「状況」
■ 「アセチルコリン」の原料「レシチン」を豊富に含む「食べ物」
■ 「エンドルフィン」の「影響」
■ 「エンドルフィン」が「生成」される「場所」
■ 「エンドルフィン」の「生成」
■ 「エンドルフィン」の「分泌」を促進する「方法」
■ 「アルファ波」を出す「方法」
■ 「エンドルフィン」が「生成」される「場所」
■ 「エンドルフィン」の「生成」
■ 「エンドルフィン」の「分泌」を促進する「方法」
■ 「アルファ波」を出す「方法」
■ Gallery
はじめに
「脳」が「スッキリ」とした状態で、「1日」を過ごす「方法」
「脳」が「スッキリ」とした「1日」を過ごすには、
・「カーテン」を開けて、「太陽の光」を浴びながら「5分」ほど過ごす
・「栄養バランス」の良い「食事」をする
・「咀嚼」する
・「新しい事」に挑戦する
・「変化」を取り入れる
・「ちょっと難しい目標」を設定する
・1つのことに「集中」する
・「目標」を達成する
・「リラックス」をする
・「癒し」を感じる
・「深呼吸」する
・「音読」をする
・「平穏」な「心の状態」になる
・「運動」をする
・「リズム運動」をする
・「お風呂」に入る
・睡眠前に、「薄暗い部屋」でリラックスする
・睡眠前に、「蛍光灯の光」を浴びない
・睡眠前に、「ゲーム」「スマートフォン」「パソコン」をしない
・部屋を真っ暗にして眠る
・「栄養バランス」の良い「食事」をする
・「咀嚼」する
・「新しい事」に挑戦する
・「変化」を取り入れる
・「ちょっと難しい目標」を設定する
・1つのことに「集中」する
・「目標」を達成する
・「リラックス」をする
・「癒し」を感じる
・「深呼吸」する
・「音読」をする
・「平穏」な「心の状態」になる
・「運動」をする
・「リズム運動」をする
・「お風呂」に入る
・睡眠前に、「薄暗い部屋」でリラックスする
・睡眠前に、「蛍光灯の光」を浴びない
・睡眠前に、「ゲーム」「スマートフォン」「パソコン」をしない
・部屋を真っ暗にして眠る
などのことを意識して過ごすと、
「脳」などが「活性化」され、
「脳内物質」などが、良く「分泌」され、
身体を良い方向へと導いてくれる。
「脳」「身体」「精神」を良い方向へと導いてくれる
「脳内物質」が、良く分泌されるとわかった行動をまとめると、
上記のような「生活スタイル」になる。
「脳」を大切にし、良い環境で、「脳」が活動できるようにするのは、
人の活動としては、一番効率が良い方法になる。
Back
「脳」の「仕組み」
「人の脳」には、
「数百億個の神経細胞」が存在し、
相互に、複雑なネットワークを構成することで、
形成されている。
「神経細胞」は、「シナプス」という「接合部分の隙間」がある。
「シナプスの前膜」からは、「神経伝達物質」が分泌され、
「シナプスの後膜」には、「神経伝達物質」を受け取る「受容体」がある。
「神経細胞」が結合し、「神経伝達物質」を受け取り、「分泌」することで、
「刺激が伝達」されるようになっている。
「脳内物質」という俗称がある「神経伝達物質」は、 どのように分泌されるかで、 「神経ネットワーク」の繋がり方が変わってくる。
Back
「脳内物質」とは
「脳内物質」は、
「50以上」の種類が存在し、
「脳内」で「分泌」され「伝達」することで、神経ネットワークの繋がりが形成される。
その中でも、重要な役割をになっている「7つの脳内物質」がある。
「7つの脳内物質」には、
・ドーパミン
・ノルアドレナリン
・アドレナリン
・セロトニン
・メラトニン
・アセチルコリン
・エンドルフィン
があり、
人の「モチベーション」などの感情を形成する。
「脳内物質」の特徴から、
それぞれの影響が強い時に、
・「ドーパミン」は、「学習脳」
・「ノルアドレナリン」は、「仕事脳」
・「セロトニン」は、「共感脳」
とも言われている。
| 脳内物質 | 説明 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーパミン |
「ドーパミン」は、 「モチベーションの源」と言われる「脳内物質」。 「より高い目標」「より困難な目標」を目の前にすると分泌される。 困難な状況に追い込まれるほど、俄然やる気を見せる性格の人は、 「ドーパミン」がよく分泌されている人に特徴が一致する。 「ドーパミン」は、 「幸福物質」と言われていて、 「分泌」されると、 「幸福」「快感」を感じられ、 「学習意欲」「やる気」などが出てくるので、 「報酬系」「学習脳」とも呼ばれている。 「ドーパミン」が「分泌」される「効果」
| ||||||||||||||||||
| ノルアドレナリン |
「闘争」と「逃走」の「ホルモン」と呼ばれている。 「闘うか」「逃げるか」という「選択」「行動」が求められる「危機的な状況」で分泌される「脳内物質」。 「ノルアドレナリン」の「長期的な分泌」は、「うつ病」の原因とも言われている。 「闘争か逃走か」「恐怖」「不安」「集中」 「ストレス反応」「ワーキングメモリ」「仕事脳」「交感神経」 「ノルアドレナリン」が、分泌されることで、「心拍数」が高まり、「脳」「骨格筋」に「血液」が行き渡る。 「闘争」「逃走」のどちらを選択するにしても、 「瞬発的な行動」が取れるようにし、「脳」「身体」を準備状態に持っていくのが、「ノルアドレナリンの役割」。 「ノルアドレナリン」により、「覚醒度」「集中度」がアップし、 「正しい判断」が「瞬間的」にできるようになり、「脳」の機能が大きくアップする。 | ||||||||||||||||||
| アドレナリン |
「アドレナリン」は、「闘争ホルモン」と言われる「脳内物質」。 「闘い」に直面した時や、「闘い」の最中に分泌される。 「交感神経」の伝達物質。 「興奮物質」「興奮」「怒り」「交感神経(昼の神経)」 「アドレナリン」が、 「血液中」に放出されると、 「心拍数」「血圧」が高まり、「筋肉」に「血液」が行き渡る。 「血糖」を高め、「瞳孔」が開き、「覚醒度」を上げる。 「注意力」「集中力」が高まり、「身体」「脳」が、「臨戦態勢」の状態になる。 | ||||||||||||||||||
| セロトニン |
「セロトニン」が、よく分泌されると、「心穏やか」な状態になる。 「僧侶」が、坐禅をしているときのような状態。 「心」に、「冷静」と「落ち着き」をもたらす。 「癒しの物質」「落ち着き」「平常心」「心の安定」「共感脳」 「セロトニン」が「分泌」されると、 「ドーパミン」「ノルアドレナリン」「アドレナリン」などの 「興奮系脳内物質」の「過剰分泌」を抑制し、 「脳内物質」の「バランス」を取る「調節物質」。 「セロトニン」が「活性化」された状態だと、 「心が安定した状態」になる。 「セロトニン」が「不足」すると、 「イライラ」「むしゃくしゃ」「落ち着かない」「不安」 などを感じるようになる。 | ||||||||||||||||||
| メラトニン |
「メラトニン」は、「睡眠物質」で、 「睡眠」と「覚醒」を調整する「ホルモン」。 「濃度」が高まると、「眠気」を感じ、 スムーズに睡眠へと至る。 「睡眠物質」「眠気」「回復物質」「アンチエイジング」 「メラトニン」が分泌されると、 「脳神経」だけでなく、 「脈拍」「体温」「血圧」を低下させる事で、 「睡眠」と「覚醒」のリズムを調整し、 「自然な睡眠」へと誘導する作用がある。 | ||||||||||||||||||
| アセチルコリン |
「アセチルコリン」は、「発想力」と「集中力」を担う「脳内物質」。 「全身の臓器」を「クールダウン」する「副交感神経」の伝達物質でもある。 「記憶と学習」「ひらめき」 「副交感神経(夜の神経)」「ニコチン」「シータ波」 「アセチルコリン」が分泌されると、
などの影響がある。 | ||||||||||||||||||
| エンドルフィン |
「エンドルフィン」は、 僧侶が荒業の末に辿り着く、悟りの境地に達した時に分泌される「脳内物質」。 「脳内麻薬」「多幸感」「恍惚感」「アルファ波」 「エンドルフィン」が分泌されると、 「幸福感」を与えてくれ、 脳を休め、「注意力」「集中力」「記憶力」「創造性」など、 多くの「脳機能」を高めてくれる。 また、「免疫力」を高め、「身体の修復力」も高める効果もある。 「癌と戦う免疫機能」を担う「NK活性」を高める作用や、 「抗がん作用」も確認されている。 | ||||||||||||||||||
Back
「ドーパミン」とは
「ドーパミン」は、
「モチベーションの源」と言われる「脳内物質」。
「より高い目標」「より困難な目標」を目の前にすると分泌される。
困難な状況に追い込まれるほど、俄然やる気を見せる性格の人は、
「ドーパミン」がよく分泌されている人に特徴が一致する。
「ドーパミン」は、
「幸福物質」と言われていて、
「分泌」されると、
「幸福」「快感」を感じられ、
「学習意欲」「やる気」などが出てくるので、
「報酬系」「学習脳」とも呼ばれている。
「ドーパミン」が生成される「場所」
「ドーパミン」は、
「中脳」と呼ばれる「脳」の奥深い場所にある「特定の神経細胞」で生成される。
主に、
・腹側被蓋野(ふくそくひがいや) (Ventral tegmental area, VTA)
・黒質(こくしつ) (Substantia nigra)
という「神経細胞」で生成される。
「中脳」と呼ばれる「脳」の奥深い場所にある「特定の神経細胞」で生成される。
主に、
・腹側被蓋野(ふくそくひがいや) (Ventral tegmental area, VTA)
・黒質(こくしつ) (Substantia nigra)
という「神経細胞」で生成される。
| 神経細胞 | 説明 |
|---|---|
| 腹側被蓋野(ふくそくひがいや) (Ventral tegmental area, VTA) |
「腹側被蓋野(ふくそくひがいや)」は、「報酬系」の中心的な役割を担う部位。 「楽しいこと」や「嬉しい経験」をした時に、 この部位から「ドーパミン」が放出され、「快感」や「報酬感」をもたらす。 |
| 黒質(こくしつ) (Substantia nigra) |
「黒質(こくしつ)」は、「運動機能の制御」に深く関わっている。 この部位から「線条体」へ「ドーパミン」が放出され、 「スムーズな運動」を可能にする。 |
「脳内」で「ドーパミン」が「分泌」される「影響」
「脳内」で、「ドーパミン」が「分泌」されると、
様々な「嬉しい効果」が期待できる。
「脳内」で「ドーパミン」が分泌されると
様々な「嬉しい効果」が期待できる。
「脳内」で「ドーパミン」が分泌されると
| 「やる気」「意欲」が向上する | 「目標達成」や「報酬」を得ることに対する「意欲」が高まる。「行動」を起こしやすくなる。 |
| 「集中力」が高まる | 「目標」に向かって「集中」しやすくなり、「作業効率」がアップする。 |
| 「快感」を感じる | 「嬉しいこと」や「楽しいこと」を経験した時に、「快感」を感じる。 |
| 「学習能力」が向上する | 「新しいこと」を学ぶ意欲が高まり、「記憶力」も向上する可能性がある。 |
| 「創造性」が向上する | 「新しいアイデア」が生まれやすくなり、創造的な活動が活発になる。 |
「ドーパミン」の「生成過程」
「ドーパミン」は、
「チロシン」という「アミノ酸」から、
いくつかの「酵素の働き」によって合成される。
「チロシン」という「アミノ酸」から、
いくつかの「酵素の働き」によって合成される。
「ドーパミン」が良く分泌される状況
・新しい事に直面した時
・変化を取り入れている時
・ちょっと難しい課題に直面している時
・目標を達成した時
・運動をした時
「ドーパミン」は、
「マンネリ」を嫌う傾向があり、
「工夫」「変化」を好む。
「ワクワク」「ハラハラ」という感情で、
「ドーパミン」が分泌される。
「変化」を取り入れることで、
「ドーパミン」が分泌される状況を生み出すことができる。 「脳」は、「チャレンジ」を好む。
「新しい事」をしてみることで、
「ドーパミン」の分泌を促進する傾向があるため、
「新しい手段」「新しい方法」「新しい場所」「新しい環境」など、
「新しい事」を積極的に取り入れることを意識すると良い。
変化を前向きに受け止める事で、
「ドーパミン」の分泌が促進され、
アイシンの能力を伸ばす絶好のチャンスとなる。
「ドーパミン」は、
「目標を達成した時」にも、
より「ドーパミン」を分泌する。
「作業前」に、「目標」と「報酬」となるものを決めておくと、
「目標達成」をしたときの「ドーパミン分泌」が多くなると言われている。
「作業」が終わってから、「報酬」を決めると、
「ドーパミン分泌」が少なくなる。
あらかじめ、
「作業前」に、この作業が午前中に終えたら、
「お昼ご飯」は、いつもより「豪華」にしよう
などと決めておくことが「ポイント」。
「作業前」の「目標達成=報酬ゲット」という関係性を明確化することで、
モチベーションが上がり、「ドーパミン分泌」に繋がりやすい。
「運動」によって分泌される「ドーパミン」は「脳」をスッキリにする
「ドーパミン」を簡単に「分泌」させる「方法」には、
「運動」がある。
運動の調節に関わる「脳の部位」が、
「ドーパミン神経系」にもなっている。
「ドーパミン神経系」は、
「A10神経系」に加え「A9神経系」も重要な役割を持っている。
「A9神経系」と呼ばれる「黒質緻密部」から、
「大脳基底核(尾状核・線条体)に投影する経路のこと。
「運動の調節」には、 「A9神経系」も関わっており、
「運動」によって「ドーパミン」が分泌されるようになっている。
「運動」をした後に、
「身体」が疲れていても、「頭」がスッキリとしている感覚を
感じた人も多いはず。
「ドーパミン」によって、
頭が非常にスッキリとしているので、
意外と、「運動後」の「仕事」「勉強」は、適しているとも言われている。
「運動」は、
「ドーパミン」だけでなく、
「集中力」「想像力」を高める脳内物質「アセチルコリン」も分泌する。
「セロトニン」も活性化する。
少しハードな運動をすると、
「脳内麻薬」と言われる「エンドルフィン」も分泌される。
「運動」は、「脳」にとって、良いことが多い。
「30分」を越える「有酸素運動」では、
「脂肪の分解」を促進する「成長ホルモン」も分泌される。
「やる気が上がらない」「モチベーションが上がらない」という人の多くは、
「運動不足」に陥っている「可能性」もあるそう。
「運動」がある。
運動の調節に関わる「脳の部位」が、
「ドーパミン神経系」にもなっている。
「ドーパミン神経系」は、
「A10神経系」に加え「A9神経系」も重要な役割を持っている。
「A9神経系」と呼ばれる「黒質緻密部」から、
「大脳基底核(尾状核・線条体)に投影する経路のこと。
「運動の調節」には、 「A9神経系」も関わっており、
「運動」によって「ドーパミン」が分泌されるようになっている。
「運動」をした後に、
「身体」が疲れていても、「頭」がスッキリとしている感覚を
感じた人も多いはず。
「ドーパミン」によって、
頭が非常にスッキリとしているので、
意外と、「運動後」の「仕事」「勉強」は、適しているとも言われている。
「運動」は、
「ドーパミン」だけでなく、
「集中力」「想像力」を高める脳内物質「アセチルコリン」も分泌する。
「セロトニン」も活性化する。
少しハードな運動をすると、
「脳内麻薬」と言われる「エンドルフィン」も分泌される。
「運動」は、「脳」にとって、良いことが多い。
「30分」を越える「有酸素運動」では、
「脂肪の分解」を促進する「成長ホルモン」も分泌される。
「やる気が上がらない」「モチベーションが上がらない」という人の多くは、
「運動不足」に陥っている「可能性」もあるそう。
「ドーパミン」の分泌を促進する「食べ物」
「ドーパミン」は、
「チロシン」という「アミノ酸」から生成される。
「チロシン」が不足していると、
十分な「ドーパミン」が、体内で製造出来ない可能性がある。
「チロシン」が豊富に含まれている「食べ物」には、
・タケノコ
・鰹節
・肉
・牛乳
・アーモンド
・ピーナッツ
などがある。
「チロシン」を「脳」へと取り込む二は、
「糖質」と一緒に「チロシン」を摂取すると良い。
「糖質」となる「炭水化物」と一緒に摂取すると、
「炭水化物」が「糖質」へと変化し、
「チロシン」と共に「脳」へと届けられる。
「チロシン」が豊富に含まれる「食べ物」は、
「炭水化物」の「ご飯」と一緒に食べると良い。
そして、
「脳内」で「チロシン」から「ドーパミン」を生成するためには、
「ビタミンB6」が必要となる。
「ビタミンB6」が不足していても、
「ドーパミン」が生成されない。
「ビタミンB6」が豊富に含まれる「食べ物」には、
・マグロ
・カツオ
・サケ
・牛乳
・バナナ
などがある。
「ドーパミン」の「生成能力」には、
「限度」があるため、
「大量摂取」をしても、
「1日」に生成される「ドーパミン」の量は限られる。
「チロシン」「糖質」「ビタミンB6」の大量摂取は控える。
「チロシン」という「アミノ酸」から生成される。
「チロシン」が不足していると、
十分な「ドーパミン」が、体内で製造出来ない可能性がある。
「チロシン」が豊富に含まれている「食べ物」には、
・タケノコ
・鰹節
・肉
・牛乳
・アーモンド
・ピーナッツ
などがある。
「チロシン」を「脳」へと取り込む二は、
「糖質」と一緒に「チロシン」を摂取すると良い。
「糖質」となる「炭水化物」と一緒に摂取すると、
「炭水化物」が「糖質」へと変化し、
「チロシン」と共に「脳」へと届けられる。
「チロシン」が豊富に含まれる「食べ物」は、
「炭水化物」の「ご飯」と一緒に食べると良い。
そして、
「脳内」で「チロシン」から「ドーパミン」を生成するためには、
「ビタミンB6」が必要となる。
「ビタミンB6」が不足していても、
「ドーパミン」が生成されない。
「ビタミンB6」が豊富に含まれる「食べ物」には、
・マグロ
・カツオ
・サケ
・牛乳
・バナナ
などがある。
「ドーパミン」の「生成能力」には、
「限度」があるため、
「大量摂取」をしても、
「1日」に生成される「ドーパミン」の量は限られる。
「チロシン」「糖質」「ビタミンB6」の大量摂取は控える。
「ドーパミン」が「過剰分泌」された時の「影響」
「ドーパミン」は、
「大量分泌」されると、
他の「脳内物質」と同様に、
「心身に害」をもたらすことになる。
「ドーパミン」は、
「目標達成」し「報酬」を得ることによって、
「ドーパミン」が、良く分泌されるが、
この行動による「ドーパミン分泌」に依存するようになると、
「依存症」となってしまい、「心身」に「悪影響」となる。
「覚せい剤依存症」「パチンコ依存症」「買い物依存症」などと同様の
「依存症」の「行動パターン」に陥る危険性がある。
「覚せい剤」は、
「ドーパミン」により影響を受ける「側坐核」を直接興奮させてしまう効果がある。
強烈な快楽が得られ、更に強い快楽を求める傾向がある。
その結果、使用量が増え、「依存症」になってしまう。
「快楽」を感じる物は、「依存」しやすいので、
「ドーパミン分泌」による「快楽感」にも注意が必要。
「統合失調症」も、
この20年ほどで、
「ドーパミン」の異常により、引き起こされることがわかってきているそう。
「統合失調症」のうち
・「陽性症状(幻覚や妄想などの症状)」は、「中脳辺緑系の障害」
・「陰性症状(感情の平板化・自発性の低下といった症状)」は、「中脳皮質系の障害」
によって引き起こされるそう。
上記の「統合失調症の症状」には、
「選択的ドーパミン遮断薬」が開発され、処方されているそう。
「パーキンソン病」は、
「運動調節」にかかわる「A9神経系」の「障害」だとされ、
「大脳基底核」で「ドーパミン」が不足した状態となるそう。
「細かな運動調節」が出来なくなり、
動きが少なくなり、「手」「指」が震え、「歩行障害」「無表情」などの症状が出る。
「ドーパミン」を含めた「脳内物質」は、
過不足なく、適度な量が生成されることで、
「脳」が正常に機能することがわかっているそう。
「大量分泌」されると、
他の「脳内物質」と同様に、
「心身に害」をもたらすことになる。
「ドーパミン」は、
「目標達成」し「報酬」を得ることによって、
「ドーパミン」が、良く分泌されるが、
この行動による「ドーパミン分泌」に依存するようになると、
「依存症」となってしまい、「心身」に「悪影響」となる。
「覚せい剤依存症」「パチンコ依存症」「買い物依存症」などと同様の
「依存症」の「行動パターン」に陥る危険性がある。
「覚せい剤」は、
「ドーパミン」により影響を受ける「側坐核」を直接興奮させてしまう効果がある。
強烈な快楽が得られ、更に強い快楽を求める傾向がある。
その結果、使用量が増え、「依存症」になってしまう。
「快楽」を感じる物は、「依存」しやすいので、
「ドーパミン分泌」による「快楽感」にも注意が必要。
「統合失調症」も、
この20年ほどで、
「ドーパミン」の異常により、引き起こされることがわかってきているそう。
「統合失調症」のうち
・「陽性症状(幻覚や妄想などの症状)」は、「中脳辺緑系の障害」
・「陰性症状(感情の平板化・自発性の低下といった症状)」は、「中脳皮質系の障害」
によって引き起こされるそう。
上記の「統合失調症の症状」には、
「選択的ドーパミン遮断薬」が開発され、処方されているそう。
「パーキンソン病」は、
「運動調節」にかかわる「A9神経系」の「障害」だとされ、
「大脳基底核」で「ドーパミン」が不足した状態となるそう。
「細かな運動調節」が出来なくなり、
動きが少なくなり、「手」「指」が震え、「歩行障害」「無表情」などの症状が出る。
「ドーパミン」を含めた「脳内物質」は、
過不足なく、適度な量が生成されることで、
「脳」が正常に機能することがわかっているそう。
Back
「ノルアドレナリン」とは
「ノルアドレナリン」は、
「闘争」と「逃走」の「ホルモン」と呼ばれている。
「闘うか」「逃げるか」という「選択」「行動」が求められる「危機的な状況」で分泌される「脳内物質」。
「恐怖」を感じた時に、最も分泌される。
性格には、「ストレス」を感じた時に分泌される「ホルモン」。
「短期集中」的に、普段以上の実力が出るのに関与している。
「注意」「集中」「覚醒」「判断」「ワーキングメモリ」「鎮痛」などの
「脳の働き」に関連している。
「ノルアドレナリン」の「長期的な分泌」は、「うつ病」の原因とも言われている。
「ノルアドレナリン型のモチベーション」は、「半年」「1年」ほどで必ず「破綻」する。
燃え尽き、「うつ病」になる人も多い。
「ノルアドレナリン」の「効果」は、「短期間」で、
「恐怖」「ストレス」などにより、「モチベーション」を上げるのは、
長くて「1年」ぐらいが限界と言われている。
それ以上は、「疲労」が蓄積し、「効率」はダウンする。
「ノルアドレナリン」が「生成」される「場所」
「ノルアドレナリン」は、
「アミノ酸」を原料に生成される「カテコールアミンの1種」。
「ホルモン」として「副腎髄質」から「血液」に放出される。
「副腎」は、
「腎臓」の隣りにある「ホルモン」を分泌する「器官」。
「副腎髄質」は、「副腎」の一部。
「ノルアドレナリン」は、
「シナプス伝達」において、
「ノルアドレナリン作動性ニューロン」から放出される「神経伝達物質」でもある。
「脳幹(橋)」にある「神経核」の1つで、
「青斑核」から、「視床下部」「大脳辺緑系」「大脳皮質」などに投射することで、
「注意」「集中」「覚醒」「判断」「ワーキングメモリ」「鎮痛」などの
「脳の働き」に関連している。
「アミノ酸」を原料に生成される「カテコールアミンの1種」。
「ホルモン」として「副腎髄質」から「血液」に放出される。
「副腎」は、
「腎臓」の隣りにある「ホルモン」を分泌する「器官」。
「副腎髄質」は、「副腎」の一部。
「ノルアドレナリン」は、
「シナプス伝達」において、
「ノルアドレナリン作動性ニューロン」から放出される「神経伝達物質」でもある。
「脳幹(橋)」にある「神経核」の1つで、
「青斑核」から、「視床下部」「大脳辺緑系」「大脳皮質」などに投射することで、
「注意」「集中」「覚醒」「判断」「ワーキングメモリ」「鎮痛」などの
「脳の働き」に関連している。
「ノルアドレナリン」が「分泌」された時の「影響」
「ノルアドレナリン」が、分泌されることで、
「心拍数」が高まり、「脳」「骨格筋」に「血液」が行き渡る。
「闘争」「逃走」のどちらを選択するにしても、
「瞬発的な行動」が取れるようにし、
「脳」「身体」を準備状態に持っていくのが、「ノルアドレナリンの役割」。
「ノルアドレナリン」により、
「覚醒度」「集中度」がアップし、
「正しい判断」が「瞬間的」にできるようになり、
「脳」の機能が大きくアップする。
「ノルアドレナリン」は、
「アドレナリン」と共に、「闘争」「逃走」についての「反応」を生じさせる。
「心拍数」を直接増加させるように、「交感神経系」を作動させ、
「脂肪」を「エネルギー」へと変換し、「筋肉の素早さ」を増加させる働きがある。
「心拍数」が高まり、「脳」「骨格筋」に「血液」が行き渡る。
「闘争」「逃走」のどちらを選択するにしても、
「瞬発的な行動」が取れるようにし、
「脳」「身体」を準備状態に持っていくのが、「ノルアドレナリンの役割」。
「ノルアドレナリン」により、
「覚醒度」「集中度」がアップし、
「正しい判断」が「瞬間的」にできるようになり、
「脳」の機能が大きくアップする。
「ノルアドレナリン」は、
「アドレナリン」と共に、「闘争」「逃走」についての「反応」を生じさせる。
「心拍数」を直接増加させるように、「交感神経系」を作動させ、
「脂肪」を「エネルギー」へと変換し、「筋肉の素早さ」を増加させる働きがある。
「ノルアドレナリン」と「アドレナリン」の違い
「ノルアドレナリン」と「アドレナリン」は、
「闘争」「逃走」において、異なる部位に機能する。
「ノルアドレナリン」は、
一部は、「視床下部」「大脳辺緑系」「大脳皮質」へ作用し、
残りの一部と共に、
「注意」「集中力」「覚醒度」「判断力」「ワーキングメモリ」「鎮痛」
の「能力」を「向上」させる作用がある。
残った一部は、「アドレナリン」と同じ効果を見せる。
「アドレナリン」は、
分泌された後に、
「筋力」「瞬発力」「心臓・血管系」「記憶力」
などの「能力」を「向上」させる作用がある。
「ノルアドレナリン」の一部と
同じ「闘争」「逃走」を担う「脳内物質」だが、
異なる部位を担当している。
「闘争」「逃走」において、異なる部位に機能する。
「ノルアドレナリン」は、
一部は、「視床下部」「大脳辺緑系」「大脳皮質」へ作用し、
残りの一部と共に、
「注意」「集中力」「覚醒度」「判断力」「ワーキングメモリ」「鎮痛」
の「能力」を「向上」させる作用がある。
残った一部は、「アドレナリン」と同じ効果を見せる。
「アドレナリン」は、
分泌された後に、
「筋力」「瞬発力」「心臓・血管系」「記憶力」
などの「能力」を「向上」させる作用がある。
「ノルアドレナリン」の一部と
同じ「闘争」「逃走」を担う「脳内物質」だが、
異なる部位を担当している。
「ノルアドレナリン」の「生成」
「ノルアドレナリン」の生成には、
「必須アミノ酸」の「フェニルアラニン」が不可欠。
生成を補助する成分には、「ビタミンC」があり、
こちらも「必要不可欠」。
「1日の生成量」が限られているので、
「フェニルアラニン」を大量摂取しても、
「ノルアドレナリン」が大きく増えることはない。
適度な量を摂取するのが良い。
「不足」すると、「機能低下」を引き起こすが、
「過剰」だと、何の変化もない。
「フェニルアラニン」は、
・肉類
・魚介類
・大豆製品
・かぼちゃ
・卵
・乳製品
・チーズ
・ナッツ類(アーモンドや落花生など)
などに多く含まれている。
「ビタミンC」は、
一度に、過剰な量を摂取すると、
体外に排出されてしまうので、
適度に定期的な摂取が必要。
「必須アミノ酸」の「フェニルアラニン」が不可欠。
生成を補助する成分には、「ビタミンC」があり、
こちらも「必要不可欠」。
「1日の生成量」が限られているので、
「フェニルアラニン」を大量摂取しても、
「ノルアドレナリン」が大きく増えることはない。
適度な量を摂取するのが良い。
「不足」すると、「機能低下」を引き起こすが、
「過剰」だと、何の変化もない。
「フェニルアラニン」は、
・肉類
・魚介類
・大豆製品
・かぼちゃ
・卵
・乳製品
・チーズ
・ナッツ類(アーモンドや落花生など)
などに多く含まれている。
「ビタミンC」は、
一度に、過剰な量を摂取すると、
体外に排出されてしまうので、
適度に定期的な摂取が必要。
「理想」の働き方は、「ノルアドレナリン」と「ドーパミン」を使い分ける
「ノルアドレナリン」は、
「恐怖」「ストレス」により、「ノルアドレナリン」が分泌され、
短期間だが、
「注意」「集中」「覚醒」「判断」「ワーキングメモリ」「鎮痛」
などの能力が向上する。
「ドーパミン」は、
「快楽」を得ると分泌され、
「目標」をたて、「目標達成」をしたときの「快楽」を感じると、
「ドーパミン」がより多く分泌される。
さらに快楽を獲得しようという欲求も強くなる傾向がある。
「不快」を避けるモチベーションの「ノルアドレナリン」と、
「快適」を求めるモチベーションの「ドーパミン」を
使い分けることで、
恒常的な行動に結びつくようになる。
「恐怖」「ストレス」により、「ノルアドレナリン」が分泌され、
短期間だが、
「注意」「集中」「覚醒」「判断」「ワーキングメモリ」「鎮痛」
などの能力が向上する。
「ドーパミン」は、
「快楽」を得ると分泌され、
「目標」をたて、「目標達成」をしたときの「快楽」を感じると、
「ドーパミン」がより多く分泌される。
さらに快楽を獲得しようという欲求も強くなる傾向がある。
「不快」を避けるモチベーションの「ノルアドレナリン」と、
「快適」を求めるモチベーションの「ドーパミン」を
使い分けることで、
恒常的な行動に結びつくようになる。
| ノルアドレナリン型モチベーション |
「恐怖」「ストレス」「叱責」などの「不快」を避けるために努力する動機。 短い期間の継続に向いている。 |
| ドーパミン型モチベーション |
「楽しさ」「ご褒美」「褒められる」などの「快楽」「報酬」を求めて努力する動機。 長期間の継続に向いている。 |
「適度なストレス」をたまに受けると「仕事」の「効率」「質」を高める
「脳」は、
「軽いストレス」を受けると、
「適度」な「ノルアドレナリン」が分泌され、
「適度」な「興奮」を即し、
「判断能力」が向上する。
そのことにより、「仕事」などの「効率性」「質」が向上する効果がある。
ちょっとした記憶などをする「ワーキングメモリ」は、
「脳」の前部にある「前頭前野」で行われる。
「前頭前野」は、
「人の脳」で、最も発達している部位で、
「大脳皮質」の「約30%」を占めている。
「前頭前野」は、「人間の人間らしさをつかさどる部位」として知られる。
・思考する
・意思決定する
・行動を抑制する
・感情を制御する
・コミュニケーションを取る
などの、人としての重要な行動の大部分を判断している。
「前頭前野」には、
「ドーパミン」「セロトニン」「ノルアドレナリン」の神経も分布している。
適度に「ノルアドレナリン」を分泌することで、
「前頭前野」の「ワーキングメモリ」も活性化する。
過剰に「ノルアドレナリン」が分泌すると、
「前頭前野」の「ワーキングメモリ」は、機能しなくなる傾向がある。
「適度なストレス」を感じているぐらいで、
分泌される「ノルアドレナリン」が、「注意力」「集中力」を高め、
「ワーキングメモリ」を活性化し、「頭の回転」を速める。
「仕事」の「効率」「質」を高めることに繋がる。
「軽いストレス」を受けると、
「適度」な「ノルアドレナリン」が分泌され、
「適度」な「興奮」を即し、
「判断能力」が向上する。
そのことにより、「仕事」などの「効率性」「質」が向上する効果がある。
ちょっとした記憶などをする「ワーキングメモリ」は、
「脳」の前部にある「前頭前野」で行われる。
「前頭前野」は、
「人の脳」で、最も発達している部位で、
「大脳皮質」の「約30%」を占めている。
「前頭前野」は、「人間の人間らしさをつかさどる部位」として知られる。
・思考する
・意思決定する
・行動を抑制する
・感情を制御する
・コミュニケーションを取る
などの、人としての重要な行動の大部分を判断している。
「前頭前野」には、
「ドーパミン」「セロトニン」「ノルアドレナリン」の神経も分布している。
適度に「ノルアドレナリン」を分泌することで、
「前頭前野」の「ワーキングメモリ」も活性化する。
過剰に「ノルアドレナリン」が分泌すると、
「前頭前野」の「ワーキングメモリ」は、機能しなくなる傾向がある。
「適度なストレス」を感じているぐらいで、
分泌される「ノルアドレナリン」が、「注意力」「集中力」を高め、
「ワーキングメモリ」を活性化し、「頭の回転」を速める。
「仕事」の「効率」「質」を高めることに繋がる。
Back
「アドレナリン」とは
「アドレナリン」は、
「恐怖」「不安」を感じた時に、
「交感神経」からの指令を受けて、
「副腎髄質」から分泌される。
「闘争」「逃走」を助ける「ホルモン」の1つ。
「アドレナリン」の「影響」「効果」
「アドレナリン」が、
「血液中」に放出されると、
「心拍数」「血圧」が高まり、
「筋肉」に「血液」が行き渡る。
「血糖」を高め、「瞳孔」が開き、
「覚醒度」を上げる。
「注意力」「集中力」が高まり、
「身体」「脳」が、「臨戦態勢」の状態になる。
「ノルアドレナリン」と似ている「効果」があるが、
異なる部位に作用する、まったく異なる「ホルモン」。
「ノルアドレナリン」は、
主に「脳」「神経系」を中心に作用する。
「アドレナリン」は、
「脳」以外の「身体」の「臓器」に作用する。
特に、「心臓」「筋肉」を中心に、影響を与える。
「アドレナリン」「ノルアドレナリン」「ドーパミン」は、
いずれも、「興奮系の神経伝達物質」で、相互に密接な関係がある。
「アドレナリン」の「効果」には、
・「身体機能」「筋力」などを、一時的にパワーアップさせる(身体に対する効果)
・「集中力」「判断力」を高める(脳の機能に対する効果)
の2つがある。
「血液中」に放出されると、
「心拍数」「血圧」が高まり、
「筋肉」に「血液」が行き渡る。
「血糖」を高め、「瞳孔」が開き、
「覚醒度」を上げる。
「注意力」「集中力」が高まり、
「身体」「脳」が、「臨戦態勢」の状態になる。
「ノルアドレナリン」と似ている「効果」があるが、
異なる部位に作用する、まったく異なる「ホルモン」。
「ノルアドレナリン」は、
主に「脳」「神経系」を中心に作用する。
「アドレナリン」は、
「脳」以外の「身体」の「臓器」に作用する。
特に、「心臓」「筋肉」を中心に、影響を与える。
「アドレナリン」「ノルアドレナリン」「ドーパミン」は、
いずれも、「興奮系の神経伝達物質」で、相互に密接な関係がある。
「アドレナリン」の「効果」には、
・「身体機能」「筋力」などを、一時的にパワーアップさせる(身体に対する効果)
・「集中力」「判断力」を高める(脳の機能に対する効果)
の2つがある。
「アドレナリン」の「生成」
「アドレナリン」は、
・チロシン
↓
・L-DOPA
↓
・ドーパミン
↓
・ノルアドレナリン
↓
・アドレナリン
↓
・L-DOPA
↓
・ドーパミン
↓
・ノルアドレナリン
↓
・アドレナリン
という過程で生成される。
「ノルアドレナリン」を経て、
「副腎髄質」にて、「アドレナリン」に変換される。
「アドレナリン」は、
「副腎」からのみ「生成」される。
「ノルアドレナリン」は、
「副腎」で「生成」されるのと他に、
「交感神経端末」からも分泌される。
「アドレナリン」「ノルアドレナリン」の「受容体」は、
「脳」だけでなく、
「身体」の全体に存在する。
「受容体」の「分布割合」は、
「ノルアドレナリン」が、「脳」に一番多く分布していて、
「アドレナリン」は、「全身の臓器」に分布し、
特に、「心筋」「平滑筋」などの「筋肉」に多い。
「アドレナリン」が、
「心臓」「筋肉」を中心に作用するのは、
「受容体」が多く分布しているから。
「アドレナリン」を分泌する「方法」
「アドレナリン」を分泌する「方法」には、
・「不安」「恐怖」を感じた時
・「危険」を感じた時
・「怒り」を感じた時
・「ストレス」を感じた時
・「興奮」した時
・「大きな声」をかなり出す
などの方法がある。
意識的に、
「アドレナリン」を分泌するには、
「行動」をするか、「環境」に身を置くかという選択肢になる。
「アドレナリン」の「影響」
「アドレナリン」が分泌されると、
・緊急時の対応力向上
・パフォーマンスの向上
・筋肉増強効果
・気分が高揚する
・心臓の動悸が激しくなる
・「脳」「身体」を「臨戦態勢」にする
・「心拍数」「血圧」の上昇
・「気管支」の拡張
・「血糖値」の上昇
・「筋肉」への「血流増加」
・「脳」への「血流増加」
などの効果がある。
「過剰分泌」されると、
・「筋肉」が硬直する
・思うように動けない
・自己制御が出来ない
・興奮しすぎる
・頭がボーっとする
・手に汗をかく
・脇汗が多くなる
・攻撃性が増す
・冷静さを失う ・暴走をする
・考えることが出来なくなる
・「心臓疾患」「脳卒中」「糖尿病」「癌」などの原因となる
・「うつ病」の原因となる
などの「悪影響」もある。
「アドレナリン」を夜に「分泌」させない「方法」
「アドレナリン」を「オフ」にして、
「脳」と「身体」をリフレッシュするには、
「交感神経」から「副交感神経」を優位にする必要がある。
「睡眠」までの「2時間~3時間」の過ごし方が大切らしい。
・「興奮」することをしない
・「お風呂」「シャワー」の「温度」を高くしすぎない
・「激しい運動」をしない
・遅くまで「仕事」をしない
・気持ちを「リラックス」できる時間を持つ
・「家族」「友達」と過ごす
・「休息」を意識する
Back
「セロトニン」とは
「セロトニン」は、
「睡眠」と「覚醒」をコントロールする「脳内物質」。
「癒しの物質」とも言われる。
「セロトニンの幸福感」は、
「安らぎ」「くつろぎ」といった「穏やかな感情」。
「セロトニン神経系」は、
・「延髄」の「縫線核」から「大脳皮質」
・「情動」の中枢となる「大脳辺緑系」
・「生命維持」をつかさどる「視床下部」「脳幹」「小脳」「脊髄」
などの、
「脳」のほとんどの領域に存在する。
「セロトニン」が「分泌」される「主な場所」
「セロトニン」は、
主に「脳」の「縫線核 (ほうせんかく)」という特定の部位で生成されている。
「縫線核 (ほうせんかく)」は、
「脳幹」と呼ばれる「脳の最も古い部分」に位置していて、
「呼吸」や「心拍数」など、「生命維持」に「重要な機能」を「コントロール」している「場所」。
主に「脳」の「縫線核 (ほうせんかく)」という特定の部位で生成されている。
「縫線核 (ほうせんかく)」は、
「脳幹」と呼ばれる「脳の最も古い部分」に位置していて、
「呼吸」や「心拍数」など、「生命維持」に「重要な機能」を「コントロール」している「場所」。
「セロトニン」の「影響」
「ドーパミン」「ノルアドレナリン」「アドレナリン」などの
「興奮系脳内物質」の「過剰分泌」を抑制し、
「脳内物質」の「バランス」を取る「調節物質」。
「セロトニン」が「活性化」された状態だと、
「心が安定した状態」になるが、
「セロトニン」が不足すると、
「イライラ」「むしゃくしゃ」「落ち着かない」「不安」
などを感じるようになる。
「気持ち」「気分」の切替は、「前頭前野」の働き。
その機能を円滑に動かしているのが「セロトニン」。
「興奮系脳内物質」の「過剰分泌」を抑制し、
「脳内物質」の「バランス」を取る「調節物質」。
「セロトニン」が「活性化」された状態だと、
「心が安定した状態」になるが、
「セロトニン」が不足すると、
「イライラ」「むしゃくしゃ」「落ち着かない」「不安」
などを感じるようになる。
「気持ち」「気分」の切替は、「前頭前野」の働き。
その機能を円滑に動かしているのが「セロトニン」。
「セロトニン」の「合成」と「分泌」
「セロトニン」の「生成」には、
「必須アミノ酸」の1つ「トリプトファン」から生成されている。
「ビタミンB6」を使って、
「トリプトファン」から「セロトニン」を合成する。
「ビタミンB6」も必須。
「セロトニン」の「合成」と「分泌」は、
「日の出」と共に盛んになり、
「午後から夜」にかけて、低下する。
「深い睡眠状態」の眼球運動がない睡眠状態「ノンレム睡眠」では、
「セロトニン」は、まったく分泌されない。
「人の身体」は、
「太陽の光」が、「網膜」から「縫線核」に伝達されることで、
「セロトニン」の「合成」が開始される。
合成された「セロトニン」から、神経内の情報伝達「インパルス」が、
「脳全体」に行き渡り、「脳」をスッキリとした「覚醒状態」にする。
「太陽の光刺激」により「セロトニン」が「生成」「活性化」することで、
「脳」の全体が、活動をスタートさせるようになっている。
「セロトニン」によって、快適な「1日」が始まる。
「セロトニン」が不足すると、
「気分」が「憂鬱」になり、
「活力」もなくなり、何もしたくない状態に陥る。
「布団から出られない」「まだ寝ていたい」という状態が、
「セロトニン神経」が弱っている「状態」。
「セロトニン」の分泌が悪化すると「うつ病」にも繋がる。
「朝」に、
「スッキリ」と起きるには、
「朝日」が部屋に差し込むようにしておくだけ。
「朝日」が差し込んで、
「脳」が「朝日の光」を認識すると「セロトニン分泌」が始まり、
ある程度の「セロトニン」が分泌されたら、
スッキリと目覚める事ができる。
女性の1人暮らしなどなら、
「照度2500ルクス以上の光」を「5分以上浴びる」ことで、
「太陽の光」と同等の影響を受けることができ、
「セロトニンの生成」も始まる。
「朝の太陽光」は、
「照度2500ルクス以上の光」と同じぐらいなので、
「太陽光」の代わりになる。
だが、「家庭用蛍光灯の光」は、「照度100ルクス~500ルクス」ほど。
「朝」に起きたら、「カーテン」を少しでも開けて、
「5分間」ほど、ゴロゴロと過ごしておけば良い。
「必須アミノ酸」の1つ「トリプトファン」から生成されている。
「ビタミンB6」を使って、
「トリプトファン」から「セロトニン」を合成する。
「ビタミンB6」も必須。
「セロトニン」の「合成」と「分泌」は、
「日の出」と共に盛んになり、
「午後から夜」にかけて、低下する。
「深い睡眠状態」の眼球運動がない睡眠状態「ノンレム睡眠」では、
「セロトニン」は、まったく分泌されない。
「人の身体」は、
「太陽の光」が、「網膜」から「縫線核」に伝達されることで、
「セロトニン」の「合成」が開始される。
合成された「セロトニン」から、神経内の情報伝達「インパルス」が、
「脳全体」に行き渡り、「脳」をスッキリとした「覚醒状態」にする。
「太陽の光刺激」により「セロトニン」が「生成」「活性化」することで、
「脳」の全体が、活動をスタートさせるようになっている。
「セロトニン」によって、快適な「1日」が始まる。
「セロトニン」が不足すると、
「気分」が「憂鬱」になり、
「活力」もなくなり、何もしたくない状態に陥る。
「布団から出られない」「まだ寝ていたい」という状態が、
「セロトニン神経」が弱っている「状態」。
「セロトニン」の分泌が悪化すると「うつ病」にも繋がる。
「朝」に、
「スッキリ」と起きるには、
「朝日」が部屋に差し込むようにしておくだけ。
「朝日」が差し込んで、
「脳」が「朝日の光」を認識すると「セロトニン分泌」が始まり、
ある程度の「セロトニン」が分泌されたら、
スッキリと目覚める事ができる。
女性の1人暮らしなどなら、
「照度2500ルクス以上の光」を「5分以上浴びる」ことで、
「太陽の光」と同等の影響を受けることができ、
「セロトニンの生成」も始まる。
「朝の太陽光」は、
「照度2500ルクス以上の光」と同じぐらいなので、
「太陽光」の代わりになる。
だが、「家庭用蛍光灯の光」は、「照度100ルクス~500ルクス」ほど。
「朝」に起きたら、「カーテン」を少しでも開けて、
「5分間」ほど、ゴロゴロと過ごしておけば良い。
「セロトニン」の材料となる必須アミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれる「食べ物」
・肉
・大豆
・米
・乳製品
・大豆
・米
・乳製品
「セロトニン生成」に必要な「ビタミンB6」が豊富に含まれる「食べ物」
・牛肉
・豚肉
・鶏のレバー
・魚の赤身
・ピスタチオ
・ごま
・ピーナッツなどの「種実類」
・バナナ
・ニンニク
など。
・豚肉
・鶏のレバー
・魚の赤身
・ピスタチオ
・ごま
・ピーナッツなどの「種実類」
・バナナ
・ニンニク
など。
「セロトニン」を「活性化」する「方法」
・「太陽の光」を浴びる
・「リズム運動」をする
・「咀嚼」する
・「深呼吸」する
・「音読」をする
・「運動」をする
・「リズム運動」をする
・「咀嚼」する
・「深呼吸」する
・「音読」をする
・「運動」をする
Back
「メラトニン」とは
「メラトニン」は、
「1958年」に発見された
「睡眠」と「覚醒」を調整する「ホルモン」。
「メラトニン」は、
その性質から「睡眠物質」「眠りを誘うホルモン」などと呼ばれることもある。
「メラトニン」の「影響」
「脳神経」だけでなく、
「脈拍」「体温」「血圧」を低下させる事で、
「睡眠」と「覚醒」のリズムを調整し、
「自然な睡眠」へと誘導する作用がある。
「全身の臓器」を「休息モード」へと切り替えることができる。
「メラトニン」は、
「睡眠促進物質」と同時に、重要な「細胞修復物質」でもある。
「老化防止効果」「抗腫瘍効果」「腫瘍増殖抑制作用」
「血管新生抑制作用」「DNA修復作用」
などもある。
「老化防止効果」もあり、強力な「抗酸化作用」も有する。
「抗酸化作用」が強い物質として知られる「ビタミンE」の
「2倍」の「抗酸化作用」を「メラトニン」は、持っている。
「メラトニン」が、「夜間」にしっかりと分泌されると、
「病気」のリスクが減少し、「老化防止」になると言われている。
「脈拍」「体温」「血圧」を低下させる事で、
「睡眠」と「覚醒」のリズムを調整し、
「自然な睡眠」へと誘導する作用がある。
「全身の臓器」を「休息モード」へと切り替えることができる。
「メラトニン」は、
「睡眠促進物質」と同時に、重要な「細胞修復物質」でもある。
「老化防止効果」「抗腫瘍効果」「腫瘍増殖抑制作用」
「血管新生抑制作用」「DNA修復作用」
などもある。
「老化防止効果」もあり、強力な「抗酸化作用」も有する。
「抗酸化作用」が強い物質として知られる「ビタミンE」の
「2倍」の「抗酸化作用」を「メラトニン」は、持っている。
「メラトニン」が、「夜間」にしっかりと分泌されると、
「病気」のリスクが減少し、「老化防止」になると言われている。
「メラトニン」が「生成」される「場所」
「メラトニン」を分泌するのは、「脳の松果体」という部分。
「松果体」は、「網膜」が受ける「光の量の情報」をもとに、
「メラトニン」の「分泌量」を決定する。
「目に入る光の量」が減少すると、
それを検知した「松果体」が「メラトニン」を分泌する。
「メラトニン」は、
「昼間」に比べ、「夜間」の分泌量は、「5倍〜10倍」も多く生産される。
「メラトニン」は、「セロトニン」から生成される。
「松果体」は、「網膜」が受ける「光の量の情報」をもとに、
「メラトニン」の「分泌量」を決定する。
「目に入る光の量」が減少すると、
それを検知した「松果体」が「メラトニン」を分泌する。
「メラトニン」は、
「昼間」に比べ、「夜間」の分泌量は、「5倍〜10倍」も多く生産される。
「メラトニン」は、「セロトニン」から生成される。
「メラトニン」の「生成過程」
・トリプトファン
↓
・セロトニン
↓
・メラトニン
↓
・セロトニン
↓
・メラトニン
「メラトニン」を出す方法
・部屋を真っ暗にして眠る
・睡眠前に、「薄暗い部屋」でリラックスする
・睡眠前に、「蛍光灯の光」を浴びない
・睡眠前に、「ゲーム」「スマートフォン」「パソコン」をしない
・日中に「セロトニン」を活性化させておく(「セロトニン」が「メラトニン」の原料)
・「朝」に、「太陽の光」を浴びる
・睡眠前に、「薄暗い部屋」でリラックスする
・睡眠前に、「蛍光灯の光」を浴びない
・睡眠前に、「ゲーム」「スマートフォン」「パソコン」をしない
・日中に「セロトニン」を活性化させておく(「セロトニン」が「メラトニン」の原料)
・「朝」に、「太陽の光」を浴びる
Back
「アセチルコリン」とは
「アセチルコリン」は、
「認知機能」と「ひらめき」を高める効果を持つ。
「神経伝達物質」の一つで、
「記憶」や「学習」「筋肉の動き」など、様々な「身体機能」に関わっている。
「アセチルコリン」の「分泌」を促すには、
| 規則正しい生活 | 「睡眠」をしっかりと取り、「バランスの取れた食事」を心がけることが大切。 |
| 適度な運動 | 「運動」は、「脳」の血流を改善し、「神経細胞」の活性化を促進する。 |
| ストレス解消 | 「ヨガ」「瞑想」など、「リラックス」できる時間を設けることがおすすめ。 |
| 学習 | 「新しいこと」を学ぶことは、「脳」を活性化させ、「アセチルコリン」の分泌を促進する。 |
などがある。
これらの習慣を続けることで、「アセチルコリン」の分泌を促進し、
「記憶力」や「学習能力」の向上に繋げることができる。
「アセチルコリン」が「生成」される「場所」
「脳」のほぼ真ん中に左右対称に存在する
「側坐核の神経細胞」が活動すると「やる気」が出る。
「側坐核の神経細胞」は、
ある程度の刺激が来ないと活動ぢないので、
頑張って作業を始めることで、「側坐核」の刺激となり、
「側坐核」が自己興奮し、「アセチルコリン」が分泌される。
「やる気」が出ない時は、「とりあえず始める」というのは、
「脳科学的」には正しい行動と言えるらしい。
「側坐核の神経細胞」が活動すると「やる気」が出る。
「側坐核の神経細胞」は、
ある程度の刺激が来ないと活動ぢないので、
頑張って作業を始めることで、「側坐核」の刺激となり、
「側坐核」が自己興奮し、「アセチルコリン」が分泌される。
「やる気」が出ない時は、「とりあえず始める」というのは、
「脳科学的」には正しい行動と言えるらしい。
「アセチルコリン」が、よく「分泌」される「状況」
「アセチルコリン」が、よく「分泌」される「状況」には、
| 状況 | 説明 |
|---|---|
| 学習や記憶の形成時 |
「新しいこと」を学んだり、「記憶」を定着させようとする時、脳内の「アセチルコリンの分泌」が活発になる。 「脳の海馬」の部分が特に活性化し、「アセチルコリン」が、「神経細胞間の情報」を伝達しやすくし、「記憶の形成」を促す。 |
| 集中している時 |
一つのことに「集中」して取り組んでいる時、 「脳」は、「アセチルコリン」を分泌し、「注意力」を高め、「効率よく情報を処理」できるようにする。 問題を解いたり、本を読んだりする時など、「集中力」が求められる場面で、「アセチルコリン」の分泌が活発になる。 |
| 睡眠中 |
「睡眠中」も、「脳」は活発に活動しており、記憶の整理や学習した内容の定着が行われる。 この時、「アセチルコリン」は、「レム睡眠」の時に、特に多く分泌され、 夢を見たり、創造性を高める働きをしていると考えられる。 「レム睡眠」の時は、「脳波」が覚醒時と似た状態になり、「脳」が活発に活動していることがわかる。 |
| ストレスを感じている時 |
「ストレス」を感じると、身体は、「自律神経」のバランスが崩れ、「交感神経」が優位になる。 この時、「アセチルコリン」の分泌量が変化し、「心拍数の上昇」や「血圧の上昇」など、様々な生理反応を引き起こす。 「ストレス」の種類や程度によって、「アセチルコリン」の分泌量が変化する。 |
| 筋肉の収縮時 |
「アセチルコリン」は、「神経」と「筋肉」の接合部で、「神経」から「筋肉」へ「信号」を伝える役割を担っている。 そのため、「筋肉」を動かす時、つまり体を動かしたり運動をする時、「アセチルコリン」が分泌される。 「神経」からの信号が「筋肉」に伝わり、「筋肉」が収縮する「仕組み」には、「アセチルコリン」が深く関わっている。 |
「アセチルコリン」の「影響」
「アセチルコリン」は、神経伝達物質の一種で、
「脳」の様々な機能に関わっている。
「アセチルコリン」が分泌されると、
などの影響がある。
「アセチルコリン」は、
・「副交感神経」の「節前」「節後線維(副交感神経の興奮)」
・「交感神経」の「節前線維(交感神経の抑制)」
・「運動神経」の「伝達物質」
としての役割を持っている。
「交感神経」が興奮すると「アドレナリン」が分泌される。
その「アドレナリン」を「アセチルコリン」が制御する。
他にも、
「アセチルコリン」は、
「前脳基底部(マイネルト基底核・内側中隔核)」から、
「大脳皮質」「大脳辺緑系」「視床」などに投射し、
「認知機能(思考・記憶・学習・注意力・集中力)」「覚醒と睡眠(特にレム睡眠)」
「シータ波の発生」「情動記憶」などの機能もになっている。
「認知機能」「ひらめき」「作業効率」「創造力」「発想力」などに関わる「脳内物質」。
「アセチルコリン」を「コントロール」できると、
「仕事がはかどる」「ひらめきを得る」などといった「メリット」が得られる。
「睡眠中」にも、「アセチルコリン」の分泌が高まり、
「脳」「身体」に「休息」を促進する。
「シータ波」が生み出され、「シナプス」が繋がりやすくなり、
「記憶」が定着しやすくなる。
「シナプス」が繋がった時に、「奇抜なアイデア」が生まれる。
「シータ波」が出ると、「アイデア」が出やすくなり、「奇抜なアイデア」が生まれる。
・アセチルコリンの分泌
↓
・「海馬」から「シータ波」が出る
↓
・「記憶力」「発想力」がアップする
「シータ波」を出すことができれば、
「記憶力」を高め、「凄いアイデア」を生み出せる可能性がある。
「シータ波」を出す方法には、
・「昼寝」をする
・「好奇心」を刺激する
・「外出」する
・座ったまま「手足」を動かす
などがある。
「アセチルコリン」が「創造力の源」と言われるのは、
意識的に、1つ1つの記憶が意識的に結びつけられ、
アイデアを絞り出すことではなく、
「アセチルコリン」の働きによって、
「無作為」「偶発的」に、1つ1つの記憶が、
偶然に繋がった時に、浮かび上がってくるものが、「ひらめき」。
「脳」の様々な機能に関わっている。
「アセチルコリン」が分泌されると、
| 中枢神経系での働き | |
|---|---|
| 学習と記憶 |
「アセチルコリン」は、「記憶の形成」や「記憶の想起」に、重要な役割を果たす。 特に、「海馬」と呼ばれる部位での「神経伝達」を促進し、 「新しい情報」を学習したり、 「過去の出来事」を思い出したりするのを補助する。 |
| 注意と覚醒 |
「注意力」を集中させ、「覚醒状態」を維持する働きがある。 |
| 報酬系 |
「報酬系」を「活性化」し、「快感」や「モチベーション」を高める効果も報告されている。 |
| 末梢神経系での働き | |
| 筋肉の収縮 |
「骨格筋の収縮」を促し、「運動機能」を支える。 |
| 自律神経 |
「副交感神経」を刺激し、「心拍数」を低下させたり、「消化活動を促進」したりする。 |
などの影響がある。
「アセチルコリン」は、
・「副交感神経」の「節前」「節後線維(副交感神経の興奮)」
・「交感神経」の「節前線維(交感神経の抑制)」
・「運動神経」の「伝達物質」
としての役割を持っている。
「交感神経」が興奮すると「アドレナリン」が分泌される。
その「アドレナリン」を「アセチルコリン」が制御する。
他にも、
「アセチルコリン」は、
「前脳基底部(マイネルト基底核・内側中隔核)」から、
「大脳皮質」「大脳辺緑系」「視床」などに投射し、
「認知機能(思考・記憶・学習・注意力・集中力)」「覚醒と睡眠(特にレム睡眠)」
「シータ波の発生」「情動記憶」などの機能もになっている。
「認知機能」「ひらめき」「作業効率」「創造力」「発想力」などに関わる「脳内物質」。
「アセチルコリン」を「コントロール」できると、
「仕事がはかどる」「ひらめきを得る」などといった「メリット」が得られる。
「睡眠中」にも、「アセチルコリン」の分泌が高まり、
「脳」「身体」に「休息」を促進する。
「シータ波」が生み出され、「シナプス」が繋がりやすくなり、
「記憶」が定着しやすくなる。
「シナプス」が繋がった時に、「奇抜なアイデア」が生まれる。
「シータ波」が出ると、「アイデア」が出やすくなり、「奇抜なアイデア」が生まれる。
・アセチルコリンの分泌
↓
・「海馬」から「シータ波」が出る
↓
・「記憶力」「発想力」がアップする
「シータ波」を出すことができれば、
「記憶力」を高め、「凄いアイデア」を生み出せる可能性がある。
「シータ波」を出す方法には、
・「昼寝」をする
・「好奇心」を刺激する
・「外出」する
・座ったまま「手足」を動かす
などがある。
「アセチルコリン」が「創造力の源」と言われるのは、
意識的に、1つ1つの記憶が意識的に結びつけられ、
アイデアを絞り出すことではなく、
「アセチルコリン」の働きによって、
「無作為」「偶発的」に、1つ1つの記憶が、
偶然に繋がった時に、浮かび上がってくるものが、「ひらめき」。
「アセチルコリン」の「生成」を促進する方法
「アセチルコリン」の「生成」を促すことは、
「記憶力」「学習能力」の向上に繋がると期待されている。
「アセチルコリン」をより生成するためには、
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 「コリン」を含む食品を食べる |
「アセチルコリン」の原料となる「コリン」を多く含む「食品」を摂取することで、 体内の「コリン濃度」を上げ、結果的に「アセチルコリン」の「生成」を促すことができる。 「コリン」を多く含む食品は、「卵黄」「レバー」「大豆」「魚介類」などがある。 |
| 「ビタミンB群」の摂取 |
「ビタミンB群」、特に「ビタミンB5」は、「アセチルコリンの合成」に重要な役割を果たす。 「レバー」「ナッツ類」「豆類」などに多く含まれる。 |
| 適度な運動 |
「運動」は、「脳の血流」を改善し、「神経細胞の活性化」を促す。 これにより、「アセチルコリンの生成」も促進されると考えられている。 |
| 質の高い睡眠 |
「睡眠不足」は、「脳の機能低下」を引き起こし、「アセチルコリンの生成」を抑制する可能性がある。 |
| ストレスの軽減 |
「ストレス」は、「脳の機能」を低下させ、「アセチルコリンの生成」を阻害する可能性がある。 「ヨガ」「瞑想」などの「リラックス効果」のある活動を取り入れることがおすすめ。 |
| サプリメントの利用 |
「コリン」や「ビタミンB群」を「サプリメント」で補うのも、一つの方法。 |
「アセチルコリン」の原料「レシチン」を豊富に含む「食べ物」
「アセチルコリン」の原料「レシチン」を豊富に含む「食べ物」には、
・卵黄
・大豆
・穀類(特に玄米)
・レバー
・ナッツ
などに多く含まれる。
Back
「エンドルフィン」とは
「エンドルフィン」は、
「ケガ」「病気」「ストレス」などによる「痛み」「苦痛」を「幸福」に転換し、
「ストレス」から「心」「身体」を守ってくれる「脳内物質」。
ストレスに応答して分泌されて、ストレスと戦う「ストレス解消ホルモン」。
「エンドルフィン」は、「精神的ストレスの解消」に作用する。
「強い快感」「幸福感」「多幸感」「恍惚感」「鎮痛」
「注意力アップ」「集中力アップ」「覚醒度アップ」「想像力アップ」
などの効果がある。
「エンドルフィン」の「影響」
「エンドルフィン」は、
「幸福感」を与えてくれ、
脳を休め、「注意力」「集中力」「記憶力」「創造性」など、
多くの「脳機能」を高めてくれる。
また、「免疫力」を高め、「身体の修復力」も高める効果もある。
「癌と戦う免疫機能」を担う「NK活性」を高める作用や、
「抗がん作用」も確認されている。
「エンドルフィン」は、
「メラトニン」と並び、「究極の癒し物質」と言える。
「メラトニン」は、「睡眠」と関連して「癒し効果」を発揮するが、
「エンドルフィン」は、「リラックス」と関連して「癒し効果」を発揮する。
「エンドルフィン」は、
「ストレス鎮痛」と呼ばれる「鎮痛効果」も発揮する。
「エンドルフィン」は、
「大脳皮質」「視床」「脊髄」などに分布する「オピオイド受容体」に結合し、
「鎮痛作用」「胃腸運動の減少」「縮瞳」「多幸感」「徐脈」「神経伝達物質の抑制作用」
などの機能をする。
「オピオイド受容体」は、
「モルヒネ」「ヘロイン」などの「麻薬」とも結合する。
「エンドルフィン」は、
人の身体の中にある「麻薬」に似た物質で、
「エンドルフィンの分泌」でも、
「モルヒネ」が投与された時と同じような「多幸感」「恍惚感」が現れる。
「エンドルフィン」が「脳内麻薬」と呼ばれる由縁。
「エンドルフィン」は、
「α(アルファ)」「β(ベータ)」「γ(ガンマ)」の「3種類」。
「βエンドルフィン」は、
「鎮痛作用」が強い「エンドルフィン」で、
「苦痛除去」の時に、最も分泌される。
「エンドルフィン」は、「究極のストレス解消物質」。
「精神的ストレスの解消」をになっている。
「ストレス」がかかった「限界状況」以外にも、
「癒された」「リラックスした」と感じられた時に、
「エンドルフィン」は分泌されている。
「幸福感」を与えてくれ、
脳を休め、「注意力」「集中力」「記憶力」「創造性」など、
多くの「脳機能」を高めてくれる。
また、「免疫力」を高め、「身体の修復力」も高める効果もある。
「癌と戦う免疫機能」を担う「NK活性」を高める作用や、
「抗がん作用」も確認されている。
「エンドルフィン」は、
「メラトニン」と並び、「究極の癒し物質」と言える。
「メラトニン」は、「睡眠」と関連して「癒し効果」を発揮するが、
「エンドルフィン」は、「リラックス」と関連して「癒し効果」を発揮する。
「エンドルフィン」は、
「ストレス鎮痛」と呼ばれる「鎮痛効果」も発揮する。
「エンドルフィン」は、
「大脳皮質」「視床」「脊髄」などに分布する「オピオイド受容体」に結合し、
「鎮痛作用」「胃腸運動の減少」「縮瞳」「多幸感」「徐脈」「神経伝達物質の抑制作用」
などの機能をする。
「オピオイド受容体」は、
「モルヒネ」「ヘロイン」などの「麻薬」とも結合する。
「エンドルフィン」は、
人の身体の中にある「麻薬」に似た物質で、
「エンドルフィンの分泌」でも、
「モルヒネ」が投与された時と同じような「多幸感」「恍惚感」が現れる。
「エンドルフィン」が「脳内麻薬」と呼ばれる由縁。
「エンドルフィン」は、
「α(アルファ)」「β(ベータ)」「γ(ガンマ)」の「3種類」。
「βエンドルフィン」は、
「鎮痛作用」が強い「エンドルフィン」で、
「苦痛除去」の時に、最も分泌される。
「エンドルフィン」は、「究極のストレス解消物質」。
「精神的ストレスの解消」をになっている。
「ストレス」がかかった「限界状況」以外にも、
「癒された」「リラックスした」と感じられた時に、
「エンドルフィン」は分泌されている。
「エンドルフィン」が「生成」される「場所」
「大きなストレス」がかかった時に、
「脳」の「脳下垂体」で生成され、分泌される。
「エンドルフィン」の「生成」
「βエンドルフィン」は、
「プロオビオメラノコルチン」という「糖たんぱく質」から、
「プロセッシング」という「断片化の過程」を経て、
「βエンドルフィン」」「ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)」「βリボトロビン」
などの「ホルモン」が生成される。
「ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)」は、
「副腎皮質」を刺激し、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を促進する「ホルモン」。
「ACTH」「エンドルフィン」は、
ストレスに応答して分泌されて、ストレスと戦う「ストレス解消ホルモン」。
「ACTH」は、「身体的ストレスの解消」に作用し、
「エンドルフィン」は、「精神的ストレスの解消」に作用する。
「エンドルフィン」の「分泌」を促進する「方法」
・「アルファ波」を出す
・「ケガ」「病気」「ストレス」などによる「痛み」「苦痛」を感じる
・「苦しみ」を感じる
・「癒し」を感じる
・「リラックス」をする(「アルファ波」を出す)
・「快」刺激を感じる
・「気持ち良い」と感じる
・「運動」をする
・「激辛料理」を食べる
・「油っぽい料理」を食べる
・「チョコレート」を食べる
・「熱いお風呂」に入る
・「鍼治療」を受ける
・
・「ケガ」「病気」「ストレス」などによる「痛み」「苦痛」を感じる
・「苦しみ」を感じる
・「癒し」を感じる
・「リラックス」をする(「アルファ波」を出す)
・「快」刺激を感じる
・「気持ち良い」と感じる
・「運動」をする
・「激辛料理」を食べる
・「油っぽい料理」を食べる
・「チョコレート」を食べる
・「熱いお風呂」に入る
・「鍼治療」を受ける
・
「アルファ波」を出す「方法」
・「クラシック音楽」を聴く
・「好きな音楽」を聴く
・「川のせせらぎ」を聴く
・「海」「紅葉」などの「綺麗な風景」を見る
・「大好きな食べ物」を食べる
・「美味しい食べ物」を食べる
・「風の心地よさ」を感じる
・「キンモクセイ」などの良い香りの「アロマ」を嗅ぐ
・「良い臭いの香り」を嗅ぐ
・目を閉じて「安静」にし、リラックスする
・1つのことに「集中」する
・「平穏」な「心の状態」になる
・「瞑想」「ヨガ」「座禅」をする
・「好きな音楽」を聴く
・「川のせせらぎ」を聴く
・「海」「紅葉」などの「綺麗な風景」を見る
・「大好きな食べ物」を食べる
・「美味しい食べ物」を食べる
・「風の心地よさ」を感じる
・「キンモクセイ」などの良い香りの「アロマ」を嗅ぐ
・「良い臭いの香り」を嗅ぐ
・目を閉じて「安静」にし、リラックスする
・1つのことに「集中」する
・「平穏」な「心の状態」になる
・「瞑想」「ヨガ」「座禅」をする
Back