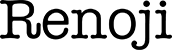Life
美容 & 健康
ボディケア
自分の「能力」を最大限に発揮する方法「集中力」を高める方法「身体」がムズムズして落ち着かない時の解消方法「健康寿命」を伸ばす方法「体の老化」を抑制する方法身体の「老廃物の排出(デトックス)」をする方法「むくみ」を解消する方法「身体の疲れ」を除去する方法「自律神経」を整える方法「筋肉痛」を解消する方法「化膿」「炎症」しやすい「体質」の「改善方法」「身体」を「アルカリ性」に保つ方法「眠気」を覚ます方法「質の良い睡眠」をとる方法効率的に「ダイエット」をする方法体のしくみ
「尿」の役割部位
「肩こり」を解消する方法「目」をスッキリとさせる方法「脳」を使いこなす方法「綺麗」な「指」を手にいれる方法「鼻づまり」を「解消」する方法家庭の医学(治療方法)
「風邪(かぜ)」の「治し方」「喉の痛み」を治す豆知識皮膚にできた「イボ」の治し方「痛風」の「正体」と「痛み」を「解消」「治療」する方法「ガン(癌)」を「予防」する方法季節
「冷え性」を解決する方法「暑い夏」に効率的に「身体」を冷やす方法
【Body Care】「集中力」を高める方法
【Body Care】
「集中力」を高める方法
INDEX
■ はじめに
■ 「集中力を高めるためのチョコレート」は「種類」に「注意」
■ 「集中力」を高めたい時には「薄目のコーヒー」
■ 「集中力」を高める方法
■ 「集中力」は「食事」から
■ 「不足」すると「集中力低下」になる「栄養成分」
■ 「人の身体」に必要な「栄養成分」
■ 「集中力」を高めるための「行動」
■ 「集中力」が続かない「原因」
■ 「集中」できない時は、まず「栄養不足」を疑う
■ 「身体」が「ムズムズ」して集中できない時は「ミネラル」「ビタミン」の「不足」かも
■ 「眠気」で「集中」できない時の「解決方法」
■ 「嫌なこと」があると「集中」できない+解決方法
■ 「嬉しい事」でも「集中」できなくなる+解決方法
■ Gallery
はじめに

「仕事」「勉強」「スポーツ」「生活」など、
あらゆる場面で、「集中力」を必要とする場面がある。
「集中力」を高めることで、
「勉強」「仕事」「作業」の効率性が各段に上がる。
「集中力」を身に着けるには、
日頃からの下地づくりが大切。
いきなり「集中力」を高めようとしても、
身体の準備が出来ていないので、
「集中力」が高まる事は、ほぼない。
何事も、普段の「トレーニング」「準備」が必要。
Back
「集中力を高めるためのチョコレート」は「種類」に「注意」

「集中力」を高めたい時に、
「チョコレートが良い」と聞いたことがある人も多い。
本当は、
「チョコレート」の「種類」によっては、
「集中力」を高めるのに「良い」が、
「種類」によっては、「良くない」と言われている。
「チョコレート」には、
「集中力」を高める可能性がある成分「カカオポリフェノール」が含まれている。
「カカオポリフェノール」は、
チョコレートの原料「カカオ」に含まれる成分で、
「抗酸化作用」があり、「脳の血流を改善」する効果と、
「認知機能を高める」という可能性が指摘されている。
「カカオ含有量」が多くなるほど、「カカオポリフェノール」も増えるようになる。
「カカオポリフェノール」だけであれば、
「チョコレート」は、「集中力を高める」のに効果的な「食べ物」となるが、
その他の成分が、ちょっと「悪い影響」となる可能性がある。
「カフェイン」「糖分」「脂肪」などの成分は、
「集中力を妨げる」という可能性を持っている。
| カフェイン | 「過剰摂取」により、「不眠」「不安感」を招き、「集中力の低下」が懸念される。 |
| 糖分 | 急激な血糖値の上昇は、「集中力の低下」「眠気」を引き起こす。 |
| 脂肪 | 過剰な脂肪摂取は、身体を重くし、集中力を妨げる可能性がある。 |
「チョコレート」を選ぶ時は、
「カカオポリフェノール」が含まれる「カカオ含有量」が多い「チョコレート」で、
「カフェイン」「糖分」「脂肪」が、極力少ない「種類」を選ぶと良い事になる。
「カカオポリフェノール」は、「カカオ含有量」に比例して多くなるので、
「カカオ含有量」が多い物を選ぶと、「カカオポリフェノール」も多く含有する事になる。
Back
「集中力」を高めたい時には「薄目のコーヒー」

「集中力」を高めたい時に、
「コーヒー」を良く飲む人は多い。
「カフェイン」は、適度に摂取すると、
・集中力の向上
・眠気覚まし
・運動能力の向上
・気分転換
・認知機能の改善
などの効果がある。
それ故に、人気の飲み物だが、
しかし、
「コーヒー」に多く含まれる「カフェイン」は、
「過剰摂取」すると、
「不眠」「不安感」「イライラ」
「心拍数の上昇」「依存症」「胃酸分泌の促進」
などを招き、「集中力の低下」が懸念されている。
「カフェインの1日の摂取量」は、
一般的に「1日400mg」ほどが目安とされていて、
「コーヒー約3杯~5杯」ほどに相当する。
「過剰なコーヒー」で「眠気」を押さえても、
「集中できない」という事も多くなってしまう。
「集中力」を高めたい時には、
「薄目のコーヒー」と「水」を用意しておくと良い。
両方を、「適度」な感覚で飲むことで、
「集中力」を高め、維持し、
「眠気」も押さえる事ができる。
「カフェイン」の「良い効果」
| 眠気覚まし | 眠気を覚まし、覚醒状態を維持する効果がある。 |
| 運動能力向上 | 運動時の脂肪燃焼を促し、持久力を高める効果も期待できる。 |
| 気分転換 | 気分転換になり、ストレスを軽減する効果も。 |
| 認知機能の改善 | 「アルツハイマー病」などの予防効果も期待されている。 |
「カフェイン」の「悪い効果」
| 不眠 | 過剰摂取は、睡眠を妨げ、不眠の原因となる可能性あり。 |
| 不安感やイライラ | カフェインには中枢神経を興奮させる作用があり、過剰摂取により不安感やイライラを引き起こす可能性があり。 |
| 心拍数の上昇 | 心臓に負担をかけ、心拍数を上昇させることがある。 |
| 依存性 | カフェインには依存性があり、急に摂取をやめると頭痛やだるさなどの離脱症状が現れることがある。 |
| 胃酸分泌の促進 | 胃酸の分泌を促し、胃痛や胃もたれを引き起こす可能性がある。 |
「カフェイン」を含む「飲み物」
| コーヒー | |
| 紅茶 | |
| 緑茶 | |
| コーラ | |
| エナジードリンク |
「カフェインレス」の「飲み物」
| デカフェコーヒー | |
| ルイボスティー | |
| ハーブティー |
Back
「集中力」を高める方法

「集中力を高める」には、
「2つ」の段階がある。
人が「集中力」を高めるには、
・身体的な下地を作る(身体的育成)
・「精神的」「生活的」な技術の取得
が必要になる。
「集中力」は、
「人の身体」の「コンディション」に大きく左右される。
「身体の状態」によって、
「集中できない」こともある。
「人の身体」は、
「身体的」に問題があると、「集中力低下」を引き起こし、
「身体的」に健全だと、「集中力向上」がしやすい。
まず、「集中力」を高めたい場合は、
「人の身体」が必要とする「適正量の栄養成分」をまんべんなく摂取することが大切。
「必要な栄養成分」を摂取出来たら、
「集中力」を高めるための、
「精神的」「生活的」な技術を使用する。
「集中力」を高める
「身体的」「精神的」「生活的」技術には、
・集中しやすい「作業環境」を整える
・「身体」の状態を整える
・「タスク管理」を行う
・心の状態を整える
などの方法がある。
Back
「集中力」は「食事」から

「集中力」は、
普段の「食事」によって形成される。
「人の身体」は、
「栄養成分」が不足すると、
あらゆる「不調」が発生し、
精神が不安定になったり、
身体の不調が発生したり、 病気にも繋がる。
「集中力」は、
身体のあらゆる機能を整え、
最大限に機能させることになる。
もちろん「栄養成分」が多く必要になる。
「ブドウ糖」「タンパク質」「ビタミン」「ミネラル」
いずれも不足すると、
「集中力」が低下したり、
「疲労感」を感じたり、
「脳機能」「身体機能」が機能しなくなったりする。
「集中力」を発揮するのには、
「食事」による「下地作り」が必須となる。
Back
「不足」すると「集中力低下」になる「栄養成分」

「人の身体」は、
「栄養成分」で構成されているので、
「不足」すると、
「身体の不調」へと繋がる。
「集中力」も、
「栄養成分」が不足するだけで、
「低下」「散漫」になりやすい。
逆に、
「栄養成分」が「過剰」になっても、
「悪影響」になることが多いので、
「栄養成分」を摂取する場合は、「適量」を意識することが大切。
下記に、
主な「栄養成分」が「不足状態」になった時の症状を記載しているが、
他の栄養成分が不足をしても、「身体」「精神」へ悪影響を引き起こす可能性がある。
基本的に、
「人の身体」が必要とする「栄養成分」の1つでも欠乏すると、
「不調」「病気」になる可能性はある。
「不足」すると「集中力低下」になる「栄養成分」一覧
| 栄養成分 | 影響 |
|---|---|
| ブドウ糖 |
「脳」の「主なエネルギー源」。 不足すると、「思考力低下」「判断力低下」「集中力の途切れ」などが発生する。 不足: 頭痛、めまい、集中力の低下、イライラ感 多く含む食品: ご飯、パン、麺類、芋類、果物など |
| ビタミンB1 |
「ブドウ糖」を「エネルギー」に変える際に必要な栄養素。 不足すると、「疲労感低下」「倦怠感低下」「記憶力低下」を引き起こす。 不足: 脚気、疲労感、倦怠感、記憶力の低下 多く含む食品: 豚肉、うなぎ、レバー、豆類など |
| 鉄分 |
血液成分の「赤血球」を作るために必要な栄養素。 不足すると、「貧血」になり、脳へ届く酸素が不足し、「集中力低下」「疲労感」につながる。 不足: 貧血、疲労感、肌の色が蒼白になる、息切れ 多く含む食品: 赤身肉、レバー、魚介類、ほうれん草など |
| オメガ-3脂肪酸 |
「脳の細胞膜」を構成する主要な構成成分。 不足すると、「脳機能の低下」「集中力低下」「記憶力低下」「気分の落ち込み」などを引き起こす可能性がある。 不足: 集中力の低下、記憶力の低下、気分の落ち込み、乾燥肌 多く含む食品: 鮭、マグロ、イワシ、えごま油、亜麻仁油など |
| ビタミンD |
「カルシウム」の吸収を助ける栄養素。 不足すると、「うつ病」「集中力の低下」「骨の健康への悪影響」を引き起こす懸念がある。 不足: うつ病、集中力の低下、骨軟化症、骨粗鬆症 多く含む食品: 鮭、マグロ、イワシ、卵黄、きのこ類(日光を浴びることで体内で合成もされる) |
Back
「人の身体」に必要な「栄養成分」

人が健康を維持し、活発に活動するためには、
バランスの取れた食事から様々な栄養素を摂取することが大切。
「集中力」を高めるには、
どの成分も必要不可欠。
「身体」「精神」に即効性のある成分もあれば、
時間をかけて、変化するものもある。
意外と、普段の食生活は、とても重要。
人が健康を維持し、活発に活動するため必要な「栄養成分」は、
大きく分けると以下の「5つ」に分類される。
「三大栄養素」は、
「人の身体」の主な「エネルギー源」となる栄養素。
「タンパク質」「炭水化物(糖質)」「脂質」
の「3種類の栄養成分」が、
「人の身体の三大栄養素」と呼ばれている。
多くが必要な「三大栄養素」に加えて、
微量ながら、必要不可欠な栄養素を含め、
「5つ」のカテゴリーに分類されている。
「5つ」に分類される「栄養成分カテゴリー」
| 栄養成分 | 説明 | |
|---|---|---|
| タンパク質 | 三大栄養素 | 「筋肉」「臓器」など「人の肉体」を作る「材料」。 |
| 炭水化物(糖質) | 三大栄養素 | 「糖質」は、「ブドウ糖」となり「脳の主なエネルギー源」となる。 |
| 脂質 | 三大栄養素 | 身体の「細胞膜」「ホルモン」などを形成する材料。 |
| ビタミン |
「ビタミン」は、「身体の機能を調節」する栄養成分。 「身体」にとって、とても重要で、 不足すると、「病気」「精神疾患」などに繋がる。 | |
| ミネラル |
「骨」「歯」の成分になったり、「身体の機能」を調節するのに使用される。 「ミネラル」がないと、「人の身体」は機能しなくなる。 微量な量だが、大きな存在。 | |
| 食物繊維 |
「食物繊維」は、「腸の働き」を活発にし、便秘予防に役立つ。 「腸」は、人の健康を維持する上で、 とても重要な臓器の1つ。 「腸内」が健康に保たれると、「人の身体」は健康に維持されるとも言われている。 | |
| 水 | 体の約60%を占め、様々な生命活動に不可欠です。 |
「人の身体」に必要な「栄養成分」は、
単一の食品からではなく、様々な食品を組み合わせてバランス良く摂取することが大切。
身体が必要としているのは、
「必要な量」の「栄養成分」。
一部の偏った栄養成分だけでは、
「人の身体」は機能できない。
「人の身体」に必要な「栄養成分」一覧
| 三大栄養素 | |
|---|---|
| 栄養成分 | 説明 |
| 炭水化物 (糖質) |
脳の主なエネルギー源。 「ご飯」「パン」「麺類」「芋類」などに多く含まれる。 |
| 脂質 |
体の細胞膜やホルモンの材料。 「魚」「肉」「ナッツ類」「油」などに多く含まれる。 |
| タンパク質 |
筋肉や臓器を作る材料。 「肉」「魚」「卵」「大豆製品」などに多く含まれる。 必須アミノ酸タンパク質を構成する「アミノ酸」は「20種類」ある。体内で合成できない「9種類」は、「必須アミノ酸」と呼ばれ、 積極的に、「食事」から補う必要がある。 「9種類」の「必須アミノ酸」・イソロイシン・ロイシン ・リジン ・メチオニン ・フェニルアラニン ・トレオニン(スレオニン) ・トリプトファン ・バリン ・ヒスチジン |
| ビタミン | |
| 栄養成分 | 説明 |
| ビタミンA |
視力維持、皮膚の健康 ビタミンAが多い食品: カロテン |
| ビタミンB群 |
エネルギー代謝、神経機能 ビタミンB群が多い食品: 全粒粉パン、レバー |
| ビタミンC |
免疫力向上、コラーゲンの生成 ビタミンCが多い食品: レモン、イチゴ |
| ビタミンD |
カルシウムの吸収促進 ビタミンDが多い食品: 鮭、卵 |
| ビタミンE |
抗酸化作用 ビタミンEが多い食品: アーモンド、植物油 |
| ビタミンK |
血止めの働き ビタミンKが多い食品: 緑黄色野菜 |
| ミネラル | |
| 栄養成分 | 説明 |
| カルシウム |
骨や歯の主成分 カルシウムが多い食品: 乳製品 |
| 鉄 |
赤血球を作るために必要 鉄分が多い食品: レバー、ほうれん草 |
| ナトリウム |
体液のバランスを保つ ナトリウムが多い食品: 食塩 |
| カリウム |
血圧の調節 カリウムが多い食品: バナナ、ほうれん草 |
| マグネシウム |
エネルギー代謝に関わる マグネシウムが多い食品: アーモンド、ほうれん草 |
| 食物繊維 | |
| 栄養成分 | 説明 |
| 食物繊維 |
腸の働きを活発にし、便秘予防に役立つ。 食物繊維が多い食品: 大麦、ごぼう |
| 水 | |
| 栄養成分 | 説明 |
| 水 |
体の約60%を占め、様々な生命活動に不可欠。 |
Back
「集中力」を高めるための「行動」

「集中力」を高めるための「行動」には、
「身体的」「精神的」「生活的」「効率的」な観点から見たものがある。
「集中力」は、
簡単に途切れてしまうことが多い、
「集中力」を高められたら、
できるだけ、「集中力」を維持できるようにするのが「集中力を高める行動」。
「集中力」を高めるための「行動」一覧
| 環境を整える |
・作業スペースを整理整頓し、視界に入るものを最小限にする。 ・照明を調整し、快適な明るさを確保する。 ・周囲の音が気になる場合は、耳栓やノイズキャンセリングヘッドホンを使う。 ・スマートフォンや通知をオフにするなど、気を散らすものを遠ざける。 |
| 身体の状態を整える |
・十分な睡眠をとる。 ・バランスの取れた「栄養補給」をする。 ・定期的に運動する。 ・水分をこまめに補給する。 |
| タスク管理 |
・記録を付ける ・やりたいことをリストアップし、優先順位をつける。 ・小さなタスクに分割して、達成感を味わいやすくする。 ・タイマーを使って集中時間を区切り、休憩を挟む。 ・ポモドーロテクニックなど、集中するための時間管理法を取り入れる。 |
| 心の状態を整える |
・深呼吸や瞑想を行い、リラックスする。 ・好きな音楽を聴くなど、気分転換をする。 ・自然の中に出てリフレッシュする。 ・アロマセラピーを活用する。 |
| その他 |
・カフェやコワーキングスペースなど、集中できる場所へ行く。 ・集中力を高めるためのアプリやツールを使う。 ・仲間と学習会に参加する。 |
Back
「集中力」が続かない「原因」

「集中力」が続かない「原因」には、
・ストレス
・睡眠不足
・栄養不足
・脱水症状
・興味関心の薄れ
・環境の乱れ
・マルチタスク
などがある。
「集中力」というのは、
意外と繊細なもので、
簡単に、「集中力」は途切れてしまう。
「周辺」の「音」「動き」などで、
「注意力」「好奇心」が散らばってしまい、
「集中」する事が難しくなることは多い。
「集中力」を妨げる「原因」を理解してしまえば、
その「原因」を廃除していくことで、
「集中力」が継続し、高める事も可能になってくる。
「集中」ができない「原因」を理解することは、
「集中」できる状況に近づく最善策にでもある。
Back
「集中」できない時は、まず「栄養不足」を疑う

「集中」ができない時や、
「集中力」を高められない時は、
まず「栄養不足」を疑う。
「環境」などが変わらず、
いつもの「場所」「時間」で、
「集中」できない時は、
その多くの「集中できない原因」が、
「栄養不足」であることが多い。
「栄養不足」と行っても、
「1つ」の「栄養成分」が不足するだけでも、
「集中力」が「低下」「散漫」することがある。
「脳」の栄養素である「ブドウ糖」が不足すると、
「空腹感」を感じるように、「脳」からの指令が出て、
お腹が空いたと実感する。
しかし、
他の栄養成分が不足した場合は、
「空腹感」などを感じることはない。
「身体」の「不調」「集中力の低下」などの症状が出るようになる。
「不足」した「栄養成分」による「症状」
| 栄養成分 | 影響 |
|---|---|
| ブドウ糖 |
「脳」の「主なエネルギー源」。 不足すると、「思考力低下」「判断力低下」「集中力の途切れ」などが発生する。 不足: 頭痛、めまい、集中力の低下、イライラ感 多く含む食品: ご飯、パン、麺類、芋類、果物など |
| オメガ-3脂肪酸 |
「脳の細胞膜」を構成する主要な構成成分。 不足すると、 「脳機能の低下」「集中力低下」「記憶力低下」「気分の落ち込み」 などを引き起こす。 不足: 集中力の低下、記憶力の低下、気分の落ち込み、乾燥肌 多く含む食品: 鮭、マグロ、イワシ、えごま油、亜麻仁油など |
| ビタミンB1 |
「ブドウ糖」を「エネルギー」に変える際に必要な栄養素。 不足すると、 「疲労感低下」「倦怠感低下」「記憶力低下」 などを引き起こす。 不足: 脚気、疲労感、倦怠感、記憶力の低下 多く含む食品: 豚肉、うなぎ、レバー、豆類など |
| ビタミンD |
「カルシウム」の吸収を助ける栄養素。 不足すると、 「うつ病」「集中力の低下」「骨の健康への悪影響」 などを引き起こす懸念がある。 不足: うつ病、集中力の低下、骨軟化症、骨粗鬆症 多く含む食品: 鮭、マグロ、イワシ、卵黄、きのこ類(日光を浴びることで体内で合成もされる) |
| 鉄分 |
血液成分の「赤血球」を作るために必要な栄養素。 不足すると、「 貧血」になり、脳へ届く酸素が不足し、「集中力低下」「疲労感」 などを引き起こす。 不足: 貧血、疲労感、肌の色が蒼白になる、息切れ 多く含む食品: 赤身肉、レバー、魚介類、ほうれん草など |
| カルシウム |
「骨」「歯」の「構成成分」。 不足すると、 「骨粗しょう症のリスク増加」「骨の発育不全」「歯の健康への悪影響」 「筋肉の収縮機能の低下」「神経の伝達障害」「血液凝固機能の低下」 などの症状が現れる。 カルシウムが多く含まれる食品: 乳製品、小魚、緑黄色野菜など |
| ナトリウム |
「ナトリウム」は、「体液」のバランスを保つのに必要な「ミネラル」「栄養成分」 「神経伝達」「筋肉の収縮」にも必要。 不足すると、 「脱水症状」「筋肉の痙攣」「疲労感」「だるさ」 「食欲不振」「血圧低下」「集中力の低下」 などを引き起こす。 ナトリウムが多い食品: 食塩 |
| カリウム |
「カリウム」は、「血圧の調節」などに使われる「栄養成分」。 「筋肉の収縮や弛緩」をスムーズに行うために必要な「ミネラル」。 カリウムはナトリウムの働きを抑制し、血圧を安定させる働きがある。 不足すると、 「筋肉の異常」「心拍の異常」「疲労感」「倦怠感」「高血圧のリスク」 「消化器系のトラブル」「食欲不振」「便秘」「下痢」 「神経系のトラブル」「イライラ」「集中力の低下」「不眠症」 などの症状が現れる。 カリウムが多い食品: バナナ、ほうれん草 |
| マグネシウム |
「マグネシウム」は、「エネルギー代謝」に関わる「ミネラル」。 マグネシウムは心臓のリズムを安定させ、血圧を調整する。 カルシウムと共に骨を強くする働きもある。 不足すると、 「筋肉の異常」「筋肉の痙攣」「こむら返り」 「神経系の異常」「イライラ感」「不眠」「集中力の低下」「抑うつ状態」 「心血管系の異常」「不整脈」「高血圧」「心疾患」 「骨粗しょう症」「吐き気」「めまい」「頭痛」「疲労感」「倦怠感」 などの症状が現れる。 マグネシウムが多い食品: アーモンド、ほうれん草 |
Back
「身体」が「ムズムズ」して集中できない時は「ミネラル」「ビタミン」の「不足」かも

「身体」が「ムズムズ」して集中できない時は、
「運動不足」の時もあれば、
「ミネラル」「ビタミン」が「不足」していることもある。
「脳」の栄養成分「ブドウ糖」が不足すると、
「空腹感」を感じて、「食事」をして、
「炭水化物(糖質)」を補給して、「ブドウ糖」を補給できる。
しかし、
「ミネラル」「ビタミン」が「不足」しても、
「空腹感」は感じず、他の症状が引き起こされる。
「ミネラル」「ビタミン」などが「不足」すると、
人によって「身体」が「ムズムズ」したりする。
「不足状態」の「症状」は、
人によって異なることもある。
不足している可能性のある「栄養成分」が多く含まれる「食品」を
一つずつ食べていくのも一つの方法だが、
「ミネラル」「ビタミン」の「サプリメント」を摂取するのが効率的。
「集中力」を高めるためには、
「ビタミン」「ミネラル」などの「サプリメント」を常備しておく必要もありそう。
Back
「眠気」で「集中」できない時の「解決方法」

「眠気」で「集中」できない時の「解決方法」は、
・「コーヒー」を飲む
・「栄養ドリンク」を飲む
・「10分」ほど「仮眠」をする
・満腹になるまでの食事をしない
・少しの「空腹感」を感じるようにする
・体温が下がらないようにする
・軽い運動をして、心拍数を少しあげて、血流を良くする
・体温を意図的に下げる
・「手」を「冷たい水」で洗う
などの「対策」がある。・「栄養ドリンク」を飲む
・「10分」ほど「仮眠」をする
・満腹になるまでの食事をしない
・少しの「空腹感」を感じるようにする
・体温が下がらないようにする
・軽い運動をして、心拍数を少しあげて、血流を良くする
・体温を意図的に下げる
・「手」を「冷たい水」で洗う
人は、眠くなると「集中」ができない。
「眠気」を感じないように、
「集中力を高めたい」時の前は、
コンディション作りも大切。
「人」は、
「体温」が「下がる」時に眠くなるようになっていて、
夜、ベッドで眠るときも、「体温」が下がると眠りに付きやすい。
「お風呂」などで、温まった身体が冷えるときに、
眠りやすくなった人は多いはず。
もし、
「眠気」が襲ってきたら、
「体温が下がる」と眠くなることを逆手に、
「体温」を意図的に下げることで、
「眠気」を覚ます事もできる。
「眠くなる」と「手」「足」が温かくなると感じた人も多いはず。
それを、冷たい水で、先に冷やしてしまえば、
「眠気」が覚める事も多い。
Back
「嫌なこと」があると「集中」できない+解決方法
「人」は、
「嫌なこと」「ストレス」などがあると、
「集中」ができない傾向がある。
「嫌なこと」があると、
そのことばかりが、頭の中を支配してしまう傾向が、人にある。
「集中ができない」と悩むことはない。
ほとんどの人が、「嫌なこと」「ストレス」があると、
「集中ができない」という状況になると言われています。
この「解決方法」は、
「嫌なこと」「ストレス」があると、
「人は集中できない」という事実を知る事で解決される。
なんだ、
人は、そういう仕組みになっているんだ。
と思えば良いだけ。
あとは、
「嫌なこと」「ストレス」を解決する。
そして、頭の中から取り除けば良い。
過去の嫌な出来事の場合は、解決すらしなくてよい。
嫌な思い出として、片づければ良い。
言葉にするのは簡単だが、
「嫌なこと」「ストレス」は、
知らぬ間に頭で考えたり、思い出したりしてしまう。
そしたら、
意識的に、
・嫌なことを考えるだけ無駄。
・考える価値もない。
・考えたところで、過去は変わらないと、
と自分に自覚させればいい。
意外と、
自分の能力で、切り開けることに意識が集中できるようになる。
Back
「嬉しい事」でも「集中」できなくなる+解決方法
「人の身体」は、
「悲しいこと」「嫌なこと」「ストレス」の他に、
「嬉しいこと」があっても、
「集中」ができなくなる傾向がある。
「嬉しいこと」があると、
気分が高揚して、目の前のことに意識を向けにくくなる。
言葉で言うと「浮かれた状態」になる。
「嬉しいこと」があって、
「集中」ができなくなったら、
目の前のことを処理して片付けることで、
「嬉しいこと」に集中できるように、
計画を立てて、実行すると、
目の前にある事に「集中」できるようになる。
仕事であれば、
仕事を片付けて、お金を稼げば、
思いっきり「嬉しいこと」「楽しいこと」に、
時間とお金を費やせる。
と思うことで、
仕事に集中ができる。
「勉強」なども同様。
目の前の事柄を終わらせれば、
「嬉しいこと」「楽しいこと」を行えると、
自分に計画を提示することで、
「集中力」を取り戻すことができ、高めることもできる。
Back