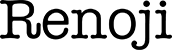Life
美容 & 健康
ボディケア
自分の「能力」を最大限に発揮する方法「集中力」を高める方法「身体」がムズムズして落ち着かない時の解消方法「健康寿命」を伸ばす方法「体の老化」を抑制する方法身体の「老廃物の排出(デトックス)」をする方法「むくみ」を解消する方法「身体の疲れ」を除去する方法「自律神経」を整える方法「筋肉痛」を解消する方法「化膿」「炎症」しやすい「体質」の「改善方法」「身体」を「アルカリ性」に保つ方法「眠気」を覚ます方法「質の良い睡眠」をとる方法効率的に「ダイエット」をする方法体のしくみ
「尿」の役割部位
「肩こり」を解消する方法「目」をスッキリとさせる方法「脳」を使いこなす方法「綺麗」な「指」を手にいれる方法「鼻づまり」を「解消」する方法家庭の医学(治療方法)
「風邪(かぜ)」の「治し方」「喉の痛み」を治す豆知識皮膚にできた「イボ」の治し方「痛風」の「正体」と「痛み」を「解消」「治療」する方法「ガン(癌)」を「予防」する方法季節
「冷え性」を解決する方法「暑い夏」に効率的に「身体」を冷やす方法
【Body Care】効率的に「ダイエット」をする方法
【Body Care】
効率的に「ダイエット」をする方法
INDEX
はじめに
「ダイエット」とは
「ダイエット」という言葉は、
「日本語」では、
一般的に「体重を減らす」という意味で使われている。
主に、「美容」「健康」を目的とした「体重減量」を指していて、
「食事制限」「運動」を組み合わせることで、「理想の体型」を目指す「行為全般」のことを意味している。
「ダイエット」の語源は、
古代ギリシア語の「diaita(生活様式、生き方)」という言葉。
本来の意味は、
「健康」を維持するための「食事療法」「生活習慣」の全般を意味している。
「体重減量」のみを目的としたものではなかった。
「欧米」における「diet」は、
「日常的な食事」「食習慣」を意味する。
「diet」という言葉は、
「a healthy diet(健康的な食事)」や「a balanced diet(バランスの取れた食事)」
というように使われることもある。
「体重減量」を意味する場合は、「on a diet」や「dieting」といった表現となる。
「現代社会」では、
「Diet」というと、
「食事制限」「運動」「サプリメント」「医療行為」
など、その意味は、多岐に渡る。
Back
「健康的」な「ダイエット」とは
「健康的」な「ダイエット」は、
単に体重を減らすだけでなく、
心身ともに健康な状態を維持することを目的としている。
「バランスの取れた食事」「適度な運動」「十分な睡眠」を基本とし、
「無理のない範囲」で継続できる方法を選ぶことが重要となっている。
Back
「ダイエット」の「目的」
「ダイエット」の「目的」は、人によって異なる。
「美容」「健康維持」「生活習慣病の予防」など、
その目的は様々。
どのような目的であれ、
「健康を第一」に考え、「目的」を達成することが重要。
様々な「目的」がある「ダイエット」。
「美容」「健康維持」「生活習慣病の予防」など、
多くの「目的」は、結果的に「体重減少」に結び付く。
「美容」「健康」「生活」も、
改善して、良くすると、「スッキリとした身体」になっていく。
どんな目的でも、
「身体」を大切にして、「健康」に近づくと、
「すっきりとした綺麗な身体」になりやすい。
Back
「ダイエット」の絶対法則「カロリーオーバーをしない!」
痩せるための「ダイエット」の絶対法則は、
「カロリーオーバーをしない!」
ということ。
「カロリーオーバー」をすると、
必ず「栄養を蓄える」ために、
「身体」に「脂肪」として貯蓄される。
1日に必要な「カロリー」を把握して、
それ以上に「食事」をしない。
それだけでも、かなり痩せてくる。
Back
「太る原因」は、必ず「カロリーオーバー」
「人」が「太る原因」は、
「世界共通」「人類共通」で、「カロリーオーバー」のみ。
「食事」「運動」「体質」などではなく、
絶対に「カロリーオーバー」。
「カロリーオーバー」以外にない。
「1日の食事量」を、
「1日の消費エネルギー量」と同じか、
少なくすることで、身体は痩せてくる。
Back
痩せたいなら自分の「基礎代謝量」を知っておく
体重を減らす「ダイエット」の場合、
「人」が、「1日」に必要とする「基礎代謝量」は、
必ず確認しておきたい。
「基礎代謝量」は、
生命維持に必要な最小限の「エネルギー量」であり、
「性別」「年齢」「体重」から計算できるようになっている。
「基礎代謝量の食事」を、毎日食事をしないと、
死んでしまったり、身体や精神がおかしくなってしまう。
簡単に言えば、
「基礎代謝量」は、何もしなくても、
「脳」「内蔵」など、「身体」「生命」を「維持」するのに使用される「エネルギー量」。
「1日」をまったく動かず、何も考えずに過ごしても、
「消費されるエネルギー量」のことを意味している。
「基礎代謝量」を把握することで、
食べなければ行けない「最低量の食事」がわかる。
下記の「基礎代謝基準値」に、「自分の体重」を掛けるだけで算出できる。
自分の「基礎代謝基準値」の計算式
「1日の基礎代謝量」 = 「基礎代謝基準値」×「自分の体重」
人が最低限必要とする「1日」の必要エネルギー量「基礎代謝基準値(kcal/kg体重/日)」
| 年齢 | 男性(体重1kgあたり) | 女性(体重1kgあたり) |
|---|---|---|
| 1~2歳 | 61.0 kcal | 59.7 kcal |
| 3~5歳 | 54.8 kcal | 52.2 kcal |
| 6~7歳 | 44.3 kcal | 41.9 kcal |
| 8~9歳 | 40.8 kcal | 38.3 kcal |
| 10~11歳 | 37.4 kcal | 34.8 kcal |
| 12~14歳 | 31.0 kcal | 29.6 kcal |
| 15~17歳 | 27.0 kcal | 25.3 kcal |
| 18~29歳 | 23.7 kcal | 22.1 kcal |
| 30~49歳 | 22.5 kcal | 21.9 kcal |
| 50~64歳 | 21.8 kcal | 20.7 kcal |
| 65~74歳 | 21.6 kcal | 20.7 kcal |
| 75歳以上 | 21.5 kcal | 20.7 kcal |
計算の基準となる「基礎代謝量の基準値」は、
「厚生労働省」が発表している「日本人の食事摂取基準」などで確認できる。
Back
「基礎代謝量」+「何カロリー」で痩せるのかを確認する
「基礎代謝量」は、
「脳」「内蔵」などの「身体」が「1日に必ず消費するエネルギー量」なので、
必ず「食事」をしないと行けない量。
体重を落とす「ダイエット」の場合は、 この「基礎代謝量」に、活動するのに消費する「エネルギー量」を加えた
「1日の必要摂取カロリー」を把握することで、
「痩せるための食事量」が簡単に算出できる。
「基礎代謝量」+「200kcal~400kcal前後」が、
「1日の必要摂取カロリー」で、「1日に消費されるカロリー」ということになる。
「活動量」「年齢」「性別」「性格」などの違いによって、
「基礎代謝量」に加える「カロリー数」は異なる。
自分自身で、
「基礎代謝量」に、どれくらい「カロリー摂取」したら、
自分は太り始め、自分は痩せ始めるのかを確認することが重要。
「自分」が「痩せるエネルギー量」を確認出来たら、
後は、とても簡単で、
「食事量」を「痩せるエネルギー量」の範囲内に納めれば良いだけ。
「1日」で考えると、
「守れる日」「守れない日」が出てくるので、
「1週間全体」で、「痩せるエネルギー量」の範囲内に収まっていれば良い。
今日は、食べ過ぎたから、明日は、少な目にしよう。
ぐらいの感覚で調整出来れば良い。
だが、
忘れてはいけないのは、
「太る」のは、「摂取カロリーオーバー」が発生した時のみ。
それを肝に命じて、忘れないことが大切。
Back
「○○ダイエット」が「必ず失敗する理由」
「○○ダイエット」という、
「1つの食品」で、ダイエットをすると、必ず失敗をする。
その理由は、シンプルに「栄養不足」。
必ず「リバウンド」します。
人の身体は、
「脂肪」を燃焼するのに、
「ビタミン」「ミネラル」「脳内物質」「ホルモン」などを使用する。
それらは、
「食事」から摂取しないと、
体内で生成できない「栄養素」も含まれる。
どんなに、
食事を制限しても、
「脂肪燃焼」に必要な「栄養素」が不足していると、
エネルギー不足でも、「脂肪」が燃焼することが出来なくなる。
そして、
食事を多く食べるように、「脳」から指令が出てしまう。
それが「リバウンド」の仕組み。
「ダイエット」には、
「身体」が必要とする「すべての栄養素」が必要になるので、
色々な栄養素が摂取できる「バランスの良い食事」が必須となる。
Back
「ダイエット」に「バランスの良い食事」が必須な理由
「ダイエット」には、
「バランスの良い食事」が必須。
その理由は、
身体の「脂肪」を分解して「エネルギー」として活用する過程を見るとわかる。
多くの栄養素が使用されていて、
「ビタミン」「ミネラル」「タンパク質」「炭水化物」が、
「脂肪分解」「輸送」「エネルギーへの転換」に使われている。
不足すると、「脂肪燃焼」が出来なくなる。
「食事をしないダイエット」の場合、
「脂肪燃焼」が行われず、
食事をすることを即す指令だけが「脳」から発せられることになる。
痩せてもいないのに、食事をもっとするように、
身体へ指令が出てしまう。
「ダイエット」は、
「最低限の量」を「栄養バランスの良い食事」ですることが必須になっている。
下記に、
「脂肪燃焼の流れ」と「脂肪燃焼に必要な栄養成分」をまとめてある。
必要な栄養成分の種類は、はっきり言って多い。
体内で生成できない「栄養成分」も多く、
食事をして補充する必要があることがわかる。
「身体」に蓄積された「脂肪」が「燃焼」される過程
「身体」に蓄積された「脂肪」が、
「脳」からの指令を受けてから、
「燃焼」する過程を掲載。
「脂肪」が、すぐに「エネルギー」になるのではなく、
「脂肪」から「成分」が分離され、
血液中に入り、「細胞」へと運搬される。
「細胞」に入った「成分」は、
更に、成分が変換されながら「細胞内」を移動し、
「細胞内で利用できる成分」に変換された後、
「エネルギー」として利用される。
「身体」に蓄積された「脂肪」が「燃焼」される流れ
| 脂肪細胞からの遊離 |
「脂肪」は、 主に「トリグリセリド」として脂肪細胞に蓄積されている。 「エネルギー」が必要になると、「ホルモン(アドレナリン、ノルアドレナリンなど)」が作用し、 「神経系の刺激」によって、脂肪細胞内の酵素「リパーゼ」が活性化される。 |
| トリグリセリドの分解 |
活性化された「リパーゼ」は、「トリグリセリド」を分解し、「脂肪酸」と「グリセロール」を遊離させる。 |
| 血中への放出 |
遊離した「脂肪酸」は、血液中に放出され、「アルブミン」というタンパク質と結合し、全身の組織へ運ばれる。 「グリセロール」は、肝臓で糖新生の材料として利用されるか、「エネルギー」として利用される。 |
| 2. 脂肪酸の輸送と活性化 | |
|---|---|
| 細胞内への取り込み |
運搬された「脂肪酸」は、「細胞膜」を通過して細胞内に取り込まれる。 |
| 活性化 |
細胞内に入った「脂肪酸」は、「ATP」を消費して、 「アシルCoA」という活性化された形になる。 この反応には、「ビタミンB5(パントテン酸)」や「コエンザイムA」が「補酵素」として必要。 |
| 3. 脂肪酸のミトコンドリアへの輸送 | |
| カルニチンシャトル |
活性化された「脂肪酸(アシルCoA)」は、ミトコンドリア内膜を通過できない。 そこで、「L-カルニチン」という物質が、「アシルCoA」を「ミトコンドリア内膜」を通過できるように運搬する。 |
| 4. β酸化 | |
| 脂肪酸の分解 |
「ミトコンドリア」内に入った「脂肪酸」は、「β酸化」という過程によって、「2炭素」ずつ分解され、「アセチルCoA」という物質になる。 この過程で、「FADH2」と「NADH」という「電子伝達体」も生成される。 |
| 必要な栄養素 |
「β酸化」には、「ビタミンB2(リボフラビン)」「ビタミンB3(ナイアシン)」などが「補酵素」として必要。 |
| 5. クエン酸回路(TCA回路) | |
| アセチルCoAの酸化 |
「アセチルCoA」は、クエン酸回路に入り、様々な酵素の作用によって、「二酸化炭素」と「水」に分解される。 この過程で、「GTP」「FADH2」「NADH」という「高エネルギー化合物」が生成される。 必要な栄養素 「クエン酸回路」には、 「ビタミンB1(チアミン)」「ビタミンB2(リボフラビン)」「ビタミンB3(ナイアシン)」「ビタミンB5(パントテン酸)」 などが「補酵素」として必要。 |
| 6. 電子伝達系 | |
| ATPの生成 |
「クエン酸回路」で生成された「FADH2」「NADH」は、 「ミトコンドリア内膜」にある電子伝達系で、「酸素」と反応し、大量の「ATP(アデノシン三リン酸)」を生成する。 「ATP」は、「細胞のエネルギー源」として利用される。 必要な栄養素 「電子伝達系」には、 「鉄」「銅」などの「補因子」が必要。 |
「身体」に蓄積された「脂肪」が「燃焼」される過程
「脂肪」が「燃焼」される過程では、
「脂肪」だけでは、「エネルギー」に変換されることができない。
調べた中でも、
下記の栄養成分が必要になる。
1つでも「不足」「欠乏」すると、「脂肪燃焼」をして「エネルギー」として利用できないらしい。
やはり、「栄養バランスの良い食事」が必須。
| 栄養素 | 説明 |
|---|---|
| ホルモン(アドレナリン) |
生成に必要な栄養素 ・フェニルアラニン ::: 大豆製品、肉類、魚介類、乳製品) ・チロシン ::: 大豆製品、肉類、魚介類、乳製品、アボカド) ・ビタミンB6 ::: レバー、マグロ、カツオ、バナナ、ジャガイモ) ・ビタミンC ::: 果物(柑橘類、イチゴなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)) ・銅 ::: レバー、牡蠣、エビ、ナッツ類、豆類) |
| ホルモン(ノルアドレナリン) |
生成に必要な栄養素 ・フェニルアラニン ::: 大豆製品、肉類、魚介類、乳製品) ・チロシン ::: 大豆製品、肉類、魚介類、乳製品、アボカド) ・ビタミンB6 ::: レバー、マグロ、カツオ、バナナ、ジャガイモ) ・ビタミンC ::: 果物(柑橘類、イチゴなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)) ・銅 ::: レバー、牡蠣、エビ、ナッツ類、豆類 |
| リパーゼ |
生成に必要な栄養素 ・たんぱく質 ::: 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品) ・ビタミンB群 ::: レバー、魚介類、肉類、卵、乳製品、豆類、緑黄色野菜) ・ミネラル ::: 海藻類、野菜類、豆類、ナッツ類) ・食物繊維 ::: 野菜類、果物類、海藻類、豆類、きのこ類) |
| タンパク質「アルブミン」 |
アルブミン生成に必要な栄養素 ・タンパク質 ::: 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品) ・炭水化物 ::: 米、パン、麺類、芋類、果物) ・脂質 ::: 青魚、ナッツ類、アボカド、植物油) ・ビタミンB群 ::: レバー、魚介類、肉類、卵、豆類、緑黄色野菜) ・ビタミンC ::: 果物(柑橘類、イチゴなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)) ・亜鉛 ::: 牡蠣、レバー、肉類、豆類、ナッツ類) |
| ビタミンB5(パントテン酸) |
パントテン酸を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、腎臓、ハツなどの内臓肉 ・魚介類 ::: たらこ、イワシ、サケ ・卵 ::: 卵黄 ・乳製品 ::: 牛乳、ヨーグルト ・豆類 :: ::: 大豆、レンズ豆 ・野菜 ::: アボカド、ブロッコリー、カリフラワー、きのこ類 ・穀類 ::: 玄米、全粒粉パン |
| コエンザイムA |
「パントテン酸」は、「コエンザイムA」の構成成分の一つで、「コエンザイムA」の合成に不可欠。 パントテン酸を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、腎臓、ハツなどの内臓肉 ・魚介類 ::: たらこ、イワシ、サケ ・卵 ::: 卵黄 ・乳製品 ::: 牛乳、ヨーグルト ・豆類 ::: 大豆、レンズ豆 ・野菜 ::: アボカド、ブロッコリー、カリフラワー、きのこ類 ・穀類 ::: 玄米、全粒粉パン |
| L-カルニチン |
L-カルニチンを生成するのに必要な栄養素 ・リジン ::: 肉類、魚介類、卵、大豆製品 ・メチオニン ::: 肉類、魚介類、卵、乳製品、豆類 ・ビタミンC ::: 果物(柑橘類、イチゴなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど) ・鉄 ::: レバー、赤身肉、魚介類、豆類、緑黄色野菜 |
| ビタミンB2(リボフラビン) |
ビタミンB2(リボフラビン)は、体内で生成することができない必須ビタミン。 ビタミンB2を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、ハツ、腎臓などの内臓肉 ・魚介類 ::: ウナギ、サンマ、サバ、アジ ・乳製品 ::: 牛乳、ヨーグルト、チーズ ・卵 ::: 鶏卵 ・豆類 ::: 大豆、納豆 ・野菜 ::: モロヘイヤ、ブロッコリー、アスパラガス ・その他 ::: きのこ類、酵母 |
| ビタミンB3(ナイアシン) |
ビタミンB3(ナイアシン)は、体内で生成することができない必須ビタミン ビタミンB3を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、ハツ、腎臓などの内臓肉、鶏むね肉、豚肉 ・魚介類 ::: マグロ、カツオ、サバ、イワシ、アジ ・豆類 ::: 大豆、落花生 ・穀類 ::: 玄米、全粒粉パン ・その他 ::: きのこ類、酵母 |
| ビタミンB1(チアミン) |
「ビタミンB1(チアミン)」は、体内で生成することができない必須ビタミン。 ビタミンB1を多く含む食品 ・肉類 ::: 豚肉(特にヒレ肉やもも肉)、レバー ・魚介類 ::: ウナギ、カツオ、マグロ、サバ ・豆類 ::: 大豆、納豆、インゲン豆 ・穀類 ::: 玄米、麦 ・野菜 ::: アスパラガス、ほうれん草、ブロッコリー ・その他 ::: 種実類、きのこ類 |
| ビタミンB2(リボフラビン) |
「ビタミンB2(リボフラビン)」は、体内で生成することができない必須ビタミン。 ビタミンB2を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、ハツ、腎臓などの内臓肉 ・魚介類 ::: ウナギ、サンマ、サバ、アジ ・乳製品 ::: 牛乳、ヨーグルト、チーズ ・卵 ::: 鶏卵 ・豆類 ::: 大豆、納豆 ・野菜 ::: モロヘイヤ、ブロッコリー、アスパラガス ・その他 ::: きのこ類、酵母 |
| ビタミンB3(ナイアシン) |
「ビタミンB3(ナイアシン)」は、体内で生成することができない必須ビタミン。 ビタミンB3を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、ハツ、腎臓などの内臓肉、鶏むね肉、豚肉 ・魚介類 ::: マグロ、カツオ、サバ、イワシ、アジ ・豆類 ::: 大豆、落花生 ・穀類 ::: 玄米、全粒粉パン ・その他 ::: きのこ類、酵母 |
| ビタミンB5(パントテン酸) |
「ビタミンB5(パントテン酸)」は、体内で生成することができない必須ビタミン。 ビタミンB5を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、ハツ、腎臓などの内臓肉 ・魚介類 ::: たらこ、イワシ、サケ ・卵 ::: 卵黄 ・乳製品 ::: 牛乳、ヨーグルト ・豆類 ::: 大豆、レンズ豆 ・野菜 ::: アボカド、ブロッコリー、カリフラワー、きのこ類 ・穀類 ::: 玄米、全粒粉パン |
| 鉄 |
「鉄」は、体外から摂取する必要がある必須ミネラル。 鉄を多く含む食品 ・肉類 ::: レバー、赤身肉 ・魚介類 ::: マグロ、カツオ、イワシ、アサリ ・豆類 ::: 大豆、納豆 ・野菜 ::: ほうれん草、小松菜 ・海藻類 ::: ヒジキ、昆布 |
| 銅 |
「銅」は、体外から摂取する必要がある必須ミネラル。 銅を多く含む食品 ・魚介類 ::: 牡蠣、エビ、カニ、イカ ・肉類 ::: レバー、ハツ ・豆類 ::: 大豆、レンズ豆 ・ナッツ類 ::: アーモンド、カシューナッツ ・その他 ::: チョコレート、ココア |
などの「栄養素」などが必要になる。
Back
今すぐ辞めるべき「太る原因」
「人」が「太る原因」は、
・食べ過ぎ
・血行が悪い
・身体を動かさない
・筋肉が少ない
・栄養バランスが悪い
がある。
これらをすべてやめると、
身体が太ることはない。
「太る原因」の中で、
「食べ過ぎ」以外の全ての「原因」が、
「消費カロリーの減少」につながる。
「食べ過ぎ」は、
「消費カロリー」以上の「カロリー摂取」となるので、
全ての「原因」が「余分なカロリー」を生み出す。
「太る原因」は、
元を辿ると、「余分なカロリー」が体内に存在すること。
「太る原因」とされていることの
「逆」のこと、
・控え目な量の食事をする
・血行を良くする
・身体を動かす
・筋肉を増やす
・栄養バランスの良い食事をする
という生活習慣にするだけで、
「身体」は、太ることなく、
痩せ始め、バランスの良い体型になる。
Back