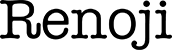旅メモ
旅メモ【日本編】
旅Memo【関東地方編】
旅Memo【茨城県編】
Category
「茨城県」の「基本情報」「茨城県」の「アウトドア」「旅」に役立つ「旅情報」
「茨城県」の「定番スポット」「茨城県」にある「愛犬同伴OK」の「旅スポット」「茨城県」にある「Beach(海水浴場)」「茨城県」にある「キャンプ場」筑波エリア大洗エリア旅Spot
鹿島神宮息栖神社(いきすじんじゃ)大洗サンビーチ海水浴場旅グルメ
「茨城県」の「御当地グルメ」「茨城県」を訪れたら食べたい美味しそうな「飲食店」「茨城県」にある美味しそうな「回転寿司店」「茨城県」にある美味しそうな「焼肉店」御当地レストラン「坂東太郎」旅の宿
「茨城県」にある魅力的な「旅の宿」「茨城県」の「日帰り入浴施設」「茨城県」にある「愛犬」と一緒に宿泊できる「旅の宿」「茨城県」にある「仮眠」「車中泊」ができる「スポット」
【茨城県】鹿島神宮
【茨城県】
鹿島神宮
INDEX
■ はじめに
■ 「鹿島神宮」は「愛犬同伴NG」
■ 「東国三社」の「参拝順序」
■ 「東国三社」とは
■ 「国譲り神話」とは
■ 「鹿島神宮」とは
■ 「鹿島神宮」の「御祭神」
■ 「鹿島神宮」の「御利益」
■ 「鹿島神宮」の「歴史」
■ 「鹿島神宮」の「見どころ」
■ 「鹿島神宮」の「祭事」
■ 「鹿島神宮」の「地図」
■ 「鹿島神宮」の「駐車場」
■ 「春日大社」は「鹿島神宮」から御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を勧請した
■ 「鹿島神宮」周辺にある美味しそうな「飲食店」
■ 「鹿島神宮」を参拝する前に、「愛犬散歩」が出来そうな「スポット」
■ 「酒々井PA(下り)」で「休憩」と「愛犬散歩」
■ 「道の駅 いたこ」で「愛犬散歩」「休憩」「買い物」
■ 美味しい「チヂミ」が食べられる「ちっちゃな韓国おおかみ」
■ 「東日本大震災」で倒壊後に再建された「二之鳥居」
■ 「水戸藩」の初代藩主「徳川頼房」により造営された「楼門」
■ 徳川家2代目将軍「徳川秀忠公」によって寄進された「拝殿」「本殿」
■ 「神様の使い」とされる「鹿」と触れ合える「鹿園」
■ 徳川幕府初代将軍「徳川家康公」によって奉納された建物「奥宮」
■ 「大地震」を引き起こす「大ナマズ」を封じている「要石(かなめいし)」
■ 美味しそうな「そば」「だんご串」が食べられる「湧水茶屋一休 ひとやすみ」
■ 湧き出る「御神水」が溜まってできた池「御手洗池」
■ 参拝帰りに御当地ファミリーレストラン「坂東太郎」で美味しい食事
■ Gallery
はじめに
「鹿島神宮」は「愛犬同伴NG」

「鹿島神宮」は、
「愛犬同伴NG」となっていた。
「鹿島神宮」公式WEBにも、
改めて、「愛犬同伴NG」という内容が掲載されていました。
トラブルも発生しているようなので、
「愛犬同伴」での参拝をしないように「ご注意」ください。
「鹿島神宮」公式WEBの「掲載文」
「鹿島神宮」公式WEB掲載ページURL
https://kashimajingu.jp/news/%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e7%8a%ac%e7%8c%ab%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%a2%83%e5%86%85%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%93%e3%81%bf%e7%a6%81%e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
掲載内容
ペット(犬猫等)の境内連れこみ禁止について
令和5年5月2日
鹿島神宮境内は御祭神をお祀りしている場所です。
その境内は清浄が保たれていなければならない場所とされており、元々ペット(犬猫等)の立ち入りを禁止しておりましたが、
昨今、境内にペットをお連れの方と参拝者の方のトラブルが多数発生し、多くのお声を頂くようになりました。
当宮では、御祭神の神域を守り清浄を保つため、また参拝者間のトラブルを避けるため、
アレルギー(犬猫アレルギー)の方の発症を防ぐため、境内へのペット(犬猫等)の連れ込みを禁止致します。
皆さまの御理解と御協力をお願い申し上げます。
※盲導犬・介助犬の同伴は許可致します。
Back
「東国三社」の「参拝順序」

「東国三社」の
「鹿島神宮」「香取神宮」「息栖神社」の参拝順序は、
特に、決まった「ルール」「参拝順序」はない。
自身の都合に合わせて参拝すれば良いとされている。
だが、
「鹿島立ち」という言葉がある。
「鹿島神宮」を「一番初め」に参拝するのが良いという説も存在する。
「日本建国」「武道」の「神様」である「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を祀っている「鹿島神宮」には、
多くの「武将」「旅人」が、「戦」「旅」へと旅立つときに、
「鹿島神宮」を参拝していったと伝えられており、
「武運」「安全」を祈願して出発したことから「鹿島立ち」ということがが生まれたとのこと。
そのため、
「物事」を始めるのに、「鹿島神宮」がふさわしい場所とされ、
「一番初め」に「鹿島神宮」を参拝するのが良いという説がある。
Back
「東国三社」とは

「鹿島神宮」は、
「日本神話」の時代から続く、
「長い歴史」「深い信仰」に支えられた、日本を代表する「神社」の一つ。
「鹿島神宮」は、
「香取神宮(千葉県香取市)」「息栖神社(いきすじんじゃ)(茨城県神栖市)」と共に、
「東国三社」の1つにもなっている。
江戸時代には、
「東国三社」の参拝を、「お伊勢参りのみそぎ参り」と呼ばれており、
関東より北の人は、
「伊勢神宮」を参拝した後に、「東国三社」を参拝していた。
「禊ぎ」の「下三宮巡り」と称することもあるらしい。
「東国三社」の「御利益」が、とても凄いと、 江戸時代では、相当な人気を誇っていたという。
現在も、「関東最強のパワースポット」と言われている。
東国三社
Address : 〒314-0133 茨城県神栖市息栖2882
「東国三社」は、
位置関係を地図で見て、線で繋ぎ合わせると、
「二等辺三角形」になっていて、
その「トライアングルゾーン」の中では、不思議なことが起こり、
強力なパワースポットとなっていて、
「夢をじつげんするためのパワーをもらえる」という噂があるそう。
「東国三社」の「3つの神社」は、
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、活躍した「神々」を祀っていて、
古くから人々の信仰を集めてきた。
「日本神話」における、
「国譲り」の際に活躍した
・武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)(鹿島神宮): 「鹿島神宮」の「主神」で、国譲りの際に大国主神を従わせた神として登場。
・経津主大神(フツヌシノカミ)(香取神宮): 「香取神宮」の「主神」で、「武甕槌大神」とともに国譲りに参加した神。
に加え、
「土地」を開拓したといわれる「岐神(クシノカミ)」
・岐神(クシノカミ)(息栖神社): 息栖神社の主神で、国土を開拓した神として伝えられています。 を祀っている。
古くから「関東地方の総鎮守」として崇敬されてきた。
「三重県伊勢市」にある最初の神宮「伊勢神宮」に匹敵するほどの信仰を集めていたと言われている。
「江戸時代」には、「お伊勢参りのみそぎ参り」と言われ、
「伊勢神宮」の参拝後に、「東国三社」を参拝することが一般的だった。
「東国三社」は、
「パワースポット」としても有名で、
「東国三社」の「各神社」は、それぞれ「強い霊力」を持つ「パワースポット」としても知られている。
「東国三社」の特徴
| 神社名 | 特徴 |
|---|---|
| 鹿島神宮 |
関東最強のパワースポットですべての始まりの地と呼ばれています。日本最古とされる神宮の一つ。 創建は、「紀元前660年(神武天皇元年)」に創建された由緒ある神社。 全国に、「約600社」ある「鹿島神社」の「総本山」。 「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、 活躍した「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を祀っていて、 「勝負の神様」として知られている。 「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、「鹿島神宮」の「主神」で、 「国譲り」の際に「大国主神」を従わせた神として登場している。 「力強いエネルギー」を感じられる「パワースポット」。 「日本建国」「武道」の「神様」として知られ、主な御利益は、「勝利祈願」「必勝祈願」。 「縁結び」「安産祈願」などの御利益もあるそう。 「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、 「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、 「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。 「力」と「勇猛さ」を象徴する神。「武力」で相手を圧倒する。 「武甕槌大神」が、「力」によって「国」を平定した。 |
| 香取神宮 |
「香取神宮」は、全国に「約400社」ある「香取神社の総本社」。 「決意する場所」とも言われており、古くから「伊勢神宮」「鹿島神宮」と並んで、 「神宮」の名称を使うことが許された数少ない「神社」。 「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、 活躍した「経津主大神(フツヌシノカミ)」を祀り、 「学業成就」「交通安全」の「神様」として信仰されている。 静かで厳かな雰囲気の神社。 「経津主大神(フツヌシノカミ)」は、 「香取神宮」の「主神」で、「武甕槌大神」とともに使者として同行し、 「知恵」と「策略」を使って、「国譲り」に貢献した「神」。 「経津主大神(フツヌシノカミ)」は、 「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」と共に、 「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、 「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。 「知恵」と「策略」を象徴する神。「巧みな言葉」や「仕掛け」で相手を説得する。 「経津主大神」は、「知恵」と「策略」によって「国譲り」を成功させた。 |
| 息栖神社 |
「2000年以上」の歴史を持ち、「鹿島神宮」「香取神宮」と共に、「東国三社」の1つ。 「土地」を開拓したといわれる「岐神(クシノカミ)」を祀り、 「土地の神様」として崇敬されている。 古くからの歴史と神秘的な雰囲気が魅力。 水上交通が盛んな頃は「息栖河岸」とともに、まちの賑わいを創り出してきた。 「岐神(くなどのかみ・路の神・井戸の神)」を主神とし、 「相殿」に、「天鳥船神(あめのとりふねのかみ)(交通守護の神)」「住吉三神(海上守護の神)」を祀っている。 「岐神(クシノカミ)」は、 「日本神話」において、土地を開拓し、人々に農耕を教えたとされる神様。 「国譲り神話」には、活躍が記載されていないが、日本の国土形成に大きく貢献した神。 荒れ果てた土地を開墾した「土地の開拓」、 人々に農耕の方法を教え、食料の自給自足を実現させた「農耕の指導」、 様々な「文化」「技術」を伝えた「文化の伝承」 などの実績があったそう。 |
Back
「国譲り神話」とは

「国譲り神話」は、
日本の古代神話「日本神話」において、
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を中心とする「高天原(たかまがはら)の神々」が、
「地上」を治めていた「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に「国を譲る物語」。
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を中心とする
「高天原(たかまがはら)の神々」が、
「天照大御神」の子「邇邇藝命(ニニギノミコト)」が、
「高天原」から地上へ降り、「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」よう要求した。
この時に、
「鹿島神宮」「香取神宮」の「御祭神」である
「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」と「経津主大神(フツヌシノカミ)」が、
「使者」の中心的な1人として、それぞれ活躍した。
「大国主神(おおくにぬしのかみ)」は、
最初は抵抗するも、最終的に、
「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」の意向を受け入れ、「国を譲る」ことを決意する。
「島根県出雲市」にある「出雲大社」は、
国を譲った「大国主神(おおくにぬしのかみ)」を祀るために、
「創建」された「神社」で、
格式の高い神社であり、「縁結び」の御利益がある神社として、
「出雲大社」は知られている。
「国譲り神話」の持つ意味は、
「天照大御神」の「子孫」である「天皇」が、
「日本の統治者」となる「正当性」を示すために用いられている。
「天照大御神」を中心とした「高天原の神々」と、
「大国主神」を中心とした「出雲の国神々」を統合し、
「一つの国家」としての「日本」を形成する物語として位置づけられている。
「地方を治めていた神々」と、「中央を治める神々」との関係を示し、
「中央集権的な国家形成のプロセス」を神話的に表現している。
「国譲り神話」は、
日本の歴史と文化を理解する上で非常に重要な神話。
「国譲り神話」を通じて、
「日本の神々」「古代の人々の信仰」「国家形成の過程」など、
より深く知ることができるようになっている。
Back
「鹿島神宮」とは

「茨城県鹿嶋市」に鎮座する「鹿島神宮」は、
全国に点在する「鹿島神社」の「総本社」。
「社格」は、「常陸国一之宮」。
歴史が古く、
「関東」の「始まりの地」とも言われている。
「東京ドーム15個分」に及ぶ広大な「境内」を持っており、
古くは、「源頼朝」や「徳川家康」をはじめとする、
歴史に名を残す「武士」が参拝に訪れている。
「日本神話」に登場する「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を祀る
古くから存在する神社「古社」。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
日本神話において「国譲り」の際に活躍し、日本の国土を平定したとされる「神様」。
「神武天皇」の「東征」の際に、
「神武天皇」を助け、その「神恩」に報いるために、
「紀元前660年(神武天皇元年)」に、
「鹿島神宮」が創建されたと伝えられている。
歴史が古く、
「奈良時代」の「713年(和銅6年)」に編纂(へんさん)が開始され、
「721年(養老5年)」頃に完成したとされる
「約1300年前」の古書「常陸国風土記」に、「鹿島神宮」の名前が記されており、
古くから信仰を集めていることが知られている。
「常陸国風土記」は、
「常陸国(現在の茨城県の大部分)」の「地理」「歴史」「伝説」などをまとめた「地方誌」。
Back
「鹿島神宮」の「御祭神」

「鹿島神宮」の「御祭神」は、
「日本神話」に登場する「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
日本神話において「国譲り」の際に活躍し、日本の国土を平定したとされる「神様」。
「武道」「国家鎮護」「東国鎮護」「雷」「剣」「相撲」「地震」の「神」としても知られる。
日本に、地震を引き起こすとされている「大ナマズ」が暴れているのを、頭を押さえつける逸話が有名。
日本神話のエピソードでは、
「建御名方(タケミナカタ)」と「相撲の力比べ」をして勝利したという言い伝えが残っていて、
両国国技館の壁画には、「国護りの力比べ」というタイトルで、その場面の「壁画」が飾ってある。
「日本神話」に登場する「国譲り」の際に、
活躍した御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「勝負の神様」として知られている。
「力強いエネルギー」を感じられる「パワースポット」。
「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「天照大御神」から地上へと遣わされた「使者」の1人として、
「大国主神(おおくにぬしのかみ)」に、「国を譲る」ように交渉をしたとされている。
「力」と「勇猛さ」を象徴する神。「武力」で相手を圧倒する。
「武甕槌大神」が、「力」によって「国」を平定した。
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「天照大御神」の子孫にあたる日本最初の「天皇」である
「神武天皇」の「東征」を行っている時に、
「神武天皇」を助けるなどの功績を残していた。
日本の初代天皇「神武天皇」となる「彦火火出見(ひこほほでみ)」が、
日本を平定する旅の途中に、「熊野の土地神」の毒に犯された。
軍はどんどん倒れ、窮地に陥っていた。
それを、「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」が、
以前、大国主神から譲り受けた神剣「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」の神威を使い、
「彦火火出見」の軍を救い、見事に息を吹き返し勝利させた。
その後、「彦火火出見(ひこほほでみ)」は、
「神武天皇」として「日本の初代天皇」に御即位された。
「神武天皇」は、窮地から救われた「神恩」として、
「紀元前660年(神武天皇元年)」に、
「鹿島神宮」を創建し、「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を「御祭神」として祀った。
その「鹿島神宮」が、現在まで、「鹿島神宮」として受け継がれてきた。
Back
「鹿島神宮」の「御利益」

「鹿島神宮」の「御利益」には、
主に
・武運
・勝負運
・勝利祈願
・必勝祈願
などがあり、
その他には、
・縁結び
・安産祈願
などの御利益もあるそう。
「鹿島神宮」の「御祭神」である「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」は、
「強さ」の象徴であり、「日本神話最強の武神」「勝利の神」。
「御祭神」の御威光もあり、「武運」「勝負運」の「御利益」があり、
「勝利祈願」「必勝祈願」などに訪れる人が多い。
「鹿島神宮」の「御神宝」である「常陸帯(ひたちおび)」にちなんで、
「縁結び」「安産」の御利益もあり、
「縁結び祈願」「安産祈願」に訪れる人も多い。
Back
「鹿島神宮」の「歴史」

「鹿島神宮」の「創建」は、
「紀元前660年(神武天皇元年)」で、
創建され多のは、
「神武天皇」の「東征」の際にも、
「神武天皇」を助け、その「神恩」に報いるためと言われている。
「古代~中世」になると、
「朝廷」から「蝦夷の平定神」として、また「藤原氏」から「氏神」として崇敬された。
「平安時代」には、
朝廷の重要な祭事が行われたり、「国家的な神社」としての地位を確立していた。
「江戸時代」になると、
「徳川家康」をはじめとする「武家」からの信仰も厚く、
「社格」は、「官幣大社」に昇格した。
「近代」以降でも、
「明治維新後」には、その「格式」は保たれ、
現在では、「神社本庁」の「別表神社」に指定されている。
Back
「鹿島神宮」の「見どころ」

「鹿島神宮」の「見どころ」には、
下記のような施設がある。
| 施設 | 説明 |
|---|---|
| 「社殿」「本殿」「石の間」「幣殿」「拝殿」 |
「社殿」「本殿」「石の間」「幣殿」「拝殿」は、「4棟」の「複合社殿」となっている。 「1605年」に「徳川家康」から、「1649年」に徳川二代目将軍「徳川秀忠」から寄進されることによって、 社殿一式が造営された。 |
| 本殿 |
「三間社流造」の美しい「本殿」。 「国の重要文化財」に指定されている。 御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」が、「本殿」に祀られている。 |
| 拝殿 | 朱塗りの鮮やかな「拝殿」は、荘厳な雰囲気を醸し出している。 |
| 神苑 | 広大な「神苑」には、様々な種類の樹木が生い茂り、四季折々の美しい風景を楽しむことができる。 |
| 宝物館 | 「国宝」「重要文化財」をはじめとする「貴重な宝物」の数々が、収蔵されている。 |
| 楼門 |
「国の重要文化財」に指定されている。 「鹿島神宮」の「楼門」は、 「熊本県の阿蘇神社」「福岡県の筥崎宮」の「楼門」と共に、「日本三大楼門」の1つ。 「1634年」に、水戸徳川初代藩主「徳川頼房」によって奉納されたもの。 「楼門」の上部に飾られている額「鹿島鳥居」は、「東郷平八郎」が書いたもの。 「楼門」の左右にある「回廊」も、「鹿島市指定文化財」に指定されている。 「楼門」をくぐって右には、「樹齢700年」の「高さ40m」の御神木「二郎杉」がある。 |
| 御祭神の要石 |
「パワースポット」として知られていて、 地震をもたらす都されている「大ナマズ」を押さえこんでいる「霊石」。 地上には、極一部しか露出しておらず、その大部分は地中深く埋まっているとのこと。 「鹿島要石真図」では、 「タケミカヅチ」が、「大ナマズ」の頭を刀剣で押さえつけている図が掲載されている。 |
| 御手洗池 |
「御手洗池」には、 「1日40万リットル以上の湧水」が湧いていると言われる「御神水」。 水面に映し出される「鳥居」が神秘的な雰囲気を持っている。 「御手洗池」の近くには、「湧き水」を使用した「甘味処」がある。 |
| 鹿園 |
「神の使い」とされている鹿「神鹿」。 奈良県にある「春日大社」が創建されるときに、 御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」が分祀され、 「奈良県」まで御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を「鹿」が連れて行ったと言われている。 その鹿「神鹿」の末裔たちが、現在も「約20頭」ほど飼育されているとのこと。 |
Back
「鹿島神宮」の「祭事」
「鹿島神宮」の「地図」
電車
「鹿島神宮」は、「東京方面」から電車で訪れるには、
「JR成田線 香取駅」から茨城方面へと進む
「JR鹿島線」に乗り換え、「鹿島神宮駅」で下車する。
他の路線はなく、
「JR鹿島線 鹿島神宮駅」が最寄り駅。
「東京駅」からだと、
「料金1980円」ほどで「約2時間30分」ほどかかるらしい。
長距離バス
「東京駅」からは、「鹿島神宮駅」までの「長距離バス」が発着しているので、
その路線で訪れるのが楽そう。
「約2時間」ほどで、「料金2100円」で乗車できるらしい。
車(普通自動車)
「東京(首都高速 箱崎IC)」から「茨城県(東関東自動車道 潮来IC)」までは、 「ETC」を利用することで、
「料金約3000円ほど」で、
到着までに、「約1時間30分」ほどかかる。
休憩などを入れると、更に時間は長くなる。
Back
「鹿島神宮」の「駐車場」

「鹿島神宮」の周辺には、
無料の「鹿島神宮 参拝者用駐車場」が「3カ所」に用意されている。
その他にも、
「鹿島神宮駅」に、大きめの駐車場が「2カ所」。
街中には「市営駐車場」もある。
一般の、「有料時間貸駐車場」もあるので、
「駐車場」は多い。
平日であれば、問題なく「駐車場」を利用できることが多い。
「鹿島神宮」周辺にある「駐車場」
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮下2丁目8−8
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1丁目13
Address : 〒314-0032 茨城県鹿嶋市宮下3丁目1−2
Back
「春日大社」は「鹿島神宮」から御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を勧請した

「平城京」に「遷都」された際に、
「藤原氏」が、「奈良」に「春日大社」を創建した。
「鹿島神宮」の御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を「春日大社」へ「分祀」し迎え、
「藤原氏」一族の「氏神」として祀ったとされている。
その時に、
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)」を
奈良県にある「春日大社」まで送り届けたのが、
「鹿島神宮」にいる鹿「神鹿」だと言われている。
「鹿」は「神の使い」として扱われており、
現在でも、「約20頭」程が、
「鹿島神宮」の「奥参道」にある「鹿園」で飼育されている。
Back
「鹿島神宮」周辺にある美味しそうな「飲食店」
「鹿島神宮」周辺にある
美味しそうな「飲食店」をセレクト。
「鹿島神宮」に参拝したときに、
訪れてみるのも良さそう。
評判の良い、美味しそうな「お店」を掲載しています。
Back
美味しそうな「飲食店」をセレクト。
「鹿島神宮」に参拝したときに、
訪れてみるのも良さそう。
評判の良い、美味しそうな「お店」を掲載しています。
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1丁目1−2
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中1974−2
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4643−10
Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中5丁目10−14
Address : 〒314-0017 茨城県鹿嶋市旭ケ丘2丁目4−3
Back
「鹿島神宮」を参拝する前に、「愛犬散歩」が出来そうな「スポット」
「鹿島神宮」は、
「東国三社」の中で、
一番最初に参拝することが多い「神社」。
「愛犬」は、
車でお留守番をしてもらう前に、
十分に散歩をさせて、満足してもらっていた方が良い。
疲れて眠っている間に、
参拝を済ませてしまうのが、良い方法。
「鹿島神宮」の近くには、
「鹿島城」だった「城跡」が「公園」になっているので、
「鹿島神宮」に一番近い散歩スポット。
「海」も近く、
「平井海水浴場」「日川浜海水浴場」で遊んでから、
「鹿島神宮」を参拝するのも良い。
Back
「酒々井PA(下り)」で「休憩」と「愛犬散歩」
 Image is 「酒々井PA(下り)」にある「スターバックス」
Image is 「酒々井PA(下り)」にある「スターバックス」「愛犬」と一緒に、
「鹿島神宮」を訪れるのなら、
「酒々井PA(下り)」は、立ち寄った方がよいかも。
一番奥の方に、
芝生がある散歩ができるスペースがあるので、
「愛犬」の気分転換ができる。
綺麗な芝生なので、愛犬も喜ぶスペース。
喫煙所が近いので、風向きには注意。
「スターバックスコーヒー」もあるので、
お気に入りのドリンクを購入して、
鹿島神宮までの残りのドライブを楽しめる。
朝食に、「コーヒー」と「サンドウィッチ系」を購入するのもよい。
「スタバ」の「サンドウィッチ系」は美味しいものが多い。
「パン屋さん」の「カレーパン」は、
なかなか美味しい「カレーパン」。
ちょこっとおすすめ。
Back
「道の駅 いたこ」で「愛犬散歩」「休憩」「買い物」
 Image is 「道の駅 いたこ」公式WEB
Image is 「道の駅 いたこ」公式WEB「東京」から、
「東関東自動車道」を通って、「鹿島神宮」を訪れると、
「道の駅 いたこ」の前を通る。
「9時〜19時」で営業をしているので、
「愛犬散歩」「休憩」「買い物」ができる。
「鹿島神宮」は、「愛犬同伴NG」なので、
「道の駅 いたこ」でも、
「愛犬散歩」をしておくと良い。
周辺で収穫される「農作物」なども売っているので、
安くて新鮮な食材の買い物もできる。
帰り道に寄るのもおすすめ。
色々な野菜が、「150円」とか「100円台~300円台」と、
かなり割安に販売されている。
サラダ野菜を購入して帰るのも楽しい。
「珍しい野菜」も販売されていたりする。
「ドッグラン」は、「建物」の裏側にある
「道の駅 潮来(いたこ)」に寄ったが、
あまり「愛犬散歩」のスペースがなかったと思っていたら、
建物の裏側にある「グランドゴルフ場」の手前にあったらしい。
気付かずに、訪れなかったが、今度訪れてみよう。
あまり「愛犬散歩」のスペースがなかったと思っていたら、
建物の裏側にある「グランドゴルフ場」の手前にあったらしい。
気付かずに、訪れなかったが、今度訪れてみよう。
Back
美味しい「チヂミ」が食べられる「ちっちゃな韓国おおかみ」
 Image is 「ちっちゃな韓国おおかみ」
Image is 「ちっちゃな韓国おおかみ」

|


|
韓国料理の美味しい「チヂミ」が食べられるお店。
「テイクアウト専門店」だが、食べた「海鮮チヂミ」が美味しかった。
「Google Map」での評価も「4.0以上」なので、
美味しいと評判のお店なのかも。
「チヂミ」は、
「ふわっ」「モチっ」としていて、
「タレ」もとても美味しい。
合わせて食べると、とても美味しい。
「海鮮チヂミ」は、1つ「1200円」だが、
ボリュームもあって、価格が高い気はしない。
「あまりお腹が空いていない!」と言っていた人が、
最終的に、少しもくれず、平等の半分ずつ食べるような結果に。。。。。。
むしろ、大きいのばかり食べてたので、少し多く食べられたと思っている。
寒かったので、「焼きたて」がとても美味しかった。
人の「あまりお腹が空いていない!」という言葉の信用性を、
凄く下げる力を持つ「海鮮チヂミ」でした。
写真が、「海鮮チヂミ1人前」。
2枚重ねになっているので、カットされたものが、
「16枚ほど」入っている。
注文をしてから焼いてくれるので、
少し待ち時間がありました。
お1人でやられていたので、忙しいときには、
トイレや周辺のお店を見たりと対策が必要。
次回も、「OPEN」していたら、
購入したいと思います。
Back
「東日本大震災」で倒壊後に再建された「二之鳥居」

Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2306−1
Address : 〒314-0036 茨城県鹿嶋市大船津2251 沖

|

|
「一之鳥居」は、
「二之鳥居」から真っすぐ前に伸びる
「北浦」「鰐川」の川岸の水の中にある。
Address : 〒314-0036 茨城県鹿嶋市大船津2251 沖
橋ができる以前の「鹿島神宮」の入口は、
「一之鳥居」周辺だったとされていて、
「舟」で対岸から着岸していたとされている。
現在の「鹿島神宮」は、
「二之鳥居」の手前からとなっており、
境内に入ると、すぐに自然豊かな参道となる。
「二之鳥居」から「奥宮」の前まで、
一直線の参道が突き通っている。
「鹿島神宮」の「二之鳥居」は、
「鹿島神宮の森」にある「樹齢500~600年」の「杉の木4本」を材料として再建されたもの。
「初代の二之鳥居」は、
「1968年(昭和43年)」に、「茨城県笠間市稲田産」の「御影石」で造られ、
「高さ18.5m」「幅22.5m」を誇る「日本一の花崗岩製の鳥居」だった。
だが、
「2011年(平成23年)3月11日」の「東日本大震災」で倒壊してしまった。
その時に、現在の「二之鳥居」が再建という形で造営された。
Back
「水戸藩」の初代藩主「徳川頼房」により造営された「楼門」

 「鹿島神宮」の「楼門」は、「日本三大楼門」の1つ。
「鹿島神宮」の「楼門」は、「日本三大楼門」の1つ。「日本三大楼門」は、
・鹿島神宮(茨城県)
・筥崎宮(はこざきぐう)(福岡県)
・阿蘇神社(熊本県)
の「楼門」が選出されている。
いずれも「国の重要文化財」に指定されている。
「鹿島神宮」の「楼門」は、「朱塗り」で、「高さ13m」。
「水戸藩」の初代藩主「徳川頼房」が、「1634年」に造営したもの。
「鹿島神宮」の境内には、
自然が豊かに生きていて、
「拝殿」「本殿」「奥宮」は、無駄のない、シンプルな装飾が特徴。
唯一、「楼門」は、
鮮やかな「朱色」になっており、
「緑」の多い自然の中で、
「朱塗りの楼門」は、ひときわ存在感を感じる建物になっている。
色鮮やかで、「写真映え」もすることもあり、
「鹿島神宮」の代表的な建物の1つになっている。
Back
徳川家2代目将軍「徳川秀忠公」によって寄進された「拝殿」「本殿」

「二之鳥居」から「奥宮」へと繋がる「参道」を 「200m」ほど進んだ「参道」の道沿いにある「拝殿」「本殿」。
そこから「350m」ほど進んだ所に「奥宮」が存在する。
「二之鳥居」から「200m」ほど進んだ
「参道」の「右側」にある「拝殿」は、
「本殿」の手前にあり、
参拝者が、「御祭神」をお参りする場所となっている。
「鹿島神宮」の「拝殿」は、「桁行五間」「梁間三間」の「入母屋造」で、
「檜皮葺」の「屋根」で作られている。
現在の「拝殿」は、
「1619年(元和5年)」に、徳川家2代目将軍「徳川秀忠公」によって寄進されたもの。
「江戸時代初期」の建築様式を、現代に伝える貴重な建物。
「本殿」は、
「御祭神」を祀っている「最も申請な場所」となっており、
「拝殿」の奥に位置している。
「鹿島神宮」の本殿は、
「三間社流造」という形式で、「檜皮葺の屋根」で作られている。
「本殿」も同じく、
「1619年(元和5年)」に、徳川家2代目将軍「徳川秀忠公」によって寄進されたもの。
「拝殿」の奥に位置していて、
なかなか見えることがないが、
「装飾」は控え目で、佇まいは荘厳、申請な雰囲気を持っている。
Back
「神様の使い」とされる「鹿」と触れ合える「鹿園」

「鹿島神宮」は、
「拝殿」「本殿」を抜けて、
「奥宮」へと向かう「奥参道」の途中に、
多くの「鹿」が飼育されている「鹿園」がある。
「鹿島神宮」の「鹿」は、
「神様の使い」として大切に扱われている。
「鹿島神宮」では、
「奈良県」にある「春日大社」が創建された際、
御祭神である「武甕槌命(タケミカヅチノミコト)」が勧請された。
その際、「武甕槌命(タケミカヅチノミコト)」が、「春日大社」へと旅立つ際に、
「神」から遣わされた「鹿」に乗って旅立ったと言われている。
その「鹿」は、鹿の神「天の迦久神(あめのかぐのかみ)」とのこと。
「春日大社」でも、「鹿島神宮」より、
「鹿」に乗って、御祭神「武甕槌命(タケミカヅチノミコト)」が到着したと言われている。
その伝説から、
「鹿島神宮」では、「鹿」を「神の使い」として信じ、大切に扱われてきたとのこと。
現在の「鹿園」にいる「鹿」たちは、
「春日大社」へと、御祭神「武甕槌命(タケミカヅチノミコト)」を連れて行った「鹿」を保護した
「春日大社」にいる「鹿の子孫」を受け継いだ「鹿」とのこと。
現在、「約20頭」の鹿たちが、
「鹿島神宮」の「鹿園」で生活している。
「鹿園」では、
近くに「売店」があり、
「100円」で「ニンジンのエサ」が購入でき、
「鹿」たちに、手渡しでエサを与えることができた。
売店は、閉まっていることも多いが、
営業していたら、「エサやり」はおすすめ。
「鹿園」のフェンスは、
「口先」だけ出せるように工夫がしてあるので、
欲しがる鹿の口に、直接、ニンジンを入れることができる。
「強い鹿」が、前を陣取って、
後の小さな「鹿」たちが、「ニンジン」を食べることが出来ないので、
小さくちぎって、奥に投げてあげると、
子供の鹿にも、ニンジンをあげる事ができる。
大きな角を持った大人の鹿は、
突然、角をぶつけ合ってケンカを始めることもあるので注意。
ちなみに、
同じ「鹿島」を拠点とする「プロサッカーチーム」の
「鹿島アントラーズ」の「アントラー」は、
「鹿の枝角」を意味している。
名前の由来は、「鹿の枝角」であるらしい。
Back
徳川幕府初代将軍「徳川家康公」によって奉納された建物「奥宮」

「鹿島神宮」の「奥宮」は、
「拝殿」「本殿」から「奥参道」を歩いて「約300m」ほどのところにある。
現在の「奥宮」は、
「1605年(慶長10年)」に、徳川幕府初代将軍「徳川家康公」によって「本殿」として奉納されたもの。
「1619年」に、徳川幕府2代目将軍「徳川秀忠」によって、
現在の「本殿」が建立されたため、現在の「奥宮」として移された。
現在、「国の重要文化財」にも指定されている。
「鹿島神宮」の「奥宮」には、
御祭神「武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)」の「荒御魂(あらみたま)」が祀られている。
「荒御魂(あらみたま)」とは、神様の「荒々しい側面」を表し、「勇猛果敢な力」を象徴している。
一般的な「参拝」としては、
「本殿」では、
日々の感謝を伝え、
具体的な「お願い事」は、「荒御魂(あらみたま)」にお願いすることになっているそう。
「奥宮」の前にある「芭蕉の句碑」の上部は、
耳を近づけると「海の音」が聞こえる
という言い伝えがあるそう。
良かったら試してみると良い。
Back
「大地震」を引き起こす「大ナマズ」を封じている「要石(かなめいし)」

Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2306−1
「奥宮」から、
「御手洗池」とは「逆の方向(南南東)」へ
少し歩いて行くと、
「大地震」を引き起こすという「大ナマズ」を封じているという
神様が置いた霊石「要石(かなめいし)」に辿り着く。
「鹿島神宮」にある「要石」は、「頭」。
「香取神宮」にある「要石」は、「尾」。
の2カ所を封じて、「大ナマズ」を封じていると言われている。
どんだけ「大きなナマズ」なんだ?という封じ方。
実際に見てみると、
「要石」は、
ほんの小さな石に見えるが、
地下に埋まっている巨大な石と言われている。
Back
美味しそうな「そば」「だんご串」が食べられる「湧水茶屋一休 ひとやすみ」

Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2306−1 鹿島神宮境内
「奥宮」から「北北東」に進むと、
「御手洗池」があって、
手前に、
美味しそうな「蕎麦」「だんご串」などが食べられる
「湧水茶屋一休 ひとやすみ」がある。
「御手洗池」に流れ込む「御神水」を使って料理しているメニューもあった。
「御神水」を持って帰れるように、
「空のペットボトル」も販売されている。
「お蕎麦」は、店内で食べられるが、
混んでいる時期は、満席になっていることが多い。
かなり待ち時間が長い時もあるみたい。
店の前では、
手軽に食べられる「だんご串」などがあったりする。
季節によって、販売しているものは異なるみたい。
訪れる度に、少しずつ違うものが販売されている。
「だんご串」は、いつもあった。
Back
湧き出る「御神水」が溜まってできた池「御手洗池」

Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中
「御手洗池」は、
古くから、「身」を清める「禊の場」として使われてきた「神聖な場所」。
現在でも、
毎年1月になると、「大寒禊(だいかんみそぎ)」という、
約200人にも及ぶ人々が、寒い冬の気温の中、
「御手洗池(みたらしいけ)」に入り、「禊」をするそう。
神社においての「禊(みそぎ)」とは、
「罪」「穢れ(けがれ)」を落とし、
心身を清浄にするための「神道」における「伝統的な儀式」のこと。
古くは、「海」「川」で身を清める「自然の禊」が一般的だった。
神社などでも、「禊」が行われるようになり、現在では、
「神社」「お寺」などでも「禊」が行われるのが一般的となったそう。
「鹿島神宮」の「御手洗池(みたらしいけ)」は、 1日に、「40万リットル以上」が湧き出ている「御神水」が溜まって出来ている「池」。
「御神水」の「透明度」は、かなり高く、
「池底」や「魚」が見えるほど、綺麗で、美しい。
「御神水」は、汲んで持ち帰ることができる。
「容器」を持参して、
自宅で利用することも可能。。
Back
参拝帰りに御当地ファミリーレストラン「坂東太郎」で美味しい食事

Address : 〒314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中1974−2
Address : 〒314-0135 茨城県神栖市堀割3丁目1−10
Address : 〒289-0312 千葉県香取市本郷711
御当地ファミリーレストラン「坂東太郎」は、
「茨城県発祥」の「御当地ファミリーレストラン」で、
「煮込みうどん」「そば」「お寿司」「とんかつ」「うなぎ」などの
豊富なメニューを取り揃えている。
「最大1kg」の「大盛り蕎麦」メニューもあって、
「お蕎麦」を食べたいときに、
とても満足なメニューもある。
「蕎麦」「うどん」は、比較的太めで、コシもあり、美味しい。
「とんかつ」は、
グループブランドに、「かつ太郎」という「とんかつ専門店」もあるので、
美味しさに期待ができる。
美味しいメニューが多いので、
「茨城県」を訪れると、
「坂東太郎」を訪れることも多い。
お店の「外観」が、
和風の「鎧兜」をイメージした店舗外装が特徴。
店舗内は、
「テーブル席」「座席席」「半個室」「個室」など、
比較的ゆったりとした「席」の間隔があり、
とても落ち着いて、食事をすることができる。
清潔感のある店内で、
親切な店員さんが対応してくれることが多い。
Back