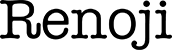「天ぷら」とは
「天ぷら」とは
INDEX
はじめに
「寿司」と共に「日本料理」を代表する「料理」として知られる「天ぷら」。
素材の味を最大限引き出し、
「サクッ」とした食感が、さらに美味しさを引き上げる。
「天ぷら」の発祥は、
「ポルトガル」の「フリッター」という揚げ物料理の伝来か、
「日本」で「独自に生まれた料理」という2説があるそう。
「発祥」については、
明確な答えは、この先も出ないと思うが、
間違いなく、今の「天ぷら」は、
日本だけにしかない、海外の人も美味しいと喜ぶ「日本料理」の1つになっていることは間違いない。
Back
「天ぷら」とは
「天ぷら」は、
「日本料理」を代表する「揚げ物料理」の1つ。
「魚介類」「肉類」「野菜」などのあらゆる食べ物に、
「小麦粉」をを主とした「衣」を付け、「油」で揚げたもの。
「天ぷら」の料理工程である「揚げる」というのは、
「高温の油」で、短時間で揚げることで、表面の「衣」で「密閉空間」を生み出す。
「素材の水分」が「蒸発」し、水蒸気によって食材は蒸され、食材に「熱」が通る。
食材の「水分」がなくなることで、「旨味」だけが残り、凝縮され、
美味しい「天ぷら」が完成する。
「天ぷら」を「蒸し料理」と表現する人もいる。
「天ぷら」の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 衣 | 「小麦粉」「卵」「冷水」などを混ぜ合わせた「衣」を食材にまとわせ、「油」で揚げることで、サクサクとした食感を生み出す。 |
| 素材 | 「魚介類、野菜、山菜など、様々な素材を揚げることができます。素材の味を生かすため、薄味に仕上げるのが特徴。 |
| 揚げ方 | 「高温の油」で、短時間で揚げることで、素材の水分を閉じ込め、旨味を凝縮させる。「蒸し料理」の1つと言われることもある。 |
| タレ | 「天つゆ」と呼ばれる、「だし汁」「醤油」「みりん」などを合わせた美味しい「タレ」につけて食べるのが一般的。 |
Back
「天ぷら」の歴史
「天ぷら」の起源は、
「室町時代(1336年~1573年)」に、
「ポルトガル」から「フリッター」という揚げ物料理が伝わってきたのが始まりとされている。
「魚」「野菜」に「衣」を付けて揚げた料理が、
「長崎」に伝わったとされている。
「天ぷら」の語源は、
「テンポラ(Tempera)」という「四季に行う斎日」という意味の言葉が語源という説がある。
もう一つの説は、
「日本」で独自に生まれた料理という説。
「天ぷら」に似ている料理が、古くから存在しており、
「独自」に発展したとする説もある。
「江戸時代」には、
「天ぷら」が、庶民の間で、広く食べられるようになり、
様々なバリエーションが生まれた。
「発祥」の説は、
明確にならないほど、歴史は古く、
「江戸時代」から現代にかけて、
更に、独自の「日本料理」としての「天ぷら」に発展した。
現在では、
「海外の人」が、美味しいと好んで食べる
「寿司」に並ぶ「日本料理」となった。
Back
「多店舗展開」している「天ぷら店」
「天ぷら」の「名産地」と呼ばれる「エリア」
「天ぷら」は、
日本を代表する料理の一つで、全国各地で様々な「食材」を使った天ぷらが楽しまれている。
その中でも、
「天ぷらの名産地」と言われているエリアがある。
「天ぷらの名産地」と呼ばれる「エリア」には、
江戸前天ぷら(東京)
「東京の天ぷら」は、江戸時代に生まれた「江戸前天ぷら」が有名。新鮮な魚介類や野菜を使い、素材の味を生かしている。特に、「アナゴ」「エビ」「キス」などの「魚介類」の「天ぷら」が美味しい。
関西風天ぷら(大阪)
「大阪の天ぷら」は、江戸前天ぷらとは異なり、「衣」に「砂糖」「醤油」を加えて味付けするのが特徴。また、「野菜」「肉」の天ぷらが多く、素材の甘みや旨味を引き出す揚げ方がされている。
京料理の天ぷら(京都)
「京都の天ぷら」は、「京料理」の一つとして、上品な味わいが特徴。新鮮な「京野菜」「旬の魚介類」を使い、素材の持ち味を生かした繊細な天ぷらを楽しめる。
博多天ぷら(福岡)
「福岡の天ぷら」は、新鮮な魚介類を使った「博多天ぷら」が有名。特に、「イカ」「エビ」の天ぷらが美味しい。「明太子」「ゴボウ」など、地元の食材を使った天ぷらも人気。
讃岐天ぷら(香川県)
地元の野菜や魚介類を使った天ぷらで、素材の味を生かしたシンプルな味わいが特徴。
Back